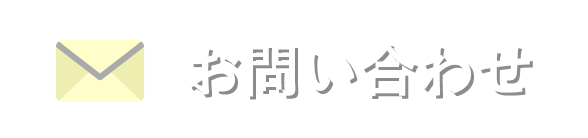- トップページ
- 債務整理 弁護士コラム
- その他
- 年金の特別催告状を無視するとどうなる? 払えないときの対処法
債務整理 弁護士コラム
年金の特別催告状を無視するとどうなる? 払えないときの対処法
- その他
- 年金
- 特別催告状

国民年金保険料の滞納があると、年金事務所から「特別催告状」が届くことがあります。
とはいえ、生活費に余裕がなく未納の保険料を支払えない方もいることでしょう。中には、「将来に年金がもらえるかどうかがわからない」といった不安感などから、国民年金保険料を支払いたくないという方もいるかもしれません。
しかし、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方にはすべて、国民年金保険料の納付が法律で義務付けられています。そのため、国民年金保険料を未納のままにしておくと深刻な事態に陥ることがあることに、注意が必要です。
本コラムでは、国民年金の特別催告状を無視するとどうなるのか、どうしても保険料を支払えないときはどうすればよいのかについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
この記事で分かること
- 国民年金保険料を支払わないときに生じるリスク
- 特別催告状が届いてから差し押さえになるまでの流れ
- 国民年金保険料を支払えないときの対処法
1、年金の特別催告状とは
年金の特別催告状は、国民年金保険料を滞納している人に対して、年金事務所が納付を請求するために送付する書面のひとつです。
保険料を滞納すると、その翌月末までにまず「催告状」が届きます。催告状に記載されている期限までに未納保険料を納付しない場合に、改めて送付されるのが特別催告状です。
滞納を続けていると特別催告状が3回にわたって届き、封筒の色が青色から黄色、赤(ピンク)色へと変化していきます。後になるほど警告の意味合いが強まり、記載内容も厳しいものになっていきます。
2、国民年金保険料を払わないとどうなる?
国民年金保険料を払わないままにしておくと、以下のように深刻なデメリットが生じます。
-
(1)延滞金がかかる
滞納を続けていると、未納の保険料に加えて延滞金の納付義務が発生します。ただし、延滞金がかかり始めるのは特別催告状よりも後に届けられる「督促状」で指定される納付期限の翌日からです。
延滞金の利率は年によって変動しますが、令和5年度は納付期限の翌日から3か月までが年2.4%、その翌日以降が年8.7%とされています。 -
(2)将来の年金が減額または受け取れなくなる
国民年金(老齢基礎年金)の支給額は年によって変動しますが、令和5年度は満額で79万5000円です。ただし満額を受給するためには、20歳から60歳までの40年間(480か月)、保険料を全額支払い続けることが条件とされています。そのため、未納があると将来受給できる年金額が減らされてしまいます。
保険料を納付した期間が10年に満たない場合は受給資格を満たさないため、1円も年金を受け取れなくなることに注意が必要です。保険料の免除や納付猶予を受けた期間は受給資格期間に算入されますが、全額納付した場合よりも受給額は減額されます。 -
(3)財産を差し押さえられる
特別催告状や督促状を無視していると「滞納処分」が行われ、最終的に財産を差し押さえられることになります。
差し押さえを受けやすいのは、給料と預金口座です。給料は全額が差し押さえとなるわけではありませんが、一部が差し引かれるために生活費に支障をきたす可能性が高いでしょう。預金口座を差し押さえられた場合は、預金全額が突然なくなる可能性があるので、当座の生活費も不足するおそれがあります。
その他にも、車や不動産、有価証券、生命保険、自営業をしている方なら売掛金などが差し押さえられることもあるので、注意が必要です。
3、特別催告状が届いてから差し押さえ実行までの流れ
特別催告状が届いても、すぐに差し押さえを受けるわけではありません。ここでは、特別催告状が届いてから実際に差し押さえを受けるまでの流れをご紹介します。
-
(1)納付の要求が繰り返される
国民年金保険料の滞納が発生すると、滞納処分が行われる前に何度も納付の要求を受けます。具体的には、年金事務所(日本年金機構)から以下の順でハガキや封書が送られてきます。
- 催告状
- 特別催告状
- 最終催告状
- 督促状
この他にも、年金事務所が委託した民間事業者の担当者から、電話や自宅訪問、文書の送付によって納付を要求されます。
そして、督促状で指定された納付期限までに未納保険料を支払わなければ、滞納処分が開始されます。ただ、その後も当面の間は、電話や自宅訪問、文書の送付による納付要求が繰り返されます。 -
(2)財産調査を受ける
再三にわたる納付要求を無視していると、いよいよ差し押さえに向けた本格的な準備が始まります。
まず行われるのは「財産調査」です。これは、差し押さえの目的となるものを特定するための調査です。財産調査では、まず年金事務所が官公署や金融機関、法務局などへ情報提供を求め、勤務先や預金口座、所有不動産の有無などを調べます。
その上で必要があれば、担当者が滞納者の自宅に訪問して事情を尋ねたり、資料の提供を求めたりします。それだけでなく、家族や勤務先、取引先に対する聴き取り調査が行われることもあるので注意が必要です。財産の有無と内容を、徹底的に調べられることを覚悟しておかなければなりません。 -
(3)差押予告通知書が届く
財産調査が終了すると、日本年金機構から差押予告通知書が届きます。
ただ、差押予告通知書が届いても、まだすぐに差し押さえが行われるわけではありません。この通知書にも未納保険料と延滞金の金額と納付期限が記載されており、その期限までに納付すれば差し押さえを回避できます。
差押予告通知書には、最終の警告書という意味合いもあるのです。 -
(4)差し押さえ・換価
差押予告通知書も無視すると、実際に差し押さえが行われます。その後に届く書類が「差押通知書」です。
差し押さえられた財産は換価され、未納保険料と延滞金に充当されます。給料が差し押さえられた場合は、手取り額の4分の1の金額が勤務先から日本年金機構へ支払われます。預金口座が差し押さえられた場合は、未納保険料と延滞金の合計額を上限として、預金が金融機関から日本年金機構へ支払われるという仕組みです。
自動車などの動産や自宅などの不動産を差し押さえられた場合は、換価(売却)されるまでにある程度の時間がかかります。速やかに滞納を解消すれば、差し押さえを解除することも可能です。しかし、放置すると換価され、その財産を失うことになります。
4、国民年金保険料が払えないときの3つの対処法
差し押さえを回避するためには、滞納を解消しなければなりません。ただ、毎月の年金保険料の支払いに加えて未納保険料や延滞金を一度に支払うことは難しい場合も多いでしょう。そんなときには、以下の対処法があります。
-
(1)年金事務所に連絡する
まずは、年金事務所に連絡することです。
事情を伝えて相談すれば、未納保険料の分割払いが認められる可能性があります。そのためには、滞納したことを反省するとともに、毎月いくらずつなら支払えるのかという納付計画を提案するなどして、納付に対する誠実な意思を示すことが重要です。
分割払いの相談は差し押さえが実行されるまで可能ですが、早ければ早いほど柔軟に対応してもらえる可能性が高くなります。そのため、遅くとも赤(ピンク)色の特別催告状が届いた時点で年金事務所に連絡した方がよいでしょう。 -
(2)保険料の免除・猶予を申請する
一定の条件を満たす場合には、年金事務所に申請することにより、保険料の免除や納付猶予が受けられます。
保険料の免除は、前年所得(1月~6月に申請する場合は前々年所得)が一定の基準以下の場合に、保険料の納付が免除される制度です。所得(世帯主と配偶者の所得も含みます)に応じて、全部または一部の納付が免除されます。
納付猶予は、20歳以上50歳未満の人について、所得に関する条件を満たす場合に納付が猶予される制度です。
また、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した場合には、保険料免除・納付猶予の臨時特例が受けられる可能性もあります。通常は前年所得または前々年所得に基づいて保険料免除・納付猶予の可否が判断されますが、臨時特例においては申請する当年の所得の見込みに基づいて判断してもらえます。
これらの申請が承認されても未納保険料や延滞金は免除されませんが、毎月の保険料が免除・猶予されることで未納分を支払いやすくなるでしょう。 -
(3)債務整理を検討する
借金の返済に追われて年金保険料の納付が難しい場合には、債務整理が有効です。年金保険料は債務整理の対象外ですが、借金返済の負担を減免することで、毎月の年金保険料や未納分の納付が容易となるでしょう。
債務整理には、主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」という3種類の手続きがあります。状況に合った手続きを選択することが、スムーズに借金問題を解決するためのポイントです。
5、まとめ
年金保険料を滞納し、特別催告状が届いたということは、差し押さえに向けた手続きが進行しつつあることを意味しています。特別催告状が届き次第、滞納分の料金を支払うなど、早めに対応することが必要です。
借金を抱えて支払いに困っているときには、弁護士に相談して、債務整理で借金問題を解決することをおすすめします。
弁護士は、状況に合った最適な手続きについてアドバイスをするだけでなく、複雑な手続きをすべて代行することが可能です。
ベリーベスト法律事務所では、知見・経験豊富な弁護士が債務整理手続きの選択から最終的な解決に至るまで、お客さまを全面的にサポートいたします。債務整理に関するご相談は何度でも無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

- 萩原達也 代表弁護士
- 弁護士会: 第一東京弁護士会
- 登録番号: 29985
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
債務整理、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金請求など、借金問題についてのお悩み解決を弁護士がサポートいたします。債務整理のご相談は何度でも無料です。ぜひお気軽に お問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています


同じカテゴリのコラム(その他)
-
更新: 2025年06月26日
- その他
- 異動情報

異動情報とは|いつ消えるか、CICの記録から消す方法を弁護士が解説
借金の支払いが遅れたり、債務整理が行われたりすると、個人信用情報機関に「異動情報」が登録されます。
異動情報が登録されると、ローンを借りられなくなったり、クレジットカードが使えなくなったり、さまざまなデメリットが生じることに注意が必要です。そのため、債務整理を行う前に、異動情報に関する注意点を理解しておきましょう。
本記事では、債務整理などによって登録される異動情報について、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。コラム全文はこちら -
更新: 2025年06月18日
- その他
- 第三者弁済

第三者弁済とは? 弁済が有効となる要件や影響、代位について解説
お金を借りた債務者本人に代わって、第三者が借金などの債務を返済するケースがあります。このような第三者弁済が行われるケースは少なくありませんが、あらゆる場合に第三者弁済が有効となるわけではありません。
また、第三者が弁済する場合であっても、民法上の「第三者弁済」には該当しないことがあります。第三者弁済に当たるケースとその他のケースの違いについて、知っておいたほうがよいでしょう。
なお、第三者弁済が有効に行われると債権者は満足しますが、弁済した第三者と債務者との間には債権・債務関係が残ることに注意が必要です。
本コラムでは、第三者弁済とは何か、第三者弁済が有効となるための要件、さらには弁済した第三者による「代位」について、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。コラム全文はこちら -
更新: 2025年06月13日
- その他
- 借金減額
- 仕組み

借金減額の仕組みとは? 罠やデメリット、正しい方法も解説
「借金減額」という広告を目にすると「怪しい」と感じるかもしれませんが、法律に従った方法で借金を減額できる仕組みもあります。借金減額の方法にはいくつかの種類があり、それぞれ仕組みが異なります。
減額効果が高い方法ほど大きなデメリットが生じる可能性もあるため、方法の選択を誤ると「罠だった」と感じてしまうこともあるかもしれません。
本コラムでは、借金減額がどのような仕組みで可能となるのか、悪徳業者の罠ではないのか、どのようなデメリットがあるのか、正しい借金減額の方法とは何か、などについて解説します。コラム全文はこちら
カテゴリを選ぶ
- トップページ
- 債務整理 弁護士コラム
- その他
- 年金の特別催告状を無視するとどうなる? 払えないときの対処法