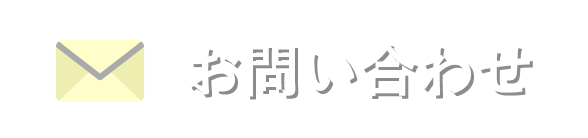- トップページ
- 債務整理 弁護士コラム
- 借金問題
- 銀行口座の差し押さえでどうなる? 差し押さえの流れや回避方法
債務整理 弁護士コラム
銀行口座の差し押さえでどうなる? 差し押さえの流れや回避方法
- 借金問題
- 差し押さえ
- 銀行

銀行口座は、資産管理を行う上で欠かせません。万が一のために蓄えを備えるだけでなく、給料の受け取りや決済用の手段としても、必須のツールです。
しかし、借金の返済などを滞納してしまえば、銀行口座が差し押さえにあってしまうこともあります。債権者にとっても銀行口座の預貯金は、滞納した借金を回収するための重要な引き当て財産だからです。
令和2年4月に改正民事執行法が施行され、債権者による債務者の財産調査が容易になりました。そのため、銀行口座は以前よりも差し押さえやすくなったといえます。
銀行口座に限った統計ではありませんが、裁判所が公表する「令和5年 司法統計年報」によると、「債権及びその他の財産権に対する強制執行」の手続きが裁判所で行われた数は、14万3400件でした。うち12万2649件は、取り下げられています。
本コラムでは、借金の返済を滞納して銀行口座が差し押さえられてしまうときの流れや効果、差し押さえを回避する方法などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、銀行口座が差し押さえられるまでの流れ
まずは、借金などの支払い・返済を滞納してしまった場合を例に、銀行口座が差し押さえられてしまうまでの基本的な流れについて、確認しておきましょう。
-
(1)支払い・返済の滞納
銀行口座などの財産の差し押さえには、それを正当化できる理由がなければなりません。借金の返済を怠ってしまうことは、その典型例です。
とはいえ、実際に借金の返済を滞納した場合であっても、最初の滞納(返済遅れ)の時点で、いきなり銀行口座が差し押さえられることはないので、ご安心ください。この程度の返済の遅れにすぎない場合には、債務者の期限の利益(一括弁済を要求されない権利)は失われていません。 -
(2)債権者による債務名義の獲得
しかし、借金の滞納が長期に及んでしまった場合には、事前に締結した債権者とのローン契約に基づいて、期限の利益を失ってしまうことになります。このような場合には、債権者から「残額の一括返済」を求められることになりますが、毎月の返済ができない状況で、残額の一括返済に応じられるというケースは、ほとんどないといえるでしょう。
そのため、その後の話し合いがまとまらない(分割返済をやり直す合意ができない)ときには、債権者は民事訴訟や督促手続き(支払督促)を申し立て、法的な手続きによる債権回収を図ることになります。債権者は、民事訴訟や支払督促によって、「債務名義」とよばれる書類(確定判決など)を獲得しなければ、差し押さえを行うことができないからです。 -
(3)強制執行(債権差し押さえ)の申し立て
債権者が債務名義を獲得した後も、債務者が任意の返済に応じない場合には、いよいよ債務者の財産の差し押さえによる回収が行われます。
債務者の財産差し押さえの手続きは、債権者が裁判所に申し立てをします。そのとき、差し押さえを認めるかどうかの審理は、債務者には知らされないまま行われることになります。差し押さえにあうかもしれないということを、債務者に事前に知られてしまえば、妨害にあってしまう可能性があるからです。 -
(4)裁判所による債権差押命令
裁判所が銀行口座の差し押さえを認めた場合には、裁判所から第三債務者(この場合には差し押さえられる預金のある銀行)と債務者(差し押さえられる口座の名義人)とに、債権差し押さえの命令が送達されます。
したがって、債務者としては差し押さえが認められた段階で、初めてその事実を知るということになります。万が一、理由のない差し押さえにあったという場合には、差し押さえについての異議を裁判所に申し立てることで対応します。 -
(5)債権者による取り立て
差し押さえを申し立てた債権者は、銀行口座の差し押さえから1週間が経過したときには、差し押さえた預貯金を銀行から取り立てることができます。
この1 週間という期間は、上で触れた債務者からの異議申し立てに対応するための期間でもあります。
2、差し押さえられた口座は使えるのか?
債権者から銀行口座を差し押さえられた場合には、その口座はどうなってしまうのか、不安に思う方も多いことでしょう。銀行口座が差し押さえにあった場合の取り扱いは、差し押さえた債権者の違いによって異なる場合が多いといえます。
-
(1)債権者が口座のある銀行以外であった場合(通常のケース)
通常の差し押さえであれば、その時点の残高は引き出せなくなります。しかし、その銀行口座が凍結されることはなく、その後も利用が可能です。給料の振り込みも通常通りに行われますし、自分で口座に入金することや、差し押さえ後の入金であれば預金の振替も可能です。
-
(2)銀行からの借金を滞納してしまった場合 口座の凍結と差し押さえの違い
しかし、銀行からの借金を滞納してしまった場合には、上記の取り扱いと異なることが多いことに注意が必要です。
銀行カードローンなどを長期間滞納した場合には、ローン契約に基づいて「銀行口座の凍結」が行われることがあります。この銀行口座の凍結と裁判所による銀行口座の差し押さえには、次のような違いがあります。- 銀行による口座凍結は、訴訟・支払督促を経由しなくても行われる
- 銀行口座が凍結された場合には、解除されるまで出金(および入金)ができなくなる。
わかりやすくいえば、裁判所による口座の差し押さえは、預金口座にあるお金だけを対象に行われるものですが、銀行による口座凍結は、銀行口座それ自体の利用停止と預金の差し押さえがセットになったものです。
したがって、銀行カードローンを滞納し、給料振込口座・公共料金の振替口座が凍結されてしまった場合には、給料が振り込まれない、料金が引き落とされないといった不都合が生じることもあります。
3、差し押さえのタイミングや回数について
銀行口座の差し押さえのおそれがある人の中には、そのタイミングや、回数が気になるという人も多いと思いますので、以下解説していきます。
●口座の差し押さえが行われやすいタイミング
債権者は、債権を回収する目的で銀行口座の差し押さえをします。銀行口座の差し押さえは、差し押さえの時点での預貯金を対象とするので、債権者としては「銀行口座に預貯金残高があるタイミング」を狙って、差し押さえの申し立てを行うことが重要となってきます。
したがって、銀行口座の差し押さえは、毎月の給料日や振替日の直前(5日・10日・月末など)などを狙い撃ちして行われることが多いといえます。
●預金の差し押さえは一度だけ
銀行口座(預貯金債権)の差し押さえは、ひとつの申し立てについて一度しか行われません。つまり、債権者が100万円の回収を図ろうとして預貯金を差し押さえたが、預貯金残額が10万円だったという場合でも、それ以後の入金額について差し押さえは行われないということです。
4、給与債権の差し押さえとは
なお、同じ債権の差し押さえであっても、給料債権が差し押さえされることもあります。この場合には、借金の完済まで差し押さえがずっと続きます。同じ債権の差し押さえであっても、取り扱いが違うことに注意しましょう。
給料が差し押さえられる場合と、預貯金が差し押さえられる場合とでは、その金額にも大きな違いがあります。
給料は、法律によって給料の1/4以上の差し押さえが禁止されています。なお、手取り額が44万円以上であれば、33万円を超えた金額を差し押さえられることがあります。
一方で、預貯金の差し押さえの場合には、その上限金額は設けられていません。
したがって、預貯金債権の差し押さえの場合には、借金の金額によっては、その時点で銀行の口座残高が0円になってしまうこともあります。
5、債務整理による差し押さえの停止
ここまで解説してきたように、銀行口座を差し押さえるためには、民事訴訟や支払督促といった手続きを経る必要があります。その意味では、「完全に不意打ち」というような形で、突然銀行口座が差し押さえられるということはありません。
しかし、借金問題は他人に相談しづらいこともあり、気が付いたときには、銀行口座の差し押さえが目前に迫っている(支払督促が届いていたのに無視してしまったケースなど)こともあるかもしれません。
このような場合には、早急に弁護士に債務整理を依頼すれば、銀行口座の差し押さえを回避できる可能性があります。
たとえば、債務整理の一種である、自己破産や個人再生を申し立てた場合には、債権者がそれまでに銀行口座の差し押さえを申し立てていたとしても、それはすべて停止となるからです。
また、弁護士に依頼すれば、債権者も「一定の金額については返済してもらえる」という期待が生まれ、差し押さえよりは弁護士と交渉してみようと考えるケースもあります。
6、まとめ
借金の返済に行き詰まってしまった方にとって「銀行口座が差し押さえられるかもしれない」という不安は、精神的に大きな負担となる場合が多いでしょう。
差し押さえを回避しようと無理な金策を重ねた結果、状況がさらに悪化してしまうというケースも珍しくありません。
債権者による銀行口座の差し押さえは、適切に対処することで回避できる可能性もあります。そのためには、弁護士への早めの相談が重要です。
ベリーベスト法律事務所では、借金問題に関する経験・知見豊富な弁護士が親身になって、最善の対応策をアドバイスさせていただきます。
当事務所での債務整理のご相談は何度でも無料となっておりますので、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

- 萩原達也 代表弁護士
- 弁護士会: 第一東京弁護士会
- 登録番号: 29985
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
債務整理、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金請求など、借金問題についてのお悩み解決を弁護士がサポートいたします。債務整理のご相談は何度でも無料です。ぜひお気軽に お問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています


同じカテゴリのコラム(借金問題)
-
公開: 2025年07月02日
- 借金問題
- 借金癖

借金癖を放置するのは危険! 借金癖を改善するための5つの方法を解説
借金癖とは、何度も借金を繰り返してしまうことをいいます。借金癖がある人は、借金をすることに抵抗感がありませんので、借金を繰り返すうちに返済ができない状態に陥ってしまうこともあります。
借金癖を改善するにはいくつかの方法がありますが、自分で対応が困難な状態になってしまったときは、早めに弁護士に相談して、債務整理を行うようにしましょう。
今回は、借金癖を放置することで生じるリスクと借金癖を改善するための5つの方法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。コラム全文はこちら -
更新: 2025年06月30日
- 借金問題
- 訴訟予告書

訴訟予告書とは? 滞納ペナルティと届いたときに検討すべきこと
借金問題は、放置期間が長ければ長いほど深刻化しやすい傾向があることが特徴です。
たとえば借金の滞納状態が深刻になると、債権者から訴訟予告書(訴訟等申立予告通知書)が届くことがあります。
訴訟予告書が届くのは、すでに高額の遅延損害金が発生しているということです。近い将来には強制執行による債権回収が迫っているため、できるだけ早いタイミングで解決に向けて踏み出さなければいけません。
本コラムでは、訴訟予告書とは具体的にどういうものか、また届いたときのデメリットや検討するべきことなどについて、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門的チームの弁護士が解説します。コラム全文はこちら -
更新: 2025年06月18日
- 借金問題
- 借金取り
- 借金
- 取り立て
- 家に来る

借金取りは家に来る!? 借金を取り立てにやってきたときの対処法
「借金を滞納してしまったから、借金取りが家や勤務先に押しかけてくるのではないか」「取り立てのために家に居座られたりしたらどうしよう」といったように、借金に関して不安に感じていることがある方もいるでしょう。
1998年から1999年にかけて、商工ローンの大手だった旧商工ファンドと日栄が「腎臓を売れ」「目玉を売ってでも借金返せ」と債務者に違法な取り立てを行い、大きな話題となったこともありました。
しかし、結論からいえば、借金取りに関して心配をする必要はありません。金融機関に対する規制は、当時よりもかなり厳しくなっているからです。
本コラムでは、借金取りが自宅や勤務先にやってきてしまう具体的なケースや、借金取りが自宅などにきてしまったときの対処方法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。コラム全文はこちら
カテゴリを選ぶ
- トップページ
- 債務整理 弁護士コラム
- 借金問題
- 銀行口座の差し押さえでどうなる? 差し押さえの流れや回避方法