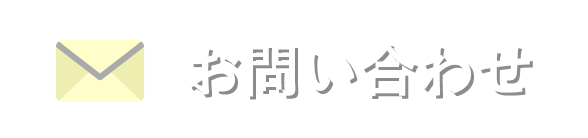- トップページ
- 債務整理 弁護士コラム
- その他
- 勝手に連帯保証人にされた! 支払いの拒み方と拒めない時の対処法
債務整理 弁護士コラム
勝手に連帯保証人にされた! 支払いの拒み方と拒めない時の対処法
- その他
- 連帯保証人
- 勝手に

連帯保証人に勝手にされてしまい、支払いを拒みたいけれど可能なのでしょうか。
他人の借金などの連帯保証人になると、本人が返済できない場合には代わりに返済しなければなりません。分かっていても、知らないところで勝手に連帯保証人にされていたら、納得できるものではないでしょう。
自分の意思で連帯保証人になったのでない以上、原則として返済する必要はありませんが、場合によっては例外的に支払い義務が生じることもあります。
この記事では、勝手に連帯保証人にされた場合に、債権者から支払いを請求された時の拒み方と、拒めない場合の対処法をベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、連帯保証人の支払い義務の内容
借金の連帯保証人とは、お金を借りた債務者本人(主債務者)と同一の責任を負う保証人のことです。
そもそも保証人とは、主債務者が債務を履行しない時に、代わりに履行する責任を負います(民法第446条1項)。
通常の保証人には「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」というものが認められています。
債権者から返済の請求を受けた場合には、まず主債務者に請求すること(催告の抗弁権、同法第452条)と、主債務者に弁済の資力がある場合には先に主債務者から取り立てるべきこと(検索の抗弁権、同法第453条)を主張し、返済を拒めます。
また、保証人が複数いる場合には、均等な割合で割った金額だけを返済すれば責任を果たしたことになり、残りの債務を支払う必要はありません(分別の利益)。
一方で、連帯保証人は主債務者と同一の責任を負うため、主債務者よりも先に請求を受けても拒むことができず、常に全額の返済義務を負います。
以上のように、連帯保証人の責任は通常の保証人の場合よりも重いことから、勝手に連帯保証人にされた場合には深刻なリスクが生じがちです。
2、勝手に連帯保証人にされた場合に支払う義務はある?
勝手に連帯保証人にされた場合に支払い義務を負うかどうかについては、以下のようにケースごとに慎重に判断する必要があります。
-
(1)契約書がなければ支払い義務なし
保証契約は、書面で行わなければ効力が生じないものとされています(民法第446条2項)。
連帯保証契約にもこの規定は適用されるので、契約書が作成されていない場合には、連帯保証人に支払い義務はありません。 -
(2)契約書があっても原則として支払い義務なし
契約は当事者双方の意思が合致して初めて成立するものです。自分で連帯保証をする意思を表示していないのであれば、契約は成立しないのが原則です。
勝手に契約書が作成されていたとしても、勝手に連帯保証人とされた人には、原則として支払い義務がありません。 -
(3)追認した場合は支払い義務あり
主債務者が他人の印鑑を持ち出すなどして、無断でその人に代わって契約を結ぶ行為のことを、法律上は「無権代理」といいます。無権代理として行われた行為は、原則として無効です。
ただし、無権代理行為をされた人がその行為を追認すると、正当な代理権に基づいて行われた行為と同様に有効となります。
勝手に連帯保証人にされた場合でも、債権者から請求を受けた時に反論せず支払いの約束をすると追認とみなされ、その後は支払いを拒否できなくなってしまいます。 -
(4)表見代理が成立する場合も支払い義務あり
無権代理で連帯保証契約が行われた場合でも、代理権があるものと相手方(債権者)が信じてもやむを得ないような事情がある時には、契約が有効となることがあり、これを「表見代理」といいます。
表見代理が成立するケースには、以下の3種類のパターンです。① 代理権授与表示による表見代理
実際には代理権を与えていなくても、与えたかのような外観を作出した場合、その代理権の範囲内で行われた行為は、相手方が善意・無過失である限り有効な代理行為となります(民法第109条1項)。たとえば、AさんがBさんに対し、C銀行から借金をする際の連帯保証人になることを承諾したのに対して、Bさんが勝手に知人のDさんから借金し、Aさんを連帯保証人にするようなケースが考えられます。
② 代理権限外行為による表見代理
実際に代理権が与えられたものの、代理人がその権限外の行為をした場合は、相手方が代理権の範囲内の行為であると信じることについて正当な理由がある時に限り、有効な代理行為となります(民法第110条)。たとえば、AさんがBさんに対し、50万円までの借金なら連帯保証人になることを承諾したのに対して、Bさんが勝手に200万円の借金についてAさんを連帯保証人にするようなケースが考えられます。
③ 代理権消滅後の表見代理
与えられた代理権がなくなった後、代理人だった人がまだ代理権があるかのように装い、代理権の範囲内の行為をした場合は、相手方が代理権消滅の事実を知らず、知らなかったことにつき過失もない場合に限り、有効な代理行為となります。(民法第112条1項)。たとえば、AさんがBさんの借金について連帯保証人になることを承諾したものの、急な出費が必要となったことから承諾を撤回した後、Bさんが勝手にAさんを借金の連帯保証人にするケースが考えられます。
3、勝手に連帯保証人にされた場合に支払いを拒む方法
勝手に連帯保証人にされ、債権者から支払いを請求された場合に拒否する方法を見ていきましょう。
-
(1)事実関係を確認し、弁護士に相談する
まずは、債権者に対して追認しないように注意しつつ、表見代理が成立していないかどうかを確認しましょう。
ただ、この確認は非常に難しいことが多いので、弁護士に相談する方が得策です。
無権代理人との間でどのようなやりとりをしたのか、無権代理人がどのような契約をしたのかといった事実関係を確認した上で、弁護士に相談してアドバイスを受けることをおすすめします。 -
(2)内容証明郵便を送付し、契約無効を主張する
表見代理が成立していない場合は、債権者に対して、その連帯保証契約は無権代理行為であって無効であること(支払う意思はないこと)を告げます。
それでも請求が止まらない場合には、同じ内容を記載した書面を作成し、内容証明郵便で債権者へ送付します。債権者によっては、この書面を稟議(りんぎ)にかけ、請求を断念することもあります。 -
(3)相手と折り合わなければ、法的手続きへ
債権者が請求を止めない場合は、法的手続きで連帯保証契約の無効を明らかにする必要があります。
自分の方から「債務不存在確認訴訟」を起こすことも可能ですが、手間と費用がかかるため、債権者に対して、「どうしても請求するなら訴訟を提起してください」と伝えて、様子をみるのが一般的です。
本当に訴訟を起こされた場合には、無権代理人とのやりとりや無権代理人の行為の内容などを証明することにより、表見代理が成立していないことを立証していきます。
4、支払いを拒否できない時の対処法
表見代理が成立するか、追認してしまった場合は、残念ながら全額について支払いを拒否できません。請求されたとおりに支払えない場合には、以下の対処法が考えられます。
-
(1)分割払いの交渉をする
通常は債権者から一括での返済を請求されますが、ほとんどの場合は話し合いにより分割払いで和解することが可能です。債権者と交渉の上、支払い可能な内容での和解成立を目指しましょう。
-
(2)債務整理をする
分割払いの交渉がまとまらない場合や、そもそも返済する余裕がない場合には、債務整理を検討するのが得策でしょう。連帯保証債務も債務整理の対象となります。
負債総額が比較的して小さい場合には、まず任意整理で解決できないかを検討してみましょう。
ただし、任意整理では基本的に元金は全額支払う必要があるため、負債総額が大きい場合には個人再生または自己破産を検討する必要があります。
無権代理人に対する求償債権(民法第459条1項)は財産に当たるので、個人再生および自己破産の手続きに支障をきたすおそれがあります。
スムーズに手続きを進めるためには、無権代理人が経済的に困窮していて求償債権が回収不能であることを立証する必要があります。
どの債務整理手続きが適しているかを判断するためには、専門的な知識が要求されるので、弁護士に相談して検討することをおすすめします。
5、まとめ
勝手に連帯保証人にされても原則として支払い義務を負いませんが、表見代理が成立する場合には支払いを拒否できません。
同居の家族が無権代理行為をした場合は、友人・知人などが行った場合よりも表見代理が成立する可能性が高くなります。
自己判断で進めると対応を誤る可能性が高く、最悪の場合は債権者から訴訟を起こされて財産の差し押さえを受けるおそれもあります。早期に弁護士に相談し、正しく対処していくことが大切です。
ベリーベスト法律事務所では、借金問題の対応経験を豊富に有する弁護士が対応し、どんな疑問にもお答えいたします。お困りの際は、当事務所の無料相談をご利用ください。

- 萩原達也 代表弁護士
- 弁護士会: 第一東京弁護士会
- 登録番号: 29985
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
債務整理、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金請求など、借金問題についてのお悩み解決を弁護士がサポートいたします。債務整理のご相談は何度でも無料です。ぜひお気軽に お問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています


同じカテゴリのコラム(その他)
-
公開: 2026年01月29日
- その他
- 保証債務とは

【事例でわかる】保証債務の仕組みとリスク軽減のための具体策
友人や親族から「保証人になってほしい」と頼まれた際、断りづらさから安易に応じてしまう人もいます。しかし、保証契約は単なる形式的な署名ではなく、保証人に重い法的責任を負わせるものです。
特に「連帯保証」では、債権者が主債務者を飛ばして直ちに保証人へ請求できるため、負担は極めて重くなります。
今回は、保証債務の定義や仕組み、通常の保証と連帯保証の違い、保証人が直面するリスクや責任範囲などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。コラム全文はこちら -
公開: 2026年01月15日
- その他
- 差し押さえ
- 持っていかれるもの

差押えで持っていかれるもの、持っていかれないものをカンタンに解説
借金の返済が滞ってしまうと、最終的に「差押え」という強制執行に発展することがあります。差押えで持っていかれる可能性があるものには、預金や給与の一部、不動産や車など、日常生活に欠かせない財産が含まれており、生活への影響は計り知れません。
しかも、借金の返済が滞った場合、信用情報に影響が出るため、クレジットカードの利用停止がなされる場合もあります。また、差押えされた場合、銀行口座が凍結されたり、勤務先に借金が知られたり、信用や人間関係にまで波及する場合があります。そのため、精神的な負担も非常に大きく、日常生活そのものが立ち行かなくなるケースも少なくありません。
もっとも、すべての財産が差押えの対象になるわけではなく、法律で「生活に最低限必要な財産」は守られています。また、事前に債務整理を行うことで差押えを防ぐことも可能です。今回は、差押えで持っていかれるもの・持っていかれないもの、差押えが生活に与える影響などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。コラム全文はこちら -
更新: 2025年12月25日
- その他
- 闇金

闇金被害は弁護士に相談を! 悪質な手口や正しい対処法を解説
一般的な金融機関から借り入れができなくなって闇金に手を出してしまい、深刻な被害に遭ってしまう人は後を絶ちません。
闇金は、「審査なし」「ブラックOK」「誰でも即日融資」などの甘い文句で勧誘してくるものです。しかし、闇金は到底支払えないような高金利を要求し、支払いが遅れるとしつこい取り立てや悪質な嫌がらせによって精神的に追い込んできます。
ご自身だけでなく、家族や知人、職場にまで被害が及ぶ可能性も高いので、絶対に闇金に手を出してはいけません。もしお金を借りてしまったら、すぐに弁護士へ相談しましょう。
本コラムでは、闇金とはどのような業者のことをいうのか、闇金が使う具体的な手口、お金を借りてしまったときの対処法などについて、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。コラム全文はこちら
カテゴリを選ぶ
- トップページ
- 債務整理 弁護士コラム
- その他
- 勝手に連帯保証人にされた! 支払いの拒み方と拒めない時の対処法