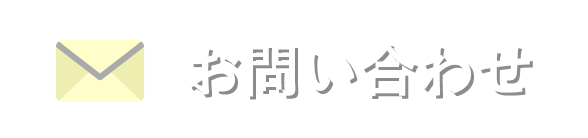- トップページ
- 債務整理 弁護士コラム
- その他
- 時効の援用とは? 借金の消滅時効を主張するために必要な手続き
債務整理 弁護士コラム
時効の援用とは? 借金の消滅時効を主張するために必要な手続き
- その他
- 時効の援用

時効の援用は、時効が完成したことによって発生する利益を受けるために必要な手続きです。借金については、消滅時効期間が経過しさえすれば、返済義務が消滅すると考えている人が多いことでしょう。
しかし、時効の援用をしなければ、債権者が返済を請求してくることが多々あります。そのときに、少しでも返済したり、返済の約束をしたりすると、時効の援用ができなくなってしまうことに注意が必要です。
本コラムでは、時効の援用とは何かを詳しく解説するとともに、時効の援用を正しく行う方法や、その際の注意点についても解説します。
1、時効の援用とは?
「時効の援用」とは、時効が完成したことで生じる利益を受ける旨を、相手方に対して伝える行為のことです。
借金の返済義務は5年~10年で消滅時効にかかりますが、時効の援用をしなければ借金は消滅しません(民法第145条)。法律上、時効の利益を受けるかどうかは当事者の自由意思に委ねられています。
債務者が債権者に対して、「この借金については消滅時効が完成したので、支払いません」と意思表示して初めて、借金が消滅します。この意思表示が「時効の援用」です。
債務者が時効の援用をするまで、債権者には法律上の請求権が残っています。そのため、消滅時効が完成した借金の返済を請求されたとしても、その請求は違法ではありません。
2、借金の消滅時効を援用するときの注意点
時効援用の手続き自体は難しいものではありませんが、いくつかのポイントに注意して行わなければ失敗する恐れがあります。
-
(1)時効期間が経過しているか確認する
時効の援用は、時効が完成した後に行う必要があります。当然のことと思われるかもしれませんが、時効完成前に時効援用の連絡をしてしまい、それがきっかけで債権者に連絡先を知られ、請求を受けてしまうケースは少なくありません。この場合、ある程度の期間は時効が進行していたにもかかわらず、債権者に時効の進行を止められてしまう可能性が高くなります。
まずは、時効期間が経過しているかどうかを確認しましょう。借金の消滅時効期間は、最後の取引から5年です(民法第166条1項1号)。ただし、個人間の借金で、2020年3月31日以前に取引したものについては旧民法が適用されるため、時効期間が10年となることに注意が必要です。 -
(2)時効が更新されていないか確認する
消滅時効期間が経過していても、時効が更新されている場合には、消滅時効は完成していません。時効の更新とは、一定の事由が発生した場合に、それまで進行していた時効期間がリセットされてゼロに戻り、そのときから新たに時効が進行することをいいます。
時効の更新事由には、主に債権者からの「請求」と、債務者による「承認」があります。
債権者が民事訴訟や支払い督促の手続きで借金の返済を請求すると、その時点で時効の完成が猶予されます。そして、支払いを命じる判決が確定し、または仮執行宣言付支払督促に対して債務者が督促異議を申し立てずに2週間が経過すると、時効が更新されます(民法147条1項1号、2号)。この場合、新たな時効期間は10年となることにも注意が必要です(同法第169条1項)。なお、債権者が裁判外で催告書の送付などにより請求したときは、そのときから6か月間だけ、時効の完成が猶予されます。
債務者による承認とは、債権者に対して債務の存在を認める行為のことです。時効完成前に借金を1円でも返済した場合や、債権者に対して「○月までに支払います」と支払いの約束をしたり、「今すぐには支払えないので待ってほしい」と支払いの猶予と求めたりすると、債務を承認したことになります。債務を承認した時点で時効が更新され、新たに5年の時効期間が進行し始めます。 -
(3)債務承認に当たる行為をしないよう注意する
時効完成後も、債務の承認には注意が必要です。消滅時効の援用をしようとして債権者に電話連絡をすると、担当者によって言葉巧みに債務承認に該当する言動を引き出される恐れがあるからです。
たとえば、「1000円だけでも支払ってほしい」と言われて支払ったり、「いくらなら支払えますか」と尋ねられて「○万円なら支払えます」と支払いの約束をしたりすると、債務を承認したことになってしまいます。
時効完成後でも債務を承認すると、時効の利益を放棄したことになり、そのときから5年が経過するまで時効が完成しなくなります。時効の援用をするときは安易に電話連絡などをせず、正しい手順を踏むことが重要です。
3、時効の援用をする方法
時効の援用をするための正しい手順は、以下のとおりです。
-
(1)時効援用通知書を内容証明郵便で送付する
時効の援用をするときには証拠を残すことが重要です。証拠がなければ、後に債権者から請求された場合に、返済を拒否することが難しくなる恐れがあります。そのため、書面の送付により時効を援用することが重要です。この書面を「時効援用通知書」といいます。
時効援用通知書に、時効が完成した借金を特定する事項や、その借金について時効を援用する旨などを記載し、内容証明郵便で債権者に送付します。内容証明郵便とすることで、書面の内容や、債権者が書面を受け取った時期が公的に証明されるため、確かな証拠を残すことが可能です。 -
(2)裁判を起こされたときは答弁書で時効を援用する
消滅時効が完成したにもかかわらず、債権者が裁判を起こしてくることもあります。その場合には、時効を援用する旨を答弁書に記載し、裁判所に提出すれば足ります。
消滅時効が完成しているからといって裁判を放置すると、債権者の言い分どおりに判決が言い渡され、時効が更新されてしまうことに注意が必要です。 -
(3)時効の援用を弁護士に依頼するメリット
時効援用通知書を正しく作成できなければ、債権者へ送付しても時効援用の効果は生じません。それだけでなく、通知書を受け取った担当者から電話がかかってきて、言葉巧みに債務を承認させられてしまう恐れもあります。
時効の援用をするなら、弁護士への依頼が有効です。依頼後は弁護士が債権者とのやりとりを代行するため、債務承認のリスクを防止できます。法的に正しい内容の時効援用通知書を弁護士が作成し、内容証明郵便で送付するので、スムーズに時効援用の手続きが完結します。時効期間が経過しているか、時効が更新されていないかについても、事前に弁護士が的確に判断するので、時効援用に失敗するリスクが抑えられるというメリットもあります。
4、借金が時効になっても援用をしないとどうなる?
時効の援用をしなくても、消滅時効完成後は債権者が請求してこなくなることも、もちろんあります。しかし、時効の援用をしなければ以下のデメリットが生じるため、放置することは得策ではありません。
-
(1)いつ請求されてもおかしくない
すでにご説明したように、消滅時効の完成後も返済を請求してくる債権者は少なくありません。請求を受けてしまうと、裁判や債務の承認によって時効が更新され、時効援用権を失ってしまうリスクがあります。突然、債権者からの請求書面が自宅に届けば、借金していたことを家族に知られてしまうことにもなりかねません。
時効の援用をしない限り、このようなリスクがいつまでも残ります。そのため、時効を援用して、借金の返済義務を完全に消滅させることが重要です。時効の援用を正しく行った債務者に請求してくる債権者は、まずいません。 -
(2)財産を差し押さえられることがある
消滅時効の完成後でも、債権者から起こされた裁判を放置して支払い義務が確定すると、そのときから10年は消滅時効を援用できなくなります。一方、債権者は強制執行を申し立てることが可能となります。突然、給料や預金などの財産を差し押さえられてしまうことがあるのです。
時効の援用をしなかったばかりに差し押さえを受けて後悔しても、もはや遅いといわざるを得ません。 -
(3)信用情報機関の事故情報がいつまでも消えない
時効の援用をしなければ借金を延滞した状態のままとなるので、信用情報機関には延滞の事故情報がいつまでも残る可能性があります。
一方、時効の援用を正しく行えば借金が消滅するため、やがて事故情報は削除されます。削除されるまでの期間は信用情報機関によって異なりますが、遅くとも時効の援用をしてから5年後には事故情報が消えて、ローンやクレジットカードなどの利用が可能となります。
5、まとめ
消滅時効が完成しただけでは、まだ借金の返済義務は消滅していません。債権者からの請求を完全に止めるためには、時効の援用が必要です。ただし、時効を援用する際には、正確な知識がなければ「請求」や「承認」によって時効が更新されてしまい、失敗に終わる恐れがあります。そのため、時効の援用手続きは弁護士に任せることをおすすめします。
ベリーベスト法律事務所にご相談いただければ、時効の援用が可能かどうかを経験豊富な弁護士が的確に判断いたします。ご依頼いただければ、迅速に時効援用の手続き代行いたします。
借金の消滅時効が気になる方は、当事務所の無料相談をお気軽にご利用ください。

- 萩原達也 代表弁護士
- 弁護士会: 第一東京弁護士会
- 登録番号: 29985
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
債務整理、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金請求など、借金問題についてのお悩み解決を弁護士がサポートいたします。債務整理のご相談は何度でも無料です。ぜひお気軽に お問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています


同じカテゴリのコラム(その他)
-
更新: 2025年06月26日
- その他
- 異動情報

異動情報とは|いつ消えるか、CICの記録から消す方法を弁護士が解説
借金の支払いが遅れたり、債務整理が行われたりすると、個人信用情報機関に「異動情報」が登録されます。
異動情報が登録されると、ローンを借りられなくなったり、クレジットカードが使えなくなったり、さまざまなデメリットが生じることに注意が必要です。そのため、債務整理を行う前に、異動情報に関する注意点を理解しておきましょう。
本記事では、債務整理などによって登録される異動情報について、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。コラム全文はこちら -
更新: 2025年06月18日
- その他
- 第三者弁済

第三者弁済とは? 弁済が有効となる要件や影響、代位について解説
お金を借りた債務者本人に代わって、第三者が借金などの債務を返済するケースがあります。このような第三者弁済が行われるケースは少なくありませんが、あらゆる場合に第三者弁済が有効となるわけではありません。
また、第三者が弁済する場合であっても、民法上の「第三者弁済」には該当しないことがあります。第三者弁済に当たるケースとその他のケースの違いについて、知っておいたほうがよいでしょう。
なお、第三者弁済が有効に行われると債権者は満足しますが、弁済した第三者と債務者との間には債権・債務関係が残ることに注意が必要です。
本コラムでは、第三者弁済とは何か、第三者弁済が有効となるための要件、さらには弁済した第三者による「代位」について、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。コラム全文はこちら -
更新: 2025年06月13日
- その他
- 借金減額
- 仕組み

借金減額の仕組みとは? 罠やデメリット、正しい方法も解説
「借金減額」という広告を目にすると「怪しい」と感じるかもしれませんが、法律に従った方法で借金を減額できる仕組みもあります。借金減額の方法にはいくつかの種類があり、それぞれ仕組みが異なります。
減額効果が高い方法ほど大きなデメリットが生じる可能性もあるため、方法の選択を誤ると「罠だった」と感じてしまうこともあるかもしれません。
本コラムでは、借金減額がどのような仕組みで可能となるのか、悪徳業者の罠ではないのか、どのようなデメリットがあるのか、正しい借金減額の方法とは何か、などについて解説します。コラム全文はこちら
カテゴリを選ぶ
- トップページ
- 債務整理 弁護士コラム
- その他
- 時効の援用とは? 借金の消滅時効を主張するために必要な手続き