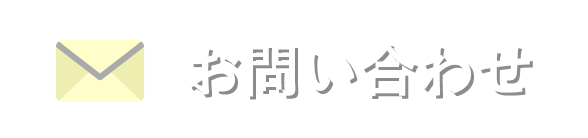- トップページ
- 債務整理 弁護士コラム
- 自己破産
- 自己破産すると持ち家はどうなる? 持ち家を残す方法も解説
債務整理 弁護士コラム
自己破産すると持ち家はどうなる? 持ち家を残す方法も解説
- 自己破産
- 自己破産
- 持ち家

自己破産をすると、借金の返済義務がすべて免除されることと引き換えに、一定の評価額を超える財産は処分されてしまいます。そのため、持ち家がある人は自己破産で家がどうなってしまうのかが気になることでしょう。
住み慣れた持ち家には思い入れもあり、手放したくないと考えるのも自然なことです。その反面で、多額の借金を整理するためには何らかのデメリットを受けることも避けられません。
この記事では、自己破産すると持ち家はどうなるのか、持ち家を残して借金を整理するにはどうすればよいのかについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、自己破産すると持ち家を失う?
自己破産手続きにおいて、破産者名義の持ち家は以下のように取り扱われます。
-
(1)原則として失ってしまう
破産者名義の財産は原則として債権者への配当の引き当てとなるため、換金処分されてしまいます。
ただし、以下のような財産は「自由財産」として手元に残すことが認められています。- 99万円以下の財産
- その他の財産で評価額20万円以下のもの
- 差押禁止財産
持ち家については、評価額20万円以下であることはまずありませんし、差押禁止財産にも該当しません。原則として、自己破産すると持ち家は失うことになります。
-
(2)持ち家が共有名義の場合も失うことが多い
持ち家が共有名義となっている場合、理論上は破産者名義の持ち分のみを失い、共有者名義の持ち分は残せるはずです。
しかし、実際には共有者名義の持ち分も含めて全体を失うことがほとんどです。
たとえば、持ち家が夫婦の共有名義となっていて夫が自己破産した場合、夫の持ち分のみを売却すれば、第三者と妻との共有名義となります。
このままでは住居として使用できず買い手がつかないので、妻の持ち分も含めて全体を売却し、妻は持ち分に応じた売却代金を取得するという処理を行うことが一般的となっています。 -
(3)例外的に失わないケース
自己破産すると、破産者の財産は自由財産を除いて破産管財人が管理・処分することになります。
ただし、買い手がつかない場合や、管理・処分に高額の費用を要して破産財団が減少してしまうような場合には、破産管財人がその財産を破産財団から放棄することがあります。
破産財団とは、簡単にいえば債権者への配当の引き当てとなる財産のことです。
破産財団から放棄された財産は破産管財人の手から離れ、処分されることはなくなるので、結果として破産者の手元に残ります。
持ち家が破産財団から放棄された場合には、例外的に持ち家を失わずにすむことになります。
しかし、持ち家は個人の買い手がつかなかったとしても不動産業者が買い取るケースがほとんどです。
破産財団から放棄されるのは、山奥など辺鄙な立地にある古い家屋など極めて稀なケースに限られます。
2、自己破産で持ち家が処分される手続きの流れ
自己破産手続きにおいて持ち家が処分されるまでの流れは、以下のとおりです。
-
(1)競売にかけられる場合
破産法上、破産者名義の不動産の処分は強制執行手続きによることが原則とされています(同法第184条1項)。
具体的には、破産管財人の申し立てによって持ち家が競売にかけられることになります。
競売の手続きは順調に進んでも6か月以上の期間を要し、その間は持ち家に住み続けることが可能です。
ただし、買受人が代金を納付した後は強制的に退去を求められることがあるので、早めに次の住居を確保して立ち退く必要があります。 -
(2)任意売却される場合
破産管財人は、裁判所の許可を得て破産者の持ち家を任意売却することもできます(破産法第78条2項1号、184条1項)。
ここにいう任意売却とは、破産管財人が競売にかけるのではなく、通常の方法で持ち家を売りに出して買い受け希望者を見つけ、売却することを指します。
一般的に競売よりも任意売却の方が高額で、かつ早期に売却できるため、任意売却の方法がとられるのがほとんどのケースです。
任意売却では競売の場合よりも早期に持ち家から立ち退く必要があることが多いですが、場合によっては買受人から引っ越し代を出してもらうことも可能というメリットもあります。 -
(3)住宅ローンが残っている場合
持ち家の住宅ローンが残っている場合、通常は住宅ローン債権者(金融機関)の抵当権が付いています。
住宅ローン債権者は、破産手続き外で抵当権を実行し、持ち家を競売にかけることが可能です。
しかし、住宅ローン債権者にとっても競売よりは任意売却の方が有利となります。
破産管財人が住宅ローン債権者の承諾と裁判所の許可を得て、任意売却により処理しているのがほとんどのケースです。
売却した結果、オーバーローンであれば残ったローンは破産債権として処理されます。
アンダーローンであれば、売却代金の中から99万円以内の現金を自由財産として取得することが可能です。
3、持ち家があるときに自己破産をするときの注意点
「持ち家を残したい」という気持ちがあるとしても、以下の行為をすると自己破産手続きに失敗する恐れがあるので注意が必要です。
-
(1)名義変更してはいけない
自己破産手続きにおいて債権者への配当の引き当てとなるのは、破産手続開始決定時に破産者名義であった財産に限られます。たとえ家族でも他人名義の財産は処分されません。
しかし、自己破産申し立て前に持ち家の名義を変更していると「財産隠し」とみなされる可能性があります。
財産隠しに該当すると、免責が許可されない可能性が高い(破産法第252条1項1号)だけでなく、悪質なケースでは「詐欺破産罪」(同法第265条1項1号)に問われる恐れもあるでしょう。
自己破産の申し立ての際には、過去2年以内に名義変更した財産があれば申告するように求められています。
申し立て前2年以内に持ち家の名義変更をしていると、財産隠しを疑われる恐れがあることに注意が必要です。 -
(2)勝手に売却してはいけない
自己破産申し立て前に、持ち家を不当な低価格で売却した場合も、名義変更の場合と同様のリスクが生じます(免責不許可について破産法第252条1項1号、詐欺破産罪について同法第265条1項4号)。
ただ、持ち家を適正な価格で売却することまで禁止されているわけではありません。
とはいえ、売却代金を浪費したり、売却代金の中から一部の債権者に優先的に返済したりすると、不当に破産財団を減少させたものとみなされることがあります。
その場合は、自己破産手続きにおいて「不当に減少させた金額」を別途積み立てるなどして調達し、債権者への配当に充てなければなりません。
自己破産申し立て前に持ち家を任意売却する場合は弁護士に依頼し、弁護士のアドバイスに従って行う方が無難です。
4、持ち家を残しつつ借金を整理する方法
債務整理をしても持ち家を残すためには、以下の方法があります。
-
(1)自己破産をして親族等に持ち家を買い取ってもらう
破産財団を構成する財産は、破産者の親族等が買い取ることも可能です。持ち家を親族等に買い取ってもらえば、その後も買受人の承諾を得て住み続けることができます。
あくまでも適正価格で買い取ってもらう必要がありますが、破産管財人が一般の市場に売りに出す場合より多少は低価格でも裁判所の許可が得られる可能性もあります。 -
(2)住宅ローンが残っている場合は個人再生をする
個人再生には「住宅ローン特則」という制度があります。
住宅ローンを返済中の持ち家があり、一定の要件を満たす場合には、住宅ローン特則付き個人再生を申し立てることで、持ち家を残しつつ他の借金を整理することが可能です。
ただし、アンダーローンの場合は持ち家の評価額と住宅ローン残高との差額が資産とみなされます。
個人再生による返済額が高額となる可能性があることに、注意しなければなりません。 -
(3)任意整理をする
任意整理では自己破産とは異なり、財産を処分する必要はありません。
借金額が大きい場合でも、親族等の協力が得られる場合は任意整理での解決を検討してみるとよいでしょう。
任意整理は、基本的に将来利息をカットしてもらい、残元金を3~5年で分割返済する手続きです。
自己破産をした場合に持ち家を親族等に一括払いで買い取ってもらうことが難しくても、任意整理をして分割返済を親族等に手伝ってもらうことができれば、持ち家を残せる可能性があります。
5、まとめ
自己破産をすると原則として持ち家を失ってしまいますが、親族等の協力が得られる場合や、他の債務整理も視野に入れるならば、持ち家を残せる可能性も十分にあります。
そのためには、自己破産を含む債務整理に関する正確な知識が要求されますので、弁護士に相談して検討しましょう。
ベリーベスト法律事務所では、債務整理事案の経験豊富な弁護士が皆さまのお悩みやご要望を承り、最善の解決方法を提案いたします。
持ち家を残しつつ借金問題を解決したいとお考えの方は、ぜひ気軽に無料相談をご利用ください。

- 萩原達也 代表弁護士
- 弁護士会: 第一東京弁護士会
- 登録番号: 29985
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
債務整理、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金請求など、借金問題についてのお悩み解決を弁護士がサポートいたします。債務整理のご相談は何度でも無料です。ぜひお気軽に お問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています


同じカテゴリのコラム(自己破産)
-
更新: 2025年12月25日
- 自己破産
- 自己破産
- 官報

自己破産すると官報に名前が出る? 家族にバレる可能性や掲載時期
多額の借金を抱えても、一定の条件を満たす場合は、自己破産によってすべての借金の支払い義務を免れることができます。ただし、自己破産をすると「官報」に氏名や住所が掲載され、全国に公表されてしまいます。
官報に掲載されることが不安で、自己破産するか迷っている方もいるかもしれません。しかし、会社や家族、知人などに見られる可能性は低く、過剰に心配する必要はないでしょう。
本コラムでは、自己破産して官報に掲載されるとどうなるか、掲載時期や掲載される内容、官報に載らずに債務整理する方法などについて、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。コラム全文はこちら -
公開: 2025年12月16日
- 自己破産
- 残クレ
- 破産

残クレで破産したら車は没収? 手放さずに済む? 借金を整理する方法
「残クレの支払いがもう限界……」そのような状況に追い込まれていませんか。
残価設定型クレジット(残クレ)は、月々の負担が軽く見える一方で、契約満了時に高額な残価精算や乗り換え判断を迫られます。生活に欠かせない車なのに、支払いができず自己破産まで考える人も少なくありません。
自己破産になれば、原則として車を手放さなければなりません。しかし、借金の負担を減らす「債務整理」には、任意整理や個人再生など、ほかにも種類があります。状況に応じた最適な手段を選択することで、車を手元に残したまま借金問題を解決できる可能性があるのです。
今回は、残クレ契約中に自己破産すると車がどうなるのか、手放さずに済む方法はあるのか、自己破産以外の借金整理の選択肢などを、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。コラム全文はこちら -
更新: 2025年12月03日
- 自己破産
- 自己破産
- 退職金

自己破産は退職金も処分対象? バレずに手続きを進めるコツを解説
借金問題の解決手段として自己破産を選択すれば、裁判所から免責許可を得られた場合に限り、原則としてすべての借金返済義務が帳消しになります。
ただし、自己破産の強力な借金減額効果を享受するには、自己破産特有の「財産処分」に注意しなければなりません。特に会社員の方が自己破産をする場合は、退職金という大きな財産の扱いが問題になります。
本コラムでは、自己破産をしたときの退職金の取り扱いについて、差し押さえにならないかどうかなど、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。自己破産手続きは、財産処分以外にも注意すべき点が少なくありません。想定外のデメリットを被る事態を避けるためにも、事前に弁護士までご相談ください。コラム全文はこちら
カテゴリを選ぶ
- トップページ
- 債務整理 弁護士コラム
- 自己破産
- 自己破産すると持ち家はどうなる? 持ち家を残す方法も解説