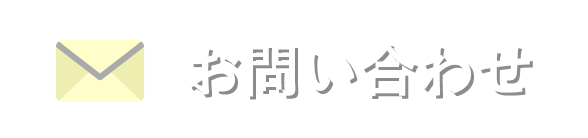- トップページ
- 債務整理 弁護士コラム
- 自己破産
- 自己破産できる借金額はいくらから? 目安と他の解決方法も解説
債務整理 弁護士コラム
自己破産できる借金額はいくらから? 目安と他の解決方法も解説
- 自己破産
- 自己破産
- いくらから

自己破産は、到底返済できないほどの借金を抱えたときに裁判所に申し立てることで、一定の条件のもとにすべての借金の返済義務を免除してもらえる債務整理の方法です。
ただ、自己破産をしたくても自分の借金額では少なすぎて認められないのではないか、と不安を感じている人もいらっしゃるでしょう。
この記事では、どれくらいの借金があれば自己破産ができるのかを解説し、借金が少ないために自己破産ができないときの解決方法についてもご紹介します。
1、自己破産できる条件
自己破産ができるのは、破産法に定められている、以下の3つの条件を満たす場合です。
-
(1)支払不能
第一の条件は、支払不能の状態に陥っていることです(破産法第1条)。
ただ、支払能力は人によって異なります。数十万円の借金でも返済が厳しいという人もいれば、1000万円を超える借金でも順調に返済していける人もいます。
支払不能に当たるかどうかは、借金額だけでなく、本人の収入や生活状況などを総合的に考慮して裁判所が客観的に判断します。
借金額が同じでも、人によって支払不能と認められるケースもあれば、認められないケースもあることに注意が必要です。 -
(2)免責不許可事由がないこと
第二の条件は、免責不許可事由がないことです。
正確にいうと、免責不許可事由があっても自己破産はできますが、免責が認められず借金がそのまま残ってしまうため、自己破産を申し立てる実益がないということになります。
免責不許可事由とは、破産法第252条1項に掲げられている、11個の事由のことを指します。- 浪費やギャンブルで借金を作ったケース(同項4号に該当)
- 特定の債権者にのみ優先的に返済するケース(同項3号に該当)
- 借金で購入した商品を現金化するケース(同項2号に該当)
などが比較的多く見受けられます。
ただし、免責不許可事由があっても事情によっては、裁判所の裁量で免責が許可されることもあります(同条2項)。このことを「裁量免責」といいます。
免責不許可事由に該当する事情があったとしても、自己破産の申し立てを検討する余地はあります。 -
(3)非免責債権でないこと
第三の条件は、抱えている債務が非免責債権でないことです。非免責債権は自己破産をしても支払義務が免除されないからです。
非免責債権とは、破産法第253条1項に掲げられた、7つの債権のことを指します。たとえば、税金の滞納(同項1号に該当)は自己破産をしても解消されず、自力で支払うなどして解決しなければなりません。
ただし、多少の非免責債権があっても、他に多額の借金を抱えている場合には自己破産をするメリットがあります。
借金を免責してもらうことによって、非免責債権も支払いやすくなるはずです。それに対して、もっぱら非免責債権のみを抱えている場合には、自己破産はできません。
2、自己破産で認められる「支払不能」とは?
借金がいくらあれば自己破産できるのかは、どのような場合に「支払不能」と認められるかにかかっています。支払不能と認められるのは、以下の3つの条件を満たす場合です(破産法第2条11号)。
-
(1)支払能力が欠けること
「支払能力が欠ける」とは、簡単にいうと借金の支払いをするだけの経済的な余裕がないことを指します。
経済的余裕があるかどうかについて、第一次的には収入が重要な判断要素となりますが、その他にも財産や信用、労力なども含めて総合的に考慮して判断されます。
これらのリソースをすべて活用しても支払いが間に合わない場合に、初めて「支払能力が欠ける」と認められるのです。
たとえば、収入がなくても高価な財産を所有しており、その財産を換金して支払に回すことが可能と認められる場合には「支払能力あり」と判断されます。
また、無収入とはいえ働いて収入を得ることが容易であるにもかかわらず、正当な理由なく働こうとしない場合にも「支払能力あり」と判断される可能性があります。 -
(2)弁済期にある債務を、弁済できないこと
どのような債務を支払えない場合に支払不能と認められるかというと、弁済期にある債務を弁済できない場合に限られます。
このままでは将来に弁済期が到来する債務を支払えなくなるような状態であっても、すでに弁済期が来ている債務を支払うことが可能であれば、支払不能には該当しないことになります。
したがって、たとえば「○年後に子どもの学費を支払わなければならないから、現在の借金は支払えない」という言い訳は認められません。 -
(3)一般的かつ継続的に、弁済できない状態であること
支払不能と認められるためには、債務を弁済できない状態が「一般的」かつ「継続的」なものであることも必要です。
一般的に弁済できない状態というのは、抱えている債務について全体的に遅滞なく支払っていくことができない状態を指します。
複数社からの借金を抱えている場合、小口の債権者に対しては全額を支払うことができても、そのために他の大口債権者への支払いができなくなる場合には、一般的に弁済できない状態に該当します。
継続的に弁済できない状態というのは、突発的な事情などで一時的に支払えなくなっただけでは足りず、今後ずっと支払いが見込めない状態のことを指します。
病気や失業で収入が途絶えたことがきっかけで自己破産を申し立てる場合、すぐ仕事に復帰するか、新たな仕事について収入の回復が見込まれる場合は、継続的に弁済できない状態には当たりません。
仕事に就けず収入が回復しない状態が長期間続く場合には、継続的に弁済できない状態に該当する可能性が出てきます。
3、自己破産できる借金額はいくらから?
具体的に借金額がいくら以上であれば支払不能と認められ、自己破産ができるのかについて、おおよその目安をご説明します。
-
(1)明確な基準はない
自己破産が可能となる借金額について、明確な基準はありません。
最低いくら以上でなければ自己破産はできないという決まりはありませんし、月収○○万円の人なら借金額○○万円以上が必要、といった基準もないのです。
あくまでも、個別の事案ごとに裁判所が具体的な事情を考慮して、支払不能かどうかを判断します。 -
(2)5年で返済できるかがひとつの目安
ひとつの目安として、抱えている借金総額を5年の分割払いで完済できるかどうか、という基準が挙げられます。
なぜなら、個人再生でも分割返済期間が最長5年とされていることと、5年かかっても返済しきれない借金を抱えていれば、やがて破綻する可能性が高いと一般的に考えられるからです。
たとえば、毎月の給料から生活費を除いて5万円を返済に充てられるとした場合、300万円(5万円×60か月)を超える借金があれば、自己破産が認められる可能性が高くなります。
一方で、生活保護受給者の場合は、保護費を借金の返済に充てることは認められないため、わずかな借金額でも自己破産が認められる可能性が十分にあります。 -
(3)100~300万円が平均的
日本弁護士連合会が2020年に実施した調査によると、自己破産した人が抱えていた負債額は500万円未満のケースが半数以上を占めており、その中でも特に多かったのは「200万円以上300万円未満」(14.52%)、「100万円以上200万円未満」(13.87%)となっています。
(参考:「2020年破産事件及び個人再生事件記録調査」(日本弁護士連合会))
自己破産が認められるかどうかは、あくまでも個別の事案ごとに判断されますが、このデータはひとつの参考資料となるでしょう。
4、借金額が少なく自己破産できないときの対処法
借金額が少なくて自己破産が認められない場合で、自力で返済できない場合は、他の債務整理を検討することになります。
-
(1)任意整理
任意整理は、債権者と直接交渉して将来利息をカットしてもらい、残った借金を3~5年で分割返済する債務整理の方法です。
毎月の返済額を減らすことが可能なので、ある程度の収入がある場合には任意整理を検討するとよいでしょう。 -
(2)個人再生
個人再生は、裁判所の手続きを利用して借金を5分の1~10分の1にまで減額し、残った借金を3年~5年で分割返済する債務整理の方法です。
安定収入は必要ですが、毎月の返済額が大幅に減るので、任意整理で支払えない場合でも個人再生なら支払える可能性があります。
借金総額が100万円以下の場合は減額されませんが(民事再生法第231条2項4号)、それでも一定の条件を満たせば強制的に将来利息のカットと分割払いが認められるというメリットがあります。
5、まとめ
自己破産できる借金額は、家計の収支状況や本人の財産、信用、労力によって異なります。
本記事では一応の目安をご紹介しましたが、具体的に確認したい場合は弁護士への相談をおすすめします。
経験豊富な弁護士であれば、自己破産できない場合でも他の解決方法に関するアドバイスが可能です。
ベリーベスト法律事務所では、自己破産をはじめとする債務整理に関するご相談を何度でも無料で承っております。お困りの際は、お気軽に無料相談をご利用ください。

- 萩原達也 代表弁護士
- 弁護士会: 第一東京弁護士会
- 登録番号: 29985
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
債務整理、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金請求など、借金問題についてのお悩み解決を弁護士がサポートいたします。債務整理のご相談は何度でも無料です。ぜひお気軽に お問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています


同じカテゴリのコラム(自己破産)
-
更新: 2025年12月25日
- 自己破産
- 自己破産
- 官報

自己破産すると官報に名前が出る? 家族にバレる可能性や掲載時期
多額の借金を抱えても、一定の条件を満たす場合は、自己破産によってすべての借金の支払い義務を免れることができます。ただし、自己破産をすると「官報」に氏名や住所が掲載され、全国に公表されてしまいます。
官報に掲載されることが不安で、自己破産するか迷っている方もいるかもしれません。しかし、会社や家族、知人などに見られる可能性は低く、過剰に心配する必要はないでしょう。
本コラムでは、自己破産して官報に掲載されるとどうなるか、掲載時期や掲載される内容、官報に載らずに債務整理する方法などについて、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。コラム全文はこちら -
公開: 2025年12月16日
- 自己破産
- 残クレ
- 破産

残クレで破産したら車は没収? 手放さずに済む? 借金を整理する方法
「残クレの支払いがもう限界……」そのような状況に追い込まれていませんか。
残価設定型クレジット(残クレ)は、月々の負担が軽く見える一方で、契約満了時に高額な残価精算や乗り換え判断を迫られます。生活に欠かせない車なのに、支払いができず自己破産まで考える人も少なくありません。
自己破産になれば、原則として車を手放さなければなりません。しかし、借金の負担を減らす「債務整理」には、任意整理や個人再生など、ほかにも種類があります。状況に応じた最適な手段を選択することで、車を手元に残したまま借金問題を解決できる可能性があるのです。
今回は、残クレ契約中に自己破産すると車がどうなるのか、手放さずに済む方法はあるのか、自己破産以外の借金整理の選択肢などを、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。コラム全文はこちら -
更新: 2025年12月03日
- 自己破産
- 自己破産
- 退職金

自己破産は退職金も処分対象? バレずに手続きを進めるコツを解説
借金問題の解決手段として自己破産を選択すれば、裁判所から免責許可を得られた場合に限り、原則としてすべての借金返済義務が帳消しになります。
ただし、自己破産の強力な借金減額効果を享受するには、自己破産特有の「財産処分」に注意しなければなりません。特に会社員の方が自己破産をする場合は、退職金という大きな財産の扱いが問題になります。
本コラムでは、自己破産をしたときの退職金の取り扱いについて、差し押さえにならないかどうかなど、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。自己破産手続きは、財産処分以外にも注意すべき点が少なくありません。想定外のデメリットを被る事態を避けるためにも、事前に弁護士までご相談ください。コラム全文はこちら
カテゴリを選ぶ
- トップページ
- 債務整理 弁護士コラム
- 自己破産
- 自己破産できる借金額はいくらから? 目安と他の解決方法も解説