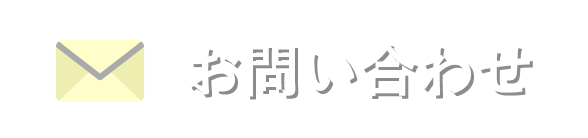- トップページ
- 債務整理 弁護士コラム
- 自己破産
- 自己破産手続きの流れと注意点を弁護士がわかりやすく解説
債務整理 弁護士コラム
自己破産手続きの流れと注意点を弁護士がわかりやすく解説
- 自己破産
- 自己破産
- 流れ

自己破産は、裁判所に申し立てて「支払不能」であることを認めてもらい、一定の条件を満たせば「免責」が許され、すべての借金の返済義務が免除される債務整理の方法です。
仕組みそのものは単純ですが、ある程度の財産を所有している場合や借り入れの経緯に問題がある場合など、事案の内容によっては複雑な手続きを要することもあります。誰しも自己破産を申し立てる前には不安を感じるものですが、どのようなことが行われるのかを知っておけば、安心して手続きを進められるようになるはずです。
この記事では、自己破産手続きの流れと注意点をわかりやすく、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、自己破産には3種類の手続きがある
自己破産には以下の3種類の手続きがあり、事案の内容に応じて振り分けられます。
-
(1)同時廃止事件
同時廃止事件は、債権者への配当に充てるだけの財産がなく、免責について詳しく調査する必要もない場合にとられる手続きです。
破産手続開始決定と同時に破産手続廃止決定が下されて免責手続きに移り、ほとんどの場合はそのまま免責が許可されます。
3種類の手続きの中で最も手間がかからず、早期に終了する手続きとなっています。 -
(2)少額管財事件
「管財事件」とは、破産管財人が選任される破産事件のことです。
99万円を超える現金や、その他の財産で評価額20万円を超えるものがある場合には、換金して債権者に配当する必要があるため、破産管財人が選任されます。この、破産管財人が行う手続きを「管財手続き」といいます。
少額管財事件とは、管財事件のうち、次の「通常管財事件」よりも管財手続きが簡略化された形で進められる破産事件のことです。
財産の換金にさほどの手間がかからないケースや債権者数が比較的少ないケース、財産がなくても借り入れの経緯に問題があるなどの理由で、免責について破産管財人による調査が必要なケースが少額管財事件に付されます。
少額管財事件は裁判所の運用によって実施されている制度であり、すべての裁判所で取り扱っているわけではないことに注意が必要です。 -
(3)通常管財事件
通常管財事件とは、破産法の規定どおりの本格的な管財手続きが行われる破産事件のことです。
3種類の手続きの中で最も複雑な手続きであり、事案の内容によっては長期化することもあります。
2、自己破産手続きの流れ【同時廃止事件の場合】
自己破産手続きの流れについて、まずは同時廃止事件の場合をご説明します。裁判所によって流れが異なる部分もありますが、本記事では東京地方裁判所の例で解説していきます。
-
(1)申し立ての準備
自己破産手続きは自分で行うこともできますが、専門的な知識を要するため弁護士に依頼して行うことが一般的です。
まずは弁護士に相談し、自己破産を申し立てることを決めたら弁護士と委任契約を結びます。その後、弁護士が発送する受任通知が債権者に届くと督促がいったん止まります。
それから、弁護士と打ち合わせをして申し立ての準備を始めます。
申立書は弁護士が作成しますが、その他にも住民票や通帳のコピー、給与明細、家計表などさまざまな添付書類が必要です。
弁護士から書類の提供を指示されたら、速やかに収集して事務所に届けることが重要です。 -
(2)裁判所への申し立て
必要書類がそろったら、裁判所の担当窓口に提出することによって自己破産を申し立てます。申立先は、債務者の住所地を管轄する地方裁判所です。
-
(3)裁判官との面接
申し立てが受理されると、裁判官との面接が行われ、申立書の内容について確認されます。
基本的には依頼した弁護士が裁判官と面接しますが、事案の内容によっては債務者本人も同席を求められ、借り入れの経緯や財産状況などについて詳しく尋ねられることもあります。
この段階で、同時廃止事件・少額管財事件・通常管財事件のいずれに付すべきかを裁判官が判断します。 -
(4)破産手続開始決定
裁判官との面接終了後、裁判所から「破産手続開始決定」が発出されます。同時廃止事件の場合は、併せて「破産手続廃止決定」も発出されるのです。
この2つの決定が1枚の書面で同時に行われるため「同時廃止決定」と呼ばれています。 -
(5)免責審尋
同時廃止事件では管財事件が行われないため、免責手続きに移ります。
免責手続きでは債務者本人が裁判官と面接する「免責審尋」が開かれ、免責不許可事由がないかについて確認されます。免責審尋には弁護士も同席します。
なお、申し立て後の裁判官との面接に債務者本人も同席した場合は、その際に免責に関する確認も行われるので、同時廃止決定後の免責審尋は省略されるのが一般的です。 -
(6)免責許可決定
裁判所は、同時廃止決定と併せて、債権者が免責に関する意見を述べることができる期間(免責意見申述期間)を定めて官報で公告します。
債権者から特段の意見申述がなく、免責不許可事由がない場合は、免責許可決定が行われます。
債権者から免責に反対するような意見が申述された場合は、破産者側の反論などを踏まえて裁判所が免責の許否を判断されるのが一般的です。
同時廃止事件の場合、裁判所に申し立ててから免責許可決定が出るまでの期間は平均して3~4か月程度です。
免責許可決定も官報で公告され、掲載日から2週間が経過すると免責許可決定が確定します。この時点で借金の支払い義務がすべて免除されます。
3、自己破産手続きの流れ【管財事件の場合】
少額管財事件と通常管財事件では、基本的な手続きの流れは同じです。破産手続き開始決定までの流れは同時廃止事件の場合と同じなので、以下ではその後の手続きの流れを解説していきます。
-
(1)破産手続開始決定後、破産管財人との面談
管財事件では、破産手続開始決定と併せて、破産手続きの経験が豊富な地元の弁護士の中から破産管財人が選任されます。
管財手続きは、破産管財人との面談から始まります。借り入れの経緯や財産状況などについて詳しく尋ねられますが、正直に事実を伝えることが重要です。
面談には依頼した弁護士も同席しますので、破産管財人からの質問に答えにくい場合にはフォローを受けることが可能です。 -
(2)財産の処分・債権者への配当
破産管財人は、破産者の財産を管理し、換価処分した金銭を債権者へ配当する手続きを進めていきます。
通常管財事件では厳格な手続きに従って配当が行われますが、少額管財事件では「簡易配当」や「同意配当」といった簡略化された手続きによって速やかに配当が行われるのが一般的です。
管財手続き中、破産者宛ての郵便物はすべて破産管財人宛てに転送されます。
破産管財人が郵便物の内容を確認することにより、破産者の債権・債務や財産状況を調査するためです。破産管財人がチェックした後の郵便物は、破産者に返却されます。 -
(3)債権者集会
管財手続き中は、破産管財人による管財業務の進捗状況などを報告するため定期的に「債権者集会」が開かれます。
少額管財事件の場合は1回の債権者集会で終了することが多いですが、通常管財事件では財産の換価・配当などに時間を要するため、数回の期日を重ねることが少なくありません。
配当が行われた場合は、その後の債権者集会をもって破産手続きは終了します。
配当できるほどの財産がなかった場合には、最終の債権者集会で「異時廃止決定」が行われ、破産手続き終了となります。 -
(4)免責許可決定
管財事件では、破産管財人が免責に関する調査も併せて行っているため、最終の債権者集会で免責の許否も判断されます。
免責許可決定が出た場合は、同時廃止事件の場合と同様に官報公告を経て確定します。
裁判所への申し立てから免責許可決定が出るまでの期間は事案の内容によりますが、少額管財事件で4~6か月程度、通常管財事件で6~12か月程度が平均的です。
4、手続きの中で注意すべきこと
自己破産手続きをスムーズに進めるためには、以下の点に注意しておく必要があります。
-
(1)自己破産によって生じるデメリット
自己破産をすると、一定の評価額を超える財産を処分されるだけでなく、以下のようなデメリットも生じます。
- 手続き中は一部の資格や職業に制限を受ける
- 手続き中に引っ越しや旅行をするには裁判所の許可を要する
- 官報に氏名や住所が掲載される
仕事や生活に支障をきたさないためには、事前にこれらのデメリットを確認した上で手続きを進めていくことが重要です。
-
(2)自己破産手続き中にしてはいけないこと
以下の行為をすると、自己破産手続きが失敗に終わる可能性が高くなります。
- 財産隠しをする
- 財産を勝手に処分する
- 特定の債権者にのみ優先的に返済する
- 弁護士に依頼した後に新たな借り入れをする
- クレジットカードを現金化する
自己破産手続きに失敗しないためには、経験豊富な弁護士に依頼し、弁護士の指示やアドバイスを守って手続きを進めていく必要があるでしょう。
5、まとめ
自己破産手続きは複雑ですが、弁護士に依頼すれば全面的なサポートが行えます。ただし、すべての弁護士が自己破産手続きに慣れているわけではないので、弁護士選びを誤ると手続きで手間取る可能性もあるでしょう。
ベリーベスト法律事務所では、自己破産事件の経験豊富な弁護士がご相談から裁判所への申し立て、免責許可決定を獲得するまで全面的にサポートすることが可能です。自己破産の申し立てをお考えの際は、ぜひ気軽に無料相談をご利用ください。

- 萩原達也 代表弁護士
- 弁護士会: 第一東京弁護士会
- 登録番号: 29985
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
債務整理、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金請求など、借金問題についてのお悩み解決を弁護士がサポートいたします。債務整理のご相談は何度でも無料です。ぜひお気軽に お問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています


同じカテゴリのコラム(自己破産)
-
更新: 2025年12月25日
- 自己破産
- 自己破産
- 官報

自己破産すると官報に名前が出る? 家族にバレる可能性や掲載時期
多額の借金を抱えても、一定の条件を満たす場合は、自己破産によってすべての借金の支払い義務を免れることができます。ただし、自己破産をすると「官報」に氏名や住所が掲載され、全国に公表されてしまいます。
官報に掲載されることが不安で、自己破産するか迷っている方もいるかもしれません。しかし、会社や家族、知人などに見られる可能性は低く、過剰に心配する必要はないでしょう。
本コラムでは、自己破産して官報に掲載されるとどうなるか、掲載時期や掲載される内容、官報に載らずに債務整理する方法などについて、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。コラム全文はこちら -
公開: 2025年12月16日
- 自己破産
- 残クレ
- 破産

残クレで破産したら車は没収? 手放さずに済む? 借金を整理する方法
「残クレの支払いがもう限界……」そのような状況に追い込まれていませんか。
残価設定型クレジット(残クレ)は、月々の負担が軽く見える一方で、契約満了時に高額な残価精算や乗り換え判断を迫られます。生活に欠かせない車なのに、支払いができず自己破産まで考える人も少なくありません。
自己破産になれば、原則として車を手放さなければなりません。しかし、借金の負担を減らす「債務整理」には、任意整理や個人再生など、ほかにも種類があります。状況に応じた最適な手段を選択することで、車を手元に残したまま借金問題を解決できる可能性があるのです。
今回は、残クレ契約中に自己破産すると車がどうなるのか、手放さずに済む方法はあるのか、自己破産以外の借金整理の選択肢などを、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。コラム全文はこちら -
更新: 2025年12月03日
- 自己破産
- 自己破産
- 退職金

自己破産は退職金も処分対象? バレずに手続きを進めるコツを解説
借金問題の解決手段として自己破産を選択すれば、裁判所から免責許可を得られた場合に限り、原則としてすべての借金返済義務が帳消しになります。
ただし、自己破産の強力な借金減額効果を享受するには、自己破産特有の「財産処分」に注意しなければなりません。特に会社員の方が自己破産をする場合は、退職金という大きな財産の扱いが問題になります。
本コラムでは、自己破産をしたときの退職金の取り扱いについて、差し押さえにならないかどうかなど、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。自己破産手続きは、財産処分以外にも注意すべき点が少なくありません。想定外のデメリットを被る事態を避けるためにも、事前に弁護士までご相談ください。コラム全文はこちら
カテゴリを選ぶ
- トップページ
- 債務整理 弁護士コラム
- 自己破産
- 自己破産手続きの流れと注意点を弁護士がわかりやすく解説