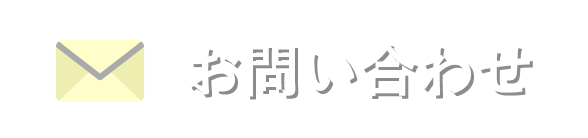- トップページ
- 債務整理 弁護士コラム
- 自己破産
- 個人事業主が自己破産しても事業継続する方法とは? 弁護士が解説
債務整理 弁護士コラム
個人事業主が自己破産しても事業継続する方法とは? 弁護士が解説
- 自己破産
- 個人事業主
- 自己破産
- 事業継続

自営業者などの個人事業主が多額の負債を抱えた場合、自己破産後をしても事業を今までどおりに継続できるのかについて、不安を抱えている方が多いことでしょう。
自己破産を申し立て、免責が許可されると負債はすべて免除されますが、その前提として一定の評価額を超える財産があれば処分しなければなりません。そのため、自己破産の手続きによって事業の基盤を失ってしまう可能性が大いにあります。
本コラムでは、個人事業主が自己破産後も可能な限り事業を継続するための方法を解説します。
1、個人事業主の自己破産後の事業継続は法律上可能?
結論からいえば、個人事業主が自己破産後も事業を継続できる可能性はあります。
法人の場合は、破産手続きの開始決定をもって事業は廃止されます(会社法第471条5号等)。
その後、破産管財人が裁判所の許可を得て破産者の事業を継続することは可能です(破産法第36条)。しかし、これは破産法人の売掛金の回収や事業譲渡など破産手続きを進めるために必要な事業活動を行うものに過ぎません。破産手続きが終了すると、法人は消滅します(破産法第35条)。
一方、個人は破産手続きが終了しても存在し続けます。破産した個人も仕事をすることが破産法で禁止されるわけではないので、可能性としては破産前から営んでいた事業を継続できることもあるのです。
とはいえ、破産法のさまざまな規定により、個人事業主がそのまま事業を続けることは難しいケースが多いのが実情です。
2、個人事業主の自己破産後の事業継続が難しくなる理由
個人事業主が、自己破産後に事業を継続することが難しくなる理由は、以下のとおりです。
-
(1)事業用の設備や在庫が処分されることが多い
自己破産をすると、破産者の財産は基本的にすべて「破産財団」となります(破産法第34条1項)。
破産財団とは、簡単にいうと破産手続きの開始決定時に申立人が所有していた財産のことで、当然ながら破産者名義の事業用財産も含まれます。
破産財団に属する財産は破産管財人のみが管理・処分する権限を有することとなり(同法第78条1項)、破産者が自由に使用できなくなります。
一定の評価額を超える財産は破産管財人によって処分され、債権者への配当などに充てられます。
事業用の設備や在庫など、事業の継続に欠かせない重要な財産は一定の評価額を超えることが多いので、破産手続きによって多くの事業用財産を失ってしまう可能性が高いのです。 -
(2)事業に関する契約が解除される
個人事業主が自己破産をすると、事業所の賃貸借契約や従業員と雇用契約、事業用機械や設備のリース契約などは強制的に解除されてしまいます。
賃貸借契約については、民法上は賃借人が自己破産をしても強制的に解除されるわけではありません。
事業用物件については敷金や保証金が破産財団となるため、破産管財人によって解除されることが一般的です。 -
(3)事業資金の融資を受けられなくなる
自己破産をすると信用情報機関に事故情報が登録され、その後は10年程度、銀行や貸金業者から新規の融資を受けることが難しくなります。
つまり、事業資金の調達が困難になるということです。 -
(4)取引先を失う可能性が高い
仕入れ先などに対する買掛金は自己破産による免責の対象となり、免責が許可されると支払う必要がなくなります。そうなると仕入れ先からの信用を失い、取引が停止される可能性が高いでしょう。
自己破産をしたことによって、顧客などの販売先からの信用を失う可能性も高いといえます。
個人事業主が自己破産すると以上のデメリットが生じるため、事業を継続することは難しい場合が多いのです。
3、個人事業主が自己破産後も事業継続できる条件
個人事業主が、自己破産しても事業を継続するためには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
-
(1)自由財産のみで事業運営が可能であること
破産手続きの開始決定時に申立人が所有している財産はすべて破産財団となるのが原則ですが、申立人が個人の場合には一定の範囲内で自由財産が認められます。
自由財産として主なものを挙げると、以下のとおりです。- 生活に欠かせない衣服・寝具・家具・家電など
- その他、法律で差し押さえが禁止されている財産
- 99万円以下の現金
- その他の財産で評価額20万円以内のもの
これらの財産については、破産管財人に引き渡す必要もなく、破産者が継続して自由に使用できます。
したがって、大がかりな事業用財産が不要な小規模な事業であれば、自己破産後も継続できる可能性があります。 -
(2)融資を受けなくても事業運営が可能であること
仕入れが不要など、元手があまりかからない業種であれば、融資を受けなくても事業を運営できることもあるでしょう。
腕一本で仕事をこなす職人やフリーランスなどであれば、融資を受けられなくなっても事業を継続できる可能性が高いといえます。
ある程度の元手が必要な業種でも、親族や知人などからの支援により事業資金を調達できる場合には、事業の継続が可能です。 -
(3)継続的で安定した収益が見込まれること
自己破産で負債をすべて処理できたとしても、生活を維持していくための収入は自己責任で確保する必要があります。
そのために事業を継続するのであれば、その事業によって、継続的で安定した収益が見込まれることが条件となります。
収益の予測については希望的観測ではなく、現実的な観点から厳しめに行うことが重要です。
特に、業績不振が原因で負債を抱えたケースであれば、収益を向上させるための具体的な手だてを検討することも必要となるでしょう。
4、事業を継続しながら借金問題を解決する方法
多額の負債を抱えつつも事業を継続したいという方は、以下の方法によって、その目的を実現できる可能性があります。
-
(1)自己破産をしても事業用財産を残す工夫をする
自己破産をしても、法律で差し押さえが禁止されている財産は自由財産として手元に残すことができます。
そして、業務に欠かせない器具などの財産は、差し押さえ禁止財産とされています(民事執行法第131条4号~6号)。
自己破産手続きにおいて、「業務に欠かせない財産」に当たると主張して、少しでも多くの事業用財産を残すことが考えられます。
ただし、ここにいう「業務」は自己の労力によるものに限られるため、「経営のために必要な財産」については含まれないものが多くあります。
差し押さえ禁止財産に該当しないものであっても、裁判所に「自由財産の拡張」を認めてもらえれば、手元に残すことが可能です(破産法第34条4項)。
破産者が生活を維持するために今の事業を継続する必要性が高く、そのために不可欠な財産であると認められれば、評価額にもよりますが、自由財産の拡張が認められる可能性があります。
また、親族や知人に事業用財産を破産管財人から買い取ってもらい、それを借りて使用することも可能です。
さほど高額でない事業用財産であれば、評価額に相当する金額を自由財産の中から破産財団に組み入れることにより、その財産を破産財団から放棄してもらうことも考えられるでしょう。
破産財団から放棄された財産は自由財産となるので、今までどおりに使用できます。 -
(2)自己破産後に別の形で事業を始める
自己破産後、今までどおりに事業を継続することが難しい場合は、別の形で事業を始めることも検討してみるとよいでしょう。
たとえば、個人で工務店を経営していた場合、工務店を廃業することになってもフリー(個人事業主)の大工として働くことが考えられます。
地道に仕事をこなして顧客からの信用を高めていけば、再び自力で工務店を開くことも可能となってくるでしょう。
自己破産後、約10年が経過すれば、再び事業資金の融資を受けることもできるようになります。 -
(3)自己破産以外の方法で借金問題を解決する
借金問題の解決方法は自己破産だけではありません。自己破産では事業を継続できない場合でも、任意整理や個人再生を選択すれば事業を継続できる可能性があります。
任意整理は、債権者と直接交渉することにより将来利息を免除してもらい、返済期間や月々の返済額を見直す手続きです。
基本的に、元金は全額返済する必要があるため大幅な減額は期待できません。
負債総額が比較的少なく、毎月の返済額を減らせば返済していけるだけの収益が得られる場合には、任意整理が適しています。
個人再生は、裁判所の手続きをすることにより借金総額を5分の1~10分の1にまで減額することが可能な手続きです。
ただし、「清算価値保障の原則」により、所有財産の総額以上の金額を返済する必要があります。
高額の事業用財産を所有している場合には、個人再生をしても返済額が思うように減らない可能性があることに注意が必要です。
任意整理・個人再生・自己破産はそれぞれ特徴が異なる手続きなので、状況に応じて、借金問題を解決すると同時に事業も継続できる可能性が最も高い手続きを選ぶことが重要となります。
5、まとめ
自己破産で可能な限り多くの事業用財産を残したり、最適な債務整理手続きを選んだりするためには、専門的な知識も要求されます。そのため、自己判断で進めるよりは、弁護士に相談することをおすすめします。
ベリーベスト法律事務所でも個人事業主の借金問題に関するご相談を承っております。
経験豊富な弁護士が、最適な解決方法を提案いたします。借金問題に関するご相談は何度でも無料でご利用できますので、お困りの際は、お気軽に無料相談をご利用ください。

- 萩原達也 代表弁護士
- 弁護士会: 第一東京弁護士会
- 登録番号: 29985
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
債務整理、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金請求など、借金問題についてのお悩み解決を弁護士がサポートいたします。債務整理のご相談は何度でも無料です。ぜひお気軽に お問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています


同じカテゴリのコラム(自己破産)
-
更新: 2025年12月25日
- 自己破産
- 自己破産
- 官報

自己破産すると官報に名前が出る? 家族にバレる可能性や掲載時期
多額の借金を抱えても、一定の条件を満たす場合は、自己破産によってすべての借金の支払い義務を免れることができます。ただし、自己破産をすると「官報」に氏名や住所が掲載され、全国に公表されてしまいます。
官報に掲載されることが不安で、自己破産するか迷っている方もいるかもしれません。しかし、会社や家族、知人などに見られる可能性は低く、過剰に心配する必要はないでしょう。
本コラムでは、自己破産して官報に掲載されるとどうなるか、掲載時期や掲載される内容、官報に載らずに債務整理する方法などについて、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。コラム全文はこちら -
公開: 2025年12月16日
- 自己破産
- 残クレ
- 破産

残クレで破産したら車は没収? 手放さずに済む? 借金を整理する方法
「残クレの支払いがもう限界……」そのような状況に追い込まれていませんか。
残価設定型クレジット(残クレ)は、月々の負担が軽く見える一方で、契約満了時に高額な残価精算や乗り換え判断を迫られます。生活に欠かせない車なのに、支払いができず自己破産まで考える人も少なくありません。
自己破産になれば、原則として車を手放さなければなりません。しかし、借金の負担を減らす「債務整理」には、任意整理や個人再生など、ほかにも種類があります。状況に応じた最適な手段を選択することで、車を手元に残したまま借金問題を解決できる可能性があるのです。
今回は、残クレ契約中に自己破産すると車がどうなるのか、手放さずに済む方法はあるのか、自己破産以外の借金整理の選択肢などを、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。コラム全文はこちら -
更新: 2025年12月03日
- 自己破産
- 自己破産
- 退職金

自己破産は退職金も処分対象? バレずに手続きを進めるコツを解説
借金問題の解決手段として自己破産を選択すれば、裁判所から免責許可を得られた場合に限り、原則としてすべての借金返済義務が帳消しになります。
ただし、自己破産の強力な借金減額効果を享受するには、自己破産特有の「財産処分」に注意しなければなりません。特に会社員の方が自己破産をする場合は、退職金という大きな財産の扱いが問題になります。
本コラムでは、自己破産をしたときの退職金の取り扱いについて、差し押さえにならないかどうかなど、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。自己破産手続きは、財産処分以外にも注意すべき点が少なくありません。想定外のデメリットを被る事態を避けるためにも、事前に弁護士までご相談ください。コラム全文はこちら
カテゴリを選ぶ
- トップページ
- 債務整理 弁護士コラム
- 自己破産
- 個人事業主が自己破産しても事業継続する方法とは? 弁護士が解説