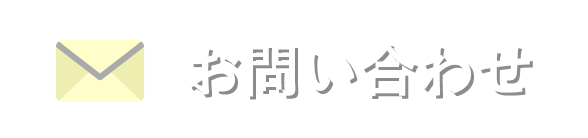- トップページ
- 債務整理 弁護士コラム
- 自己破産
- 自己破産するときの必要書類とは? 書類が集まらないときの対処法も解説
債務整理 弁護士コラム
自己破産するときの必要書類とは? 書類が集まらないときの対処法も解説
- 自己破産
- 自己破産
- 必要書類

自己破産は、裁判所に申し立てをして、借金の返済義務をすべて免除してもらえる手続きです。
申し立ての際には、借入状況や経緯の他にも、収入や資産状況なども裁判所に申告しなければなりません。そのため、自己破産をするには、数多くの必要書類をそろえる必要があります。
本コラムでは、自己破産を申し立てるために必要な書類の種類と集め方について、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。ご自身で必要書類をそろえることが難しいときの対処法も紹介するので、ぜひご参考ください。
1、自己破産の全ケースでの必要書類11種
自己破産をするには、どのようなケースでも必要になる書類があります。1章では、自己破産申し立てで必須の必要書類11種をご紹介します。
-
(1)申立書
申立書とは、破産手続開始および免責許可の決定を求める旨を記載する書面です。
申立人の氏名・住所などの個人情報や、借入件数、借入額などを書き込めば完成する書式が裁判所で用意されています。
裁判所のホームページでダウンロードできますが、裁判所によって書式が異なることもあるため、申立て先の裁判所の担当窓口で入手することがおすすめです。 -
(2)債権者一覧表
債権者一覧表とは、債権者の氏名・住所や借入の時期、現在の債務額、借金の使い途などを一覧表にまとめて記載する書面です。裁判所で入手することができ、書式にしたがって書き込みます。
-
(3)財産目録
財産目録とは、申立人の所有財産について、種類ごとに有無と内容、金額、評価額などを記載する書面です。財産目録も、裁判所で書式を入手して書き込みます。
-
(4)陳述書
申立人の経歴から家族構成、生活状況、借入の経緯、自己破産申し立てに至った事情などを記載する書面が陳述書です。裁判所で入手した書式に書き込みますが、別紙に借入の経緯や自己破産申し立てに至った事情について、さらに詳しく記載して添付するのが一般的となっています。
-
(5)家計の状況
申立人の家計の収支を一覧表にまとめて記載する書面も、自己破産時には必要です。直近1か月の収入と支出について、世帯単位で項目ごとに金額を記載します。書式は、書き込み式のものを裁判所で入手することが可能です。
-
(6)居住地がわかる書類
申立人が日本国籍であることと、居住地を証明するために住民票が必要です。本籍地の記載があり、同居家族全員の記載があり、マイナンバーの記載がないものを、お住まいの市区町村の役所で取得しましょう。
賃貸住宅に居住している場合は、賃貸借契約書のコピーも必要です。 -
(7)預貯金通帳のコピー
入出金の流れを証明するために、預貯金通帳のコピーが必要です。開設している口座のすべてについて最新の記帳をして、申し立て直近2年分のコピーを用意しましょう。
-
(8)収入を証明するもの
収入を証明する書類として、給与所得者なら、給与明細書(申し立て直近2か月分)と源泉徴収票(申し立ての前年分)を用意しましょう。自営業者なら、確定申告書の控え(申し立て直近3年分)と課税(非課税)証明書を用意してください。
収入がない場合は、課税(非課税)証明書だけで足ります。課税(非課税)証明書は、保険料控除等が記載されているものが必要です。 -
(9)資産を証明するもの
財産目録に計上した資産については、その裏付けとなる証明書も必要です。主な証明書として、次のようなものが挙げられます。
資産の種類 所有の証明書(入手先) 評価額の証明書(入手先) 不動産(持ち家など) 登記事項証明書(法務局) 査定書(不動産仲介業者など) 自動車 車検証(手持ちのもの) 査定書(中古車買取業者など) 退職金 - 退職金見込額証明書(勤務先の会社) 保険 保険者証(手持ちのもの) 解約返戻金見込額証明書(保険会社) 有価証券(株など) 証券(手持ちのもの) 残高証明書(証券会社)
不動産を所有していない場合は、住所地の市区町村の役所で無資産証明書を取得しなければなりません。
-
(10)現在の借金額がわかる書類のコピー
弁護士に依頼せず自分で自己破産を申し立てる場合には、現在の借金額がわかる書類も必要です。
債権者ごとに、直近に届いた請求書や督促状をコピーしておきましょう。借入先の金融機関のホームページで、借入残高を表示した画面をプリントアウトしたものでも構いません。 -
(11)封筒または宛名ラベル(通知用)
裁判所が債権者や申立人への通知に使用するための封筒または宛名ラベルも、準備する必要があります。封筒のサイズや必要枚数は裁判所によって異なることがあるので、申し立て予定の裁判所で確認しましょう。
切手は封筒に貼らず、別途、裁判所の窓口で申立時に提出します。
2、自己破産でケースによっては必要となる書類5種
自己破産の申立時の状況によっては、他にも書類が必要となることがあります。以下では、よくあるケースと、その場合の必要書類を紹介します。
-
(1)公的給付(年金や生活保護など)の受給者証
年金や生活保護を受給している場合は、収入の証明として受給者証と課税(非課税)証明書が必要です。
受給者証を紛失した場合は、年金事務所や市区町村の役所で再発行してもらいましょう。 -
(2)税金等の滞納状況がわかる書類
税金や社会保険料などの公租公課を滞納している場合は、その種類や滞納金額がわかる書類が必要です。税務署等から届いた督促状などのコピーを用意しましょう。
公租公課の滞納金は自己破産しても免責されませんが、財団債権または優先的破産債権となるため、滞納状況がわかる書類が求められます。 -
(3)投資(株やFXなど)に関する取引明細
株やFXなどの投資をしている場合は、申し立て直近1~2年分の取引明細書が必要です。証券会社から届いた書面または電子書面を用意しましょう。
高リスクの投資はギャンブルと同様に免責不許可事由(破産法第252条1項4号)に該当する可能性があるため、取引状況を証明しなければなりません。 -
(4)反省文
浪費やギャンブルなどの免責不許可事由がある場合は、反省文を提出することで、裁量免責(破産法第252条2項)が許可される可能性が高まります。
陳述書とは別の書面に、借金をしてまで浪費やギャンブルをしてしまった理由、反省の気持ち、自己破産以外では解決が難しい理由、現在の生活状況、今後の改善策などを詳しく記載することをおすすめします。 -
(5)その他、裁判所が指示するもの
自己破産にはさまざまなケースがあるため、場合によっては裁判所から他にも書類の提出を指示されることがあります。
裁判所の指示に従えば手続きを進められますが、事前に弁護士に相談して必要と考えられる書類を用意しておいた方が、スムーズに手続きを進めやすくなります。
3、自己破産で必要書類の準備が長引いたときのリスク
自己破産で必要書類の準備が長引くと、次のようなリスクが生じます。必要書類は効率よく集めて、速やかに申し立てることが重要です。
-
(1)自分で申し立てる場合は債権者からの督促が止まらない
自分で自己破産を申し立てる場合は、破産手続開始決定の書面が債権者に届くまで督促が止まりません。債権者に対応しながら必要書類を集めることは大変なので、自己破産の申し立ては弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼すると、受任通知が債権者に届いた時点で督促がいったん止まるので、落ち着いて必要書類の準備を進めることが可能です。 -
(2)書類の再取得を要することがある
必要書類の一部の作成・取得が遅れると、既に用意した書類の有効期間が切れたり、状況が変わったりして、再取得を要することがあります。
特に、住民票の再取得や通帳コピーの取り直し、給与明細書の補充などを要するケースが多いので、注意しましょう。 -
(3)裁判を起こされるおそれがある
自己破産の申し立てに至らないまま滞納が3~6か月ほど続くと、債権者から裁判を起こされる可能性が高まります。裁判を放置すると差し押さえを受けるおそれもあります。
弁護士に依頼した場合でも必要書類の準備が遅れると裁判を起こされることがあるので、弁護士の指示に応じて速やかに書類を集めましょう。
4、自己破産の必要書類が集まらないときの対処法
自己破産の必要書類を集めることが難しいときは、ひとりで悩まず裁判所または弁護士に相談しましょう。
-
(1)裁判所の窓口に相談する
自己破産申し立ての方法については、裁判所の担当窓口に相談すれば教えてもらうことができます。
ただし、裁判所は中立・公平な立場なので、自己破産手続きを有利に進めるためのアドバイスは得られないことに注意してください。また、申立書や必要書類の内容についての質問には、裁判所は回答してくれないことが一般的です。 -
(2)弁護士に相談する
弁護士に相談すれば、債務者の味方としての立場から、必要書類の集め方から自己破産手続きの進め方までアドバイスを受けることが可能です。
依頼後は、住民票や収入・資産に関する疎明資料など、どうしても債務者本人が用意しなければならない書類を除いて、弁護士が代行して申し立て準備を進めます。
また、自分で必要書類を集めようとして債権者への対応が遅れてしまうよりは、弁護士に相談しながら必要書類を収集した方が円滑に破産の申し立てができますので、迷った場合には、速やかに弁護士に相談しましょう。
5、まとめ
自己破産の必要書類は多岐にわたり、ケースによっては作成・取得が難しいものもあります。
破産の手続きで戸惑いがあるときは、弁護士に相談するとよいでしょう。弁護士に依頼をすれば、申し立ての準備にかかる負担を大幅に軽減できる上に、自己破産を有利に進められる可能性も高まります。
自己破産の申し立てをお考えの方は、早めにベリーベスト法律事務所へご相談ください。債務整理専門チームの経験豊富な弁護士が、それぞれのケースのご事情を十分に踏まえて丁寧に対応いたします。また、借金に関する相談は何度でも無料で受け付けておりますので、まずはお問い合わせください。

- 菅谷 良平 パートナー弁護士
- 弁護士会: 東京弁護士会
- 登録番号: 47122
債務整理部マネージャー弁護士として、債務整理・借金問題及びその周辺分野に精通しています。これまで、お客さまの生活再建に向けて、数多くの案件に対応してまいりました。債務整理のご相談は、何度でも無料です。任意整理、自己破産、個人再生など、借金問題についてお悩みの方は、ぜひお気軽に ご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています


同じカテゴリのコラム(自己破産)
-
更新: 2025年12月25日
- 自己破産
- 自己破産
- 官報

自己破産すると官報に名前が出る? 家族にバレる可能性や掲載時期
多額の借金を抱えても、一定の条件を満たす場合は、自己破産によってすべての借金の支払い義務を免れることができます。ただし、自己破産をすると「官報」に氏名や住所が掲載され、全国に公表されてしまいます。
官報に掲載されることが不安で、自己破産するか迷っている方もいるかもしれません。しかし、会社や家族、知人などに見られる可能性は低く、過剰に心配する必要はないでしょう。
本コラムでは、自己破産して官報に掲載されるとどうなるか、掲載時期や掲載される内容、官報に載らずに債務整理する方法などについて、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。コラム全文はこちら -
公開: 2025年12月16日
- 自己破産
- 残クレ
- 破産

残クレで破産したら車は没収? 手放さずに済む? 借金を整理する方法
「残クレの支払いがもう限界……」そのような状況に追い込まれていませんか。
残価設定型クレジット(残クレ)は、月々の負担が軽く見える一方で、契約満了時に高額な残価精算や乗り換え判断を迫られます。生活に欠かせない車なのに、支払いができず自己破産まで考える人も少なくありません。
自己破産になれば、原則として車を手放さなければなりません。しかし、借金の負担を減らす「債務整理」には、任意整理や個人再生など、ほかにも種類があります。状況に応じた最適な手段を選択することで、車を手元に残したまま借金問題を解決できる可能性があるのです。
今回は、残クレ契約中に自己破産すると車がどうなるのか、手放さずに済む方法はあるのか、自己破産以外の借金整理の選択肢などを、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。コラム全文はこちら -
更新: 2025年12月03日
- 自己破産
- 自己破産
- 退職金

自己破産は退職金も処分対象? バレずに手続きを進めるコツを解説
借金問題の解決手段として自己破産を選択すれば、裁判所から免責許可を得られた場合に限り、原則としてすべての借金返済義務が帳消しになります。
ただし、自己破産の強力な借金減額効果を享受するには、自己破産特有の「財産処分」に注意しなければなりません。特に会社員の方が自己破産をする場合は、退職金という大きな財産の扱いが問題になります。
本コラムでは、自己破産をしたときの退職金の取り扱いについて、差し押さえにならないかどうかなど、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。自己破産手続きは、財産処分以外にも注意すべき点が少なくありません。想定外のデメリットを被る事態を避けるためにも、事前に弁護士までご相談ください。コラム全文はこちら
カテゴリを選ぶ
- トップページ
- 債務整理 弁護士コラム
- 自己破産
- 自己破産するときの必要書類とは? 書類が集まらないときの対処法も解説