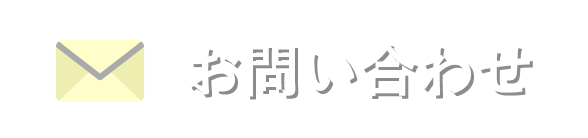- トップページ
- 債務整理 弁護士コラム
- 自己破産
- 自己破産したら相続できない? 自己破産が遺産相続に与える影響
債務整理 弁護士コラム
自己破産したら相続できない? 自己破産が遺産相続に与える影響
- 自己破産
- 自己破産
- 相続

自己破産を検討している人には、自己破産によって生じるデメリットを不安に感じている人も多いと思います。たしかに、さまざまな場面に影響を及ぼしてしまうことがないわけではありません。たとえば親の遺産相続の場面でも、自己破産が一定の影響を与えるケースがあります。
本記事では、自己破産が相続に影響を及ぼしてしまうケースや、それを回避するための対処方法について解説していきます。
1、自己破産すると親の財産を相続できなくなるのか?
自己破産すると一定の期間(手続き開始から免責確定まで)は就けなくなる仕事などがあることから、自己破産すると相続する権利なども失うという心配をしている人もいるかもしれません。しかし、自己破産をしたことで家族などの財産を相続する権利を失うことはありません。
-
(1)自己破産は相続の欠格事由に該当しない
相続欠格とは、法律が定める事情に該当した場合に相続する権利を失ってしまう制度です。具体的には、民法891条が以下の事情を相続欠格事由として定めています。
- 故意に被相続人または同順位以上の相続人を死亡、または死亡させようとした場合
- 被相続人が殺害されたのを知って告発や告訴を行わなかった場合
- 詐欺・脅迫によって被相続人の遺言を取り消し・変更を妨げた場合
- 詐欺や脅迫によって被相続人の遺言を取り消し・変更・妨害させた場合
- 被相続人の遺言書偽造・変造・破棄・隠蔽(いんぺい)した場合
相続欠格となるのは、この5つの事情に該当した場合のみに限られますので、相続人(となるはずの人)が自己破産をしたとしても、相続欠格となることはありません。
-
(2)自己破産を理由に相続を廃除できない
相続廃除とは、被相続人の意思によって特定の相続人を相続から除外する制度です。しかし、相続する権利は、相続人固有の権利という側面も持ち合わせているので、相続廃除は、必ずしも被相続人の意思だけで自由に決めることはできず、次のような事情がある場合のみ認められています。
- 被相続人を虐待した
- 被相続人に対して、極度の屈辱を与えた
- 被相続人の財産を不当に処分した
- ギャンブルなどを繰り返し、被相続人に多額の借金を支払わせた
- 浪費・犯罪を繰り返したり、反社会団体への加入するなどをして被相続人に多大な迷惑をかけた(度重なる重大な親不孝)
- 重大な犯罪を起こし、有罪判決を受けた
- 愛人と一緒に暮らすなどの不貞行為をする配偶者
- 財産目当ての婚姻関係がなされている
- 財産目当ての養子縁組がなされている
相続人が自己破産をしたということだけでは、相続廃除も認められません。しかし、自己破産の原因となった理由によっては、相続廃除となってしまう可能性があることは注意しておく必要があるでしょう。
2、相続財産は自己破産するとどうなるか? 破産手続きの基本ルールを確認
自己破産をした場合には、債務者(破産者)が所有する財産が強制的に売却されてしまう可能性があり、このことが相続にも悪影響を与えてしまうことがないわけではありません。
まずは自己破産した場合に強制処分される財産についての基本的なルールを確認しておきましょう。
-
(1)誰の財産が強制処分されるのか
自己破産した場合に強制売却(差し押さえ)の対象となるのは、破産者が所有する財産に限られます。たとえば、同居の家族などの財産であっても、破産者本人の財産ではありませんから、自己破産で差し押さえられることはありません。
-
(2)強制処分されるのはいつの時点の財産か
自己破産した場合に強制売却の対象となるのは、「破産手続き開始決定のとき」に破産者が所有していた財産に限られます。このことは、破産手続き開始決定よりも後に取得した財産は、強制売却の対象とはならないという点で大きな意味をもっています。
このような自己破産後に取得した財産のことを新得財産と呼んでいますが、典型的には自己破産後に得た給料などが該当します。 -
(3)強制処分されることのない財産
破産者が破産手続き開始決定のときに所有していた財産であっても、そのすべてが強制処分の対象となるわけではありません。破産者の今後の生活に欠かせない財産まで強制処分してしまうことは、破産者にとってあまりにも酷で債権者との関係でも公平とはいえないからです。
自己破産をしても強制売却されない財産の例としては、次のようなものが挙げられます。- 99万円までの現金
- 一般的な衣服や生活家具・家電
- 仕事維持のために必要な道具・器具など(職人道具や漁網・家畜など)
また、売却しても利益の生じない財産や、売却それ自体が難しい財産(山地やがけ地など)についても、強制売却の対象とならない場合が多いといえます。
3、自己破産するタイミングと相続との関係
上記のルールを前提に、自己破産が相続に与える実際の影響について確認していきましょう。
-
(1)自己破産を申し立てる前に相続手続きが完了する場合
自己破産の申し立て前に相続が発生した場合には、当然のことですが、通常の場合と同様に相続手続きが行われます。したがって、(相続人が複数にいる場合には)遺産分割協議を行い、その内容に基づいて相続人それぞれが財産を相続することになります。
ただし、上記で解説した基本ルールにしたがって、相続によって取得した財産は破産手続きにおける強制売却の対象となり得ることに注意しておく必要があるでしょう。 -
(2)自己破産の申し立て後、破産手続き開始決定前に相続が発生した場合
自己破産の申し立てから、破産手続き開始決定前までの間に相続が発生したケースでは特に対応に注意する必要があります。
この場合には、すでに自己破産の申し立てをしている以上は、破産手続きが開始される前であっても、破産手続きの開始を念頭において相続の手続きを進める必要があるからです。
したがって、このケースにおいては、相続財産も上記で解説した基本ルールにしたがって、強制売却の対象となってしまい一切取得できない可能性があります。
また、他の共同相続人と行う遺産分割協議も破産者である相続人ではなく、裁判所から選任された破産管財人が行いますので、他の相続人にも自己破産したことを知られてしまいます。 -
(3)自己破産開始後に相続が発生した場合
自己破産の手続きが開始された後に相続が発生した場合には、その相続には自己破産の影響は生じません。上記で解説したように、破産手続きにおいて強制売却の対象となるのは、「破産手続き開始のとき」に破産者が所有していた財産に限定されるからです。
したがって、このケースは、自己破産手続きによって財産を没収されることもなく、相続財産を取得できるという点でもっと有利なケースといえます。
4、自己破産による相続への影響は小さくできるか?
自己破産による相続への影響は、自己破産をする相続人だけでなく、他の共同相続人の相続内容にも大きな影響を与えてしまうことが少なくありません。
たとえば、相続財産が被相続人の自宅しかないというようなケースで3人の相続人のひとりが自己破産した場合には、自己破産した人の相続分(持分権)が破産手続きにおいて競売に掛けられてしまうこともあり、その自宅を手放すことになってしまう可能性もあります。
このようなケースで相続による影響を小さくする方法としては、相続放棄などによる対応が考えられます。
-
(1)相続放棄による対応
相続放棄とは、自らの意思で「相続人にならない」選択することをいいます。相続放棄をした場合には、その相続人は「はじめから相続人ではなかった」という取り扱いになるため、相続の手続き(遺産分与)からは完全に除外されます。
したがって、自己破産手続きが開始される前に相続が発生した場合には、相続放棄をすることで、その自己破産による相続への影響を排除することができます。前述の被相続人の自宅を数人で相続するケースであれば、自己破産する人が相続放棄をすることで、残りのふたりの相続人だけでその自宅を相続できるようになるというわけです。
しかし、この相続放棄による対応は、破産手続き開始決定が下される前になされる必要があることに注意する必要があります。なぜなら、破産手続き開始後の相続放棄は、「限定承認」の効果しかもたないと破産法で定められているからです(破産法238条1項)。
限定承認とは、その相続で得られた利益の範囲で債務を引き受けるという方法のことを指すので、破産手続き開始後に相続放棄をしたとしても、破産者の相続分を破産手続きから除外することはできなくなってしまうからです。
なお、相続放棄や限定承認は、相続が開始していないと行うことができません。相続それ自体は自己破産のタイミングにあわせて発生するものではありませんので、相続放棄によってうまく対応できるケースというのは、実際にはかなり限られるといえます。 -
(2)自己破産直前に遺産分割協議をする際の注意点
相続人が複数いる場合には、遺産分割の内容は、相続人全員による遺産分割協議によって決めなければなりません。相続人それぞれの相続分は、必ずしも法定相続分どおりでなければならないわけではないので、理屈としては、「特定の相続人の相続分をゼロとする」という内容の遺産分割協議をすることも可能です。
しかし、自己破産手続きを申し立てている相続人の相続分だけをゼロとするような内容の遺産分割協議は、後の自己破産手続きで問題となる可能性があることに注意しておかなければなりません。このような遺産分割協議は、詐害行為(債権者の権利を害する行為)に該当すると評価されてしまう可能性があるからです。
破産者が詐害行為をした場合には、破産管財人による否認権行使の対象となります。否認権が行使されれば、その遺産分割協議は法的な効力を失うことになりますので、結局、相続財産は、破産手続きによって強制売却されるということになります。
さらに、詐害行為が悪質であると判断された場合には、自己破産が失敗する(免責を認めてもらえない)原因にもなってしまいます。
5、まとめ
ここまで解説してきたように、自己破産中に相続が発生したときには相続に大きな影響を与えてしまう場合があります。相続財産が破産手続きの中で売却されてしまうために、自分の相続分が少なくなってしまうだけでなく、他の相続人の相続分にも重大な影響を与えてしまう可能性があります。
このような悪影響を回避する方法としては、できるだけ早い時期に自己破産で借金を清算してしまうという選択肢があります。自己破産で借金を解決してしまえば、家族から引き継ぐ遺産もしっかり守ることができるからです。

- 萩原達也 代表弁護士
- 弁護士会: 第一東京弁護士会
- 登録番号: 29985
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
債務整理、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金請求など、借金問題についてのお悩み解決を弁護士がサポートいたします。債務整理のご相談は何度でも無料です。ぜひお気軽に お問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています


同じカテゴリのコラム(自己破産)
-
更新: 2025年12月25日
- 自己破産
- 自己破産
- 官報

自己破産すると官報に名前が出る? 家族にバレる可能性や掲載時期
多額の借金を抱えても、一定の条件を満たす場合は、自己破産によってすべての借金の支払い義務を免れることができます。ただし、自己破産をすると「官報」に氏名や住所が掲載され、全国に公表されてしまいます。
官報に掲載されることが不安で、自己破産するか迷っている方もいるかもしれません。しかし、会社や家族、知人などに見られる可能性は低く、過剰に心配する必要はないでしょう。
本コラムでは、自己破産して官報に掲載されるとどうなるか、掲載時期や掲載される内容、官報に載らずに債務整理する方法などについて、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。コラム全文はこちら -
公開: 2025年12月16日
- 自己破産
- 残クレ
- 破産

残クレで破産したら車は没収? 手放さずに済む? 借金を整理する方法
「残クレの支払いがもう限界……」そのような状況に追い込まれていませんか。
残価設定型クレジット(残クレ)は、月々の負担が軽く見える一方で、契約満了時に高額な残価精算や乗り換え判断を迫られます。生活に欠かせない車なのに、支払いができず自己破産まで考える人も少なくありません。
自己破産になれば、原則として車を手放さなければなりません。しかし、借金の負担を減らす「債務整理」には、任意整理や個人再生など、ほかにも種類があります。状況に応じた最適な手段を選択することで、車を手元に残したまま借金問題を解決できる可能性があるのです。
今回は、残クレ契約中に自己破産すると車がどうなるのか、手放さずに済む方法はあるのか、自己破産以外の借金整理の選択肢などを、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。コラム全文はこちら -
更新: 2025年12月03日
- 自己破産
- 自己破産
- 退職金

自己破産は退職金も処分対象? バレずに手続きを進めるコツを解説
借金問題の解決手段として自己破産を選択すれば、裁判所から免責許可を得られた場合に限り、原則としてすべての借金返済義務が帳消しになります。
ただし、自己破産の強力な借金減額効果を享受するには、自己破産特有の「財産処分」に注意しなければなりません。特に会社員の方が自己破産をする場合は、退職金という大きな財産の扱いが問題になります。
本コラムでは、自己破産をしたときの退職金の取り扱いについて、差し押さえにならないかどうかなど、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。自己破産手続きは、財産処分以外にも注意すべき点が少なくありません。想定外のデメリットを被る事態を避けるためにも、事前に弁護士までご相談ください。コラム全文はこちら
カテゴリを選ぶ
- トップページ
- 債務整理 弁護士コラム
- 自己破産
- 自己破産したら相続できない? 自己破産が遺産相続に与える影響