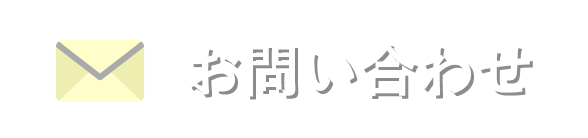- トップページ
- 債務整理 弁護士コラム
- 自己破産
- 自己破産は退職金も処分対象? バレずに手続きを進めるコツを解説
債務整理 弁護士コラム
自己破産は退職金も処分対象? バレずに手続きを進めるコツを解説
- 自己破産
- 自己破産
- 退職金

借金問題の解決手段として自己破産を選択すれば、裁判所から免責許可を得られた場合に限り、原則としてすべての借金返済義務が帳消しになります。
ただし、自己破産の強力な借金減額効果を享受するには、自己破産特有の「財産処分」に注意しなければなりません。特に会社員の方が自己破産をする場合は、退職金という大きな財産の扱いが問題になります。
本コラムでは、自己破産をしたときの退職金の取り扱いについて、差し押さえにならないかどうかなど、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。自己破産手続きは、財産処分以外にも注意すべき点が少なくありません。想定外のデメリットを被る事態を避けるためにも、事前に弁護士までご相談ください。
1、差し押さえもありえる? 自己破産したときの退職金の扱い
まずは、自己破産手続きにおける退職金の一般ルールについて、ケースごとに解説します。
退職金の取り扱いは、債務者(破産者)がどのタイミングで自己破産手続きを申し立てるかによって異なります。
そもそも会社に退職金制度が存在しない場合、退職金が財産処分の対象になる心配をする必要はありませんが、「退職金制度が存在しないこと」を裁判所に証明しなければいけない点につき、ご留意ください。
-
(1)退職金受け取り済みの人が自己破産する場合
すでに会社を辞めて退職金を受け取っている人が自己破産をする場合、退職金をどのように保管しているかによって取り扱いが異なります。
まず、「預貯金」として口座に保管している場合には、「口座残高20万円を超える金額」が差し押さえされ、債券の回収に充てる全額換価処分の対象です。
次に、「現金」として保管しているなら、「99万円を超える金額」がすべて換価処分されます。
つまり、退職金を受け取り済みの状態で自己破産をした場合、「退職金の一般ルール」が適用されることはありません。預貯金や現金のなかに流入した一般財産として、幅広い範囲の「元退職金」が債権者に振り分けられて、手元に残すことができないということです。
高額の退職金を受け取ってしまっている場合には、自己破産によって相当損をする可能性が高いので、事前に以下のような問題を弁護士に相談しましょう。- 本当に自己破産すべきなのか
- 自己破産以外の債務整理手続きを選択したほうがメリットは大きいのではないか
-
(2)退職したが退職金を受け取る前の人が自己破産する場合
退職後、まだ退職金を受け取っていないが、以下のような状況では、自己破産手続き上、退職金は給与と同じ扱いを受けます。
- 今後退職金を受け取ることが決まっている場合
- 近く退職することが決まっていて、退職金が入ってくる見込みがある場合
今後退職金を受け取ることが決まっている場合や、近く退職することが決まっていて退職金が入ってくる見込みがある場合には、自己破産手続き上、退職金は給与と同じ扱いを受けます。
つまり、退職金見込額の1/4相当額が換価処分の対象になるということです。
この場合、退職金としてまとまった金額が入っていない状態であるにもかかわらず、退職金見込額の1/4に相当する現金を裁判所に差し出さなければいけないため、自己破産手続きの難易度が高くなります。 -
(3)在職中の人が自己破産する場合
退職の予定がない人が自己破産をする場合には、退職金見込額の1/8相当額が換価処分の対象です。
なお、退職金見込額とは、破産手続き開始決定の時点で退職した場合の退職金額を意味します。
たとえば、会社の在籍年数が浅い段階なら、自己破産をしたところで退職金予定額は大した金額ではありません。その一方で、在籍年数が相当長期に及んでいる段階なら、換価処分の対象になる退職金見込額を考慮すると、自己破産のハードルが高くなるでしょう。
なお、自己破産をして退職金見込額が差し押さえになるとしても、会社を辞める必要はありません。
2、自己破産で退職金が換価処分対象になるか不安なときに確認すべきこと
退職金が原因で自己破産をためらっている方は、以下の要素に該当するか否かをご確認ください。場合によっては、退職金が換価処分の対象外になる可能性があります。
-
(1)換価処分対象額が20万円以上か
まず、自己破産の換価処分の対象になる財産は、20万円超の部分に限られます。つまり、退職金が20万円以内に収まる場合には、手元に残せるということです。
たとえば、以下の状況では退職金を全額手元に残せるでしょう。- 在職中に自己破産する場合:退職金見込額の1/8が20万円(退職金見込額が160万円)以内
- 退職予定者が自己破産する場合:退職金見込額の1/4が20万円(退職金見込額が80万円)以内
- すでに退職した人が自己破産する場合:退職金額が20万円以内に収まる金額
-
(2)退職金が差し押さえ・換価処分の対象外か
企業の退職金のなかには、その性質上、そもそも換価処分の対象外になるものがあります。
- 中小企業退職金共済
- 小規模企業共済
- 社会福祉施設職員等退職手当共済
- 確定給付企業年金
- 厚生年金基金
- 企業型確定拠出年金
- 個人型確定拠出年金
これらの退職金は差し押さえが禁止されており、自己破産でも換価処分の対象外と扱われるため、手元にそのまま残すことが許されます。
-
(3)自由財産の拡張が認められるか
自己破産の財産処分には、「自由財産の拡張」という例外措置が認められています。
自由財産の拡張とは、破産者の申し立てや裁判所の判断によって、破産者が所有し続けることが許される財産の範囲を広げる制度のことです。
たとえば、預貯金額が20万円を超える場合や、所持している現金が99万円を超える場合でも、破産者の生活維持のために必要だと認められる個別事情が存在するときには、換価処分を免れることができます。
なお、実際の自己破産実務では、総額99万円が自由財産拡張の限度と判断されることが多くあります。
3、会社にバレずに自己破産をする方法
ここまで解説したように、給与所得者が自己破産をするときには必ず退職金の取り扱いが議題に上がるため、原則として「退職金見込額証明書」を用意する必要があります。
退職金見込額証明書は、会社側に発行を依頼しなければ入手できません。しかし、自己破産を検討している方の多くが、「会社に知られずに自己破産をしたい」と考えているはずです。
ここからは、会社にバレずに退職金見込額証明書を入手する方法や、会社に知られずに退職金問題を克服するコツを解説します。
-
(1)退職見込額証明書の発行理由を工夫する
退職金見込額証明書は、勤務先の経理課や総務課に発行依頼をするのが一般的です。
発行依頼を出すときには退職金見込額証明書の使用用途の説明を求められますが、正直に「自己破産手続きのため」と伝える必要はありません。
たとえば、以下の理由を代用するだけで、自己破産のことを知られずに退職見込額証明書を発行してもらえるでしょう。- マイホーム購入資金の住宅ローン審査
- 子どものための教育ローン審査
- 奨学金の保証人・連帯保証人審査
- 退職金の運転資金
-
(2)退職見込額証明書の代わりの書類を用意する
退職金見込額証明書をどうしても用意できないときには、退職金見込額を証明できる別の証拠を用意するのも選択肢のひとつです。
たとえば、就業規則や退職金規定が定められている場合には、これらの規定を元に退職金見込額を算定し、裁判所に対する説明にできるでしょう。
4、退職金がネックで自己破産できないときの対策方法
退職金が換価処分の対象になることが原因で自己破産に踏み出せないときには、家計収支を見直すこと、個人再生や任意整理といった対処法をご検討ください。
なお、債務者がひとりでどの解決策が適切かを判断するのは、ハイリスクです。実際に対処を検討する際は、弁護士に相談しましょう。
-
(1)家計収支を見直す
状況次第ですが、債務整理を利用せずに家計収支を見直すだけで自力完済を目指せる場合があります。債務整理を頼らずに自力完済を実現できれば、債務整理によって生じる数々のデメリットを回避することが可能です。
家計収支を見直す具体的な方法として、以下のものが挙げられます。- 副業や資格手当などによって収入アップを目指す
- スマホ代や公共料金のプラン変更、家賃の見直しなどによって固定費を節約する
- 不要な生命保険を解約する
- 自宅にある不用品や効果ブランド品を売却する
- 多重債務状態にあるなら、「おまとめローン」などを活用して低金利商品に一本化する
-
(2)個人再生
自己破産を選択するのが難しい場合には、個人再生を検討するのも選択肢のひとつです。
個人再生とは、裁判所から認可を受けた場合に限り、借金元本自体を減額して返済負担を軽減する債務整理手続きのことです。自己破産のように財産が処分されることはないので、退職金が取り上げられる心配をする必要はありません。
個人再生のメリット・デメリットは以下のとおりです。【個人再生のメリット】
- 借金元本に踏み込んだ減額効果を期待できる
- 借金の理由を問われない
- 職業制限や資格制限がない
- 住宅ローン特則によりマイホームを手放さずに済む
【個人再生のデメリット】
- 借金総額が100万円以下だと一切減額されない
- 連帯保証人に迷惑がかかる
- 原則3年間の返済計画が作られるので、毎月の返済額が増えるリスクがある
- 無職など、継続的な返済可能性がない場合には、裁判所から認可してもらえない
- 裁判所の手続きが複雑
- 官報に掲載される
- ブラックリストに登録される
自己破産とてんびんにかけて、どちらが適切か弁護士からアドバイスを受けるのがおすすめです。
-
(3)任意整理
退職金が原因で自己破産に抵抗があるときには、任意整理も検討しましょう。
任意整理とは、債権者・債務者間の直接交渉によって返済条件を見直す債務整理手続きのことです。交渉次第ですが、将来利息や遅延損害金をカットしたうえで、元本のみの原則3年~5年の分割払い計画で和解契約が締結されることが多いです。
任意整理のメリット・デメリットは、以下のとおりです。債務整理のなかではもっともデメリットが小さいので、比較的利用しやすいでしょう。【任意整理のメリット】
- 将来利息や遅延損害金がカットされるので、借金返済総額を大幅に軽減できる
- 任意整理の対象にする借金を自由に選択できる
- 裁判所を利用せずに、柔軟かつスピーディーに交渉手続きを進めやすい
- 比較的家族に隠しやすい
- 自宅や自動車などを手元に残せる
【任意整理のデメリット】
- 債権者が交渉に応じてくれないと、手続きを進行できない
- 任意整理交渉に成功した後も、3年~5年は借金返済生活が継続する
- 返済計画次第では、毎月の返済額が増えるリスクがある
- ブラックリストに登録される
- 連帯保証人付きの債務を任意整理すると、連帯保証人に迷惑がかかる
5、まとめ
自己破産を利用すると、借金返済義務の帳消しという大きなメリットを得られる代償として、退職金などが差し押さえられ、財産処分されるデメリットを避けられません。
ただし、退職のタイミングや退職金の金額次第では、自己破産をしても退職金が無傷で済むこともあります。「退職金があるから自己破産はやめるべきだ」と即断するべきではないでしょう。
他方で、債務者の状況次第では、自己破産によって相当額の退職金が取り上げられて手続き後の生活再建が立ち行かなくなるリスクが生じる場合もあります。
「自己破産をしたほうがいいかわからない」「自分の場合は退職金がどうなるか知りたい」など、お困りの際は、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。債務整理専門チームの知見・経験豊富な弁護士が、親身になって対応いたします。

- 萩原達也 代表弁護士
- 弁護士会: 第一東京弁護士会
- 登録番号: 29985
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
債務整理、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金請求など、借金問題についてのお悩み解決を弁護士がサポートいたします。債務整理のご相談は何度でも無料です。ぜひお気軽に お問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています


同じカテゴリのコラム(自己破産)
-
更新: 2025年12月25日
- 自己破産
- 自己破産
- 官報

自己破産すると官報に名前が出る? 家族にバレる可能性や掲載時期
多額の借金を抱えても、一定の条件を満たす場合は、自己破産によってすべての借金の支払い義務を免れることができます。ただし、自己破産をすると「官報」に氏名や住所が掲載され、全国に公表されてしまいます。
官報に掲載されることが不安で、自己破産するか迷っている方もいるかもしれません。しかし、会社や家族、知人などに見られる可能性は低く、過剰に心配する必要はないでしょう。
本コラムでは、自己破産して官報に掲載されるとどうなるか、掲載時期や掲載される内容、官報に載らずに債務整理する方法などについて、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。コラム全文はこちら -
公開: 2025年12月16日
- 自己破産
- 残クレ
- 破産

残クレで破産したら車は没収? 手放さずに済む? 借金を整理する方法
「残クレの支払いがもう限界……」そのような状況に追い込まれていませんか。
残価設定型クレジット(残クレ)は、月々の負担が軽く見える一方で、契約満了時に高額な残価精算や乗り換え判断を迫られます。生活に欠かせない車なのに、支払いができず自己破産まで考える人も少なくありません。
自己破産になれば、原則として車を手放さなければなりません。しかし、借金の負担を減らす「債務整理」には、任意整理や個人再生など、ほかにも種類があります。状況に応じた最適な手段を選択することで、車を手元に残したまま借金問題を解決できる可能性があるのです。
今回は、残クレ契約中に自己破産すると車がどうなるのか、手放さずに済む方法はあるのか、自己破産以外の借金整理の選択肢などを、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。コラム全文はこちら -
更新: 2025年12月03日
- 自己破産
- 自己破産
- 退職金

自己破産は退職金も処分対象? バレずに手続きを進めるコツを解説
借金問題の解決手段として自己破産を選択すれば、裁判所から免責許可を得られた場合に限り、原則としてすべての借金返済義務が帳消しになります。
ただし、自己破産の強力な借金減額効果を享受するには、自己破産特有の「財産処分」に注意しなければなりません。特に会社員の方が自己破産をする場合は、退職金という大きな財産の扱いが問題になります。
本コラムでは、自己破産をしたときの退職金の取り扱いについて、差し押さえにならないかどうかなど、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。自己破産手続きは、財産処分以外にも注意すべき点が少なくありません。想定外のデメリットを被る事態を避けるためにも、事前に弁護士までご相談ください。コラム全文はこちら
カテゴリを選ぶ
- トップページ
- 債務整理 弁護士コラム
- 自己破産
- 自己破産は退職金も処分対象? バレずに手続きを進めるコツを解説