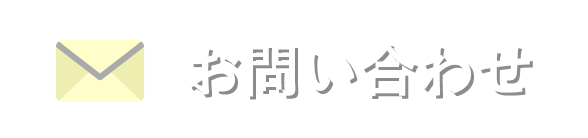- トップページ
- 債務整理 弁護士コラム
- 自己破産
- 自己破産すると連帯保証人はどうなる? 迷惑をかけない解決方法
債務整理 弁護士コラム
自己破産すると連帯保証人はどうなる? 迷惑をかけない解決方法
- 自己破産
- 自己破産
- 連帯保証人

自己破産をすれば、お金を借りた本人の借金返済義務はすべて免除されますが、連帯保証人に迷惑がかかることがあります。実際、「自己破産すると連帯保証人はどうなるのだろうか」と気になっている方は多いことでしょう。
連帯保証人がいる場合は、自己破産をする前に事情を伝えるべきですが、一方では、連帯保証人に迷惑をかけずに借金問題を解決できる方法もあります。
本コラムでは、自己破産をすると連帯保証人にどのような影響が及ぶのか、迷惑をかけない3つの解決方法について、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。
1、自己破産すると連帯保証人はどうなる?
連帯保証人とは、主債務者(お金を借りた本人)と連帯して債務を負う保証人のことです。「保証人」の一種ですが、主債務者と同じ返済義務を負うという特徴があります。主債務者が自己破産をすると、連帯保証人には次のような影響が及びます。
-
(1)残債務の一括返済を請求される
主債務者が自己破産をして借金を返済しないことになると、債権者は連帯保証人に残債務の返済を請求します。このとき、通常は一括返済を求められます。
なぜなら、債権者との契約で、主債務者が自己破産などの債務整理をしたときには期限の利益を失う旨が定められていることがほとんどだからです。期限の利益とは、「返済期限までは借金を返済しなくてよい」という債務者の権利のことですが、当初の契約が分割払いであっても、期限の利益を失うと残債務の全額をすぐに返済しなければなりません。
返済できない場合は、連帯保証人が債権者から裁判を起こされ、最終的には財産を差し押さえられることもあります。 -
(2)主債務者への求償権は失う
連帯保証人が主債務者に代わって借金を返済した場合には、その金額を主債務者に対して請求できる「求償権」が生じます(民法第459条1項)。
しかし、主債務者が自己破産をして免責が許可されると、連帯保証人に対する求償債務も免除されます。そのため、連帯保証人としては残債務の全額を返済したとしても、主債務者からお金を返してもらうことはできません。 -
(3)連帯保証人も自己破産を要することがある
連帯保証人と債権者との話し合いによって分割払いが認められることもありますが、どうしても返済できない場合、連帯保証人は自分の債務として債務整理を検討する必要があるでしょう。
実際のところ、主債務者と連帯保証人が一緒に自己破産するケースが多々あります。
2、連帯保証人と保証人で自己破産による影響は異なる?
連帯保証人と保証人は、どちらも主債務者の債務を保証する人のことですが、法律上は重要な違いがあります。ここからは、主債務者が自己破産した場合の影響の違いについて、見ていきましょう。
-
(1)返済額は異なることがある
複数の連帯保証人あるいは保証人がいる場合、「保証人」は自分の負担分のみを返済すれば足ります(民法第456条)。このことを「分別の利益」といいます。しかし、「連帯保証人」には分別の利益が認められていないため、残債務全額の返済義務を負わなければなりません。
たとえば、ひとつの借金について連帯保証人1人と保証人1人が付いている場合、主債務者が自己破産をすると、連帯保証人は残債務全額の返済請求を受けます。
一方、保証人は2分の1の金額についてのみ、返済請求を受けるだけです。保証人が全額の返済請求を受けたとしても、分別の利益を主張して、2分の1の金額については返済を拒否することができます。
実際、日本学生支援機構から連帯保証人と保証人を付けて奨学金を借りた場合、主債務者が自己破産すると、連帯保証人には残債務全額、保証人には2分の1の金額の返済が請求されています。 -
(2)返済を請求される時期は異ならない
連帯保証人あるいは保証人が「いつ」債権者から返済請求を受けるのかについて、法律上の違いはありますが、実際、ほとんど違いはありません。
法律上、連帯保証人には催告の抗弁権がないので、主債務者よりも先に請求された場合でも、返済を拒否することができないのです(同法第454条)。
とはいえ、実際には、金融機関や貸金業者は、主債務者からの債権回収が難しい状況になるまで連帯保証人に返済を請求することはありません。
一方、保証人は債権者から請求を受けたときに「先に主債務者へ請求してください」と主張できる「催告の抗弁権」を有しています(民法第452条本文)。
ただし保証人であっても、主債務者が自己破産をした場合は、催告の抗弁権を行使できなくなることに注意が必要です(同法第452条但書)。
したがって、主債務者が自己破産をするような場面では、連帯保証人であっても保証人であっても債権者から返済請求を受ける時期にほとんど違いはありません。 -
(3)差し押さえのリスクは異ならない
差し押さえのリスクについても、法律上は保証人よりも連帯保証人の方が高いリスクを負っていますが、実際のところ、ほとんど違いがないといえます。
債権者が主債務者に請求した後に保証人に返済を請求した場合でも、法律上、保証人は「先に主債務者の財産を差し押さえてください」と主張できる「検索の抗弁権」を有しています(民法第453条)。
ただし、主債務者が自己破産をすると、保証人も検索の抗弁権を主張できなくなります。債権者は抵当権などの物的担保権がない限り、主債務者の財産を差し押さえることができないからです。
一方、連帯保証人には法律上、検索の抗弁権がないので、主債務者が延滞をすると、債権者はいつでも裁判と強制執行の手続きを踏んで、連帯保証人の財産を差し押さえることが可能となります。
とはいえ、実際、金融機関や貸金業者は、主債務者からの債権回収が難しい状況になるまで連帯保証人の財産の差し押さえを実行することはありません。
したがって、主債務者が自己破産をするような場面では、連帯保証人であっても保証人であっても差し押さえのリスクにほとんど差はないのです。
3、連帯保証人がいる場合に自己破産するときの3つの注意点
連帯保証人がいる場合に自己破産をするときには、次の3点に注意しましょう。
-
(1)連帯保証人付きの借金を優先的に返済してはいけない
連帯保証人に迷惑をかけたくないからといって、自己破産申し立ての直前に連帯保証人付きの借金のみを優先し、一括返済等すると、免責不許可事由に該当し(破産法第252条1項3号)、免責が認められなくなるおそれがあります。
自己破産をするためには、連帯保証人付きの借金も他の借金と平等に自己破産手続きの対象としなければなりません。 -
(2)連帯保証人にお金を支払ってもいけない
連帯保証人付きの借金を自己破産手続きの対象にすると、連帯保証人が返済請求を受けますが、お詫びのつもりでも連帯保証人にお金を支払ってはいけません。
自己破産申し立ての直前または自己破産の手続き中にこのような行為をすると、財産隠しとみなされ、やはり免責が認められなくなるおそれがあります(破産法第252条1項1号)。
それに、連帯保証人に支払ったお金は破産管財人によって取り戻されるため(同法第160条1項2号)、結果としてお詫びしたことにもなりません。
どうしてもお詫びをしたいのであれば、自己破産手続きが終了(免責許可決定が確定)した後にすべきです。 -
(3)連帯保証人付きの借金を隠して申し立ててはいけない
連帯保証人付きの借金を隠して自己破産を申し立てた場合も、免責不許可事由に該当し(破産法第252条1項7号)、免責が認められなくなるおそれがあります。
隠しておけばバレないだろうと考える人もいますが、申立書類と添付資料は裁判所や破産管財人によって精査されますし、破産手続開始決定が出ると官報にも掲載されるので、隠した債権は必ず発覚すると考えるべきです。
4、連帯保証人に迷惑をかけずに借金問題を解決する3つの方法
連帯保証人に迷惑をかけずに借金問題を解決する方法として、次の3つが挙げられます。
-
(1)住宅の任意売却
住宅ローンに連帯保証人が付いている場合には、住宅を任意売却することが考えられます。
任意売却によれば、競売よりも高額で売却できるケースが多いので、場合によっては売却代金で住宅ローンの残高を完済することも可能です。完済に至らない場合でも、借入先との交渉によって主債務者が残高を分割払いすることが認められれば、連帯保証人に迷惑はかかりません。 -
(2)任意整理
任意整理とは、裁判所を介さず債権者と直接交渉する手続きです。そのため、整理する債権者を自由に選べます。連帯保証人付きの借金はそのまま返済を継続し、他の借金のみを任意整理すれば、連帯保証人に迷惑はかかりません。
ただし、任意整理は債務整理の中でもっとも減額幅が小さいので、借金総額が大きいケースには、あまり向いていません。それでも、家族や親戚などが返済に協力してくれる場合には、任意整理を検討する価値はあるといえます。 -
(3)個人再生
住宅ローンに連帯保証人が付いている場合には、個人再生をすることも考えられます。「住宅ローン特則」を適用できれば、住宅ローンだけは今までどおりに返済を継続することが認められるので、連帯保証人に迷惑はかかりません。
住宅ローン特則付き個人再生をすることで、住宅ローン以外の借金は5分の1~10分の1程度にまで減額され、かつ、持ち家を残すことも可能という大きなメリットも得られます。
5、まとめ
連帯保証人は主債務者と同等の返済義務を負っているため、主債務者が自己破産をすると、どうしても連帯保証人に迷惑がかかってしまいます。迷惑がかかることを前提として自己破産をすべきか、他の方法で解決を図るべきかは、具体的な状況に応じて検討すべきです。
最善の解決方法を選択するためには専門的な知識も必要なので、弁護士に相談した方がよいでしょう。
ベリーベスト法律事務所では、債務整理専門チームの経験豊富な弁護士が、具体的な事情を考慮して最適な解決方法をご提案いたします。自己破産や借金問題に関するご相談は何度でも無料ですので、まずはご相談ください。

- 菅谷 良平 パートナー弁護士
- 弁護士会: 東京弁護士会
- 登録番号: 47122
債務整理部マネージャー弁護士として、債務整理・借金問題及びその周辺分野に精通しています。これまで、お客さまの生活再建に向けて、数多くの案件に対応してまいりました。債務整理のご相談は、何度でも無料です。任意整理、自己破産、個人再生など、借金問題についてお悩みの方は、ぜひお気軽に ご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています


同じカテゴリのコラム(自己破産)
-
更新: 2025年12月25日
- 自己破産
- 自己破産
- 官報

自己破産すると官報に名前が出る? 家族にバレる可能性や掲載時期
多額の借金を抱えても、一定の条件を満たす場合は、自己破産によってすべての借金の支払い義務を免れることができます。ただし、自己破産をすると「官報」に氏名や住所が掲載され、全国に公表されてしまいます。
官報に掲載されることが不安で、自己破産するか迷っている方もいるかもしれません。しかし、会社や家族、知人などに見られる可能性は低く、過剰に心配する必要はないでしょう。
本コラムでは、自己破産して官報に掲載されるとどうなるか、掲載時期や掲載される内容、官報に載らずに債務整理する方法などについて、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。コラム全文はこちら -
公開: 2025年12月16日
- 自己破産
- 残クレ
- 破産

残クレで破産したら車は没収? 手放さずに済む? 借金を整理する方法
「残クレの支払いがもう限界……」そのような状況に追い込まれていませんか。
残価設定型クレジット(残クレ)は、月々の負担が軽く見える一方で、契約満了時に高額な残価精算や乗り換え判断を迫られます。生活に欠かせない車なのに、支払いができず自己破産まで考える人も少なくありません。
自己破産になれば、原則として車を手放さなければなりません。しかし、借金の負担を減らす「債務整理」には、任意整理や個人再生など、ほかにも種類があります。状況に応じた最適な手段を選択することで、車を手元に残したまま借金問題を解決できる可能性があるのです。
今回は、残クレ契約中に自己破産すると車がどうなるのか、手放さずに済む方法はあるのか、自己破産以外の借金整理の選択肢などを、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。コラム全文はこちら -
更新: 2025年12月03日
- 自己破産
- 自己破産
- 退職金

自己破産は退職金も処分対象? バレずに手続きを進めるコツを解説
借金問題の解決手段として自己破産を選択すれば、裁判所から免責許可を得られた場合に限り、原則としてすべての借金返済義務が帳消しになります。
ただし、自己破産の強力な借金減額効果を享受するには、自己破産特有の「財産処分」に注意しなければなりません。特に会社員の方が自己破産をする場合は、退職金という大きな財産の扱いが問題になります。
本コラムでは、自己破産をしたときの退職金の取り扱いについて、差し押さえにならないかどうかなど、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。自己破産手続きは、財産処分以外にも注意すべき点が少なくありません。想定外のデメリットを被る事態を避けるためにも、事前に弁護士までご相談ください。コラム全文はこちら
カテゴリを選ぶ
- トップページ
- 債務整理 弁護士コラム
- 自己破産
- 自己破産すると連帯保証人はどうなる? 迷惑をかけない解決方法