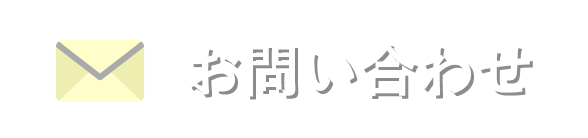- トップページ
- 債務整理 弁護士コラム
- 自己破産
- 社長の自己破産について 自分自身・家族・会社への影響は?
債務整理 弁護士コラム
社長の自己破産について 自分自身・家族・会社への影響は?
- 自己破産
- 社長
- 自己破産

企業の経営が傾いてしまうと、社長自身も自己破産を考える場面もあるかと思います。
自己破産後、新たに起業は可能なのか、また会社が破産しない場合は、社長として再度復帰できるのかなど気になるところでしょう。
今回の記事では、そんな社長の自己破産について、
・社長の自己破産とはどういうことなのか?
・社長が自己破産をしたらその後の生活にどのような影響が出るのか?
・自己破産によるリスクを最小限に抑えるためには?
などについて、詳しくご紹介していきます。
ご参考になれば幸いです。
1、会社の破産に伴う社長の自己破産
経営が苦しくなり資金繰りなどが困難になった場合には、会社は破産することもあるでしょう。
中小企業の場合には、代表取締役である社長は、会社の債務について個人保証をしている場合が多いため、社長個人もそれに伴って自己破産をせざるを得ないケースもあります。
2、社長が自己破産したらもう起業はできない!?
では、会社の破産によって社長が自己破産をしたら、その後はどのような影響が出るのでしょうか?
もう二度と起業することはできないのでしょうか?
-
(1)基本的に起業は可能
現在では、自己破産をした人が再度起業をしてはいけない、という法律はありません。
よって、社長が自己破産をしたとしても、もう一度起業することは基本的には可能です。 -
(2)例外な事由について
ただし、例外もあります。
- 割賦販売業者
- 貸金業者
- 質屋
- 旅行業
- 保険業
- 警備業
- 建築業
- 下水道処理施設維持管理業
- 風俗業
- 廃棄物処理業者
- 古物商
これらの事業を新たに立ち上げる際は、復権する必要がありますので注意が必要です。
ほとんどの場合、たとえば、「財産隠し」や「裁判所・破産管財人の業務妨害」などをしていなければ、さほど時間をかけずに免責許可を受けられ、復権できるでしょう。
しかし、自己破産手続きの内容によっては(これらに該当する場合には)、復権するまでに半年〜1年ほどの期間がかかってしまう可能性も十分あり得ます。 -
(3)起業する場合は資金調達方法に工夫が必要
起業をする際には、資金の調達方法に工夫が必要です。
なぜなら、破産すればブラックリストに載ってしまい、個人での借り入れはできなくなるからです。
自己破産を理由に個人での銀行からの借り入れができない場合には、クラウドファンディングやプロジェクトファイナンスの検討、知人からの出資を期待できるかなど、資金繰りの工夫が必要となってきます。
ただし、現代では、資本金を必要としないビジネスもたくさんありますし、起業する手段は多岐にわたりますので、そういった事業にチャレンジすることも賢い判断だといえるでしょう。
3、社長のリスクを最小限に止めるためには
もしも会社が破産をするとなった場合には、社長のリスクを最小限に抑えるために、どのような対策をとればよいのでしょうか?
この章では、自己破産に伴う社長のリスクヘッジについて、ご紹介していきます。
-
(1)会社の債務整理は早めの着手が大切
会社の債務が膨大である場合、社長が会社の連帯保証人になっているときは、社長も個人資産では返済しきれないため、社長個人の(破産を含めた)債務整理は避けられないでしょう。
しかし、早めの対応により、会社の債務を可能な限り小さく抑えることができれば、社長の個人資産の範囲内で対応ができる可能性もあります。
そうなれば、会社が倒産することもなく、社長個人も債務整理自体せずに済むことも考えられます。
このため、会社の経営悪化への対策は、早めに行うことが何よりも重要と言えるでしょう。 -
(2)早期相談によって会社の債務整理を上手に行う
また、社長個人の債務整理は免れないにせよ、会社の債務対策を早期に行うことにより、破産以外の債務整理で対応できるケースもあるでしょう。
破産でなければ自宅等の資産を残すことができ、家族への影響も小さくて済みます。
不安がある場合は、早めに弁護士等へ相談することが大切です。 -
(3)経営者保証ガイドラインを利用する
経営が完全に行き詰まり、自己破産をするしかないという状況になる前の段階で、早期に債務整理を始めることができれば、自己破産以外の方法で処理できる可能性もあります。
その1つの方法が、経営者保証ガイドラインです。
これを適用することで、個人で保証をしている負債についても、自己破産した場合よりも有利な内容で処理することができる可能性があります。
①経営者保証ガイドラインとは
まず、経営者保証ガイドラインとは、平成26年から運用が開始された制度です。
社長自らの個人負担は、事業拡大や、会社の早期適正処理の妨げとなっていることが多いと考えられることから、これを防ぐために策定された制度です。
上記でも記載したように、経営者保証ガイドラインを適用することで、個人保証の負債について、自己破産した場合よりも有利な取り扱いで処理することができる可能性があります。
②経営者保証ガイドラインを適用するための要件とは?
経営者保証ガイドラインを適用するための要件において、もっとも重要なことは、
「債権者にとってのメリットをきちんと示せるか?」
です。
そのために必要なことは、やはり早期の対応です。
逆に、対応が遅れてしまえば、経営状況はさらに悪化し、債権者にとっての経済的合理性も失われていきます。
なので、会社の立ち行きが困難になる前に、早期の対応をするようにしましょう。
それ以外にも、経営者保証ガイドラインを適用するための要件としては、以下の3つがあります。- 主債務者である会社が、裁判所における倒産手続き、もしくは、中立かつ公正な第三者の関与している私的整理手続き(私的整理ガイドラインに基づく私的整理)を申し立てていること(適正な倒産手続き)
- 実際に行われる、会社の倒産手続きにおける配当額が、通常の破産手続きを行った場合よりも大きくなることが見込めること(債権者にとっての経済的合理性)
- 保証人である経営者に破産法が定めているような免責不許可事由がなく、またそれが発生するおそれがないこと(保証人が誠実であること)
簡単に説明すると、きちんとした手続きを早期に始めることが大切だということです。
そうすることで、2つめの「債権者にとっての経済的合理性」の要件に該当する可能性が高まります。
③経営者保証ガイドラインが適用されることによる社長のメリット
もしも経営者保証ガイドラインが適用されれば、自己破産をした場合よりもかなり有利な状況を作ることが可能になります。
具体的には、- 個人保証分の減額・免除・返済猶予を受けられる
- 自己破産の自由財産(99万円)よりも多くの財産を手元に残せる
- 住居用の不動産を処分せずに済む(生活に必要な程度を超える、豪華な不動産の場合は処分されます)
- 信用情報への登録がない(ブラックリストに載らない)
といったことです。
自己破産をしたときよりも多くの財産を残せたり、自宅などを処分されずに済んだり、また、ブラックリストに載らないことで、その後の生活への影響を減らしたりすることもできます。
このように、経営者保証ガイドラインが適用されれば、個人保証の返済額が少なくことだけでない大きなメリットを享受できるのです。
4、会社の破産に伴わない、個人的な破産の場合の注意点
この章では、会社に伴わない個人的な破産をする場合について、注意点をご紹介していきます。
-
(1)株式会社の場合
株式会社の社長が自己破産したときには、その会社の社長を必ず退任しなければなりません。
民法第653条第2号
委任者又は受任者が破産手続き開始の決定を受けたこと。
株式会社と取締役の関係は委任契約なのですが、こちらの条文のように、委任は、当事者の一方が破産したときには終了すると規定されているからです。
つまり、株式会社の社長が自己破産をする場合には、その会社の社長を退任する必要があります。
ただし、任意整理や個人再生に関しては、必ずしも退任する必要はありません。
自己破産によって退任した社長が再任するには、株主総会決議が必須条件となります。
上場していない企業や、家族経営などの閉鎖的な企業であれば、退任翌日に株主総会が開かれ、即座に社長の再任決議がなされることも少なくありません。
ただ、上場企業や大手企業になると、株主の数も多いことから、すぐに株主総会を開くことは困難です。
この場合には、多くの時間や負担がかかることが予想されます。
定款とは異なる手順・方式でなされた決議は無効となりますので、多少時間がかかったとしても、必ずこの流れを経る必要があるということは抑えておきましょう。 -
(2)持ち分会社の場合
一般的な持ち分会社では、「役員が自己破産した場合には退任する」と定められています。
このように定められているのは、持ち分会社の役員の場合には、会社への出資金の処理をしなければならないからです。
持ち分会社の場合、社長は会社に対して、「出資金の返還請求権」を有していると考えられます。
そのため、自己破産によって、この「出資金の返還請求権」が差し押さえ対象になることから、社長はその会社の出資者でなくなり、それと同時に、社長の地位も失うという流れになります。
これはあくまでも、多くの会社で行われている、一般的なケースにおいての内容です。
実際には、それぞれの定款の定めに従うことになります。
持ち分会社の場合も、株主総会と同様に、定款の定めどおりに行えば、自己破産後すぐに社長に再任することは十分可能です。
ただし、持ち分会社の社長(業務執行役員)になるためには、「出資者」になる必要があります。
そのため、自己破産をした後にどこからそのお金を調達するのかなどを考える必要がありますので、その際には工夫が必要です。
5、会社の倒産、社長の債務整理については早めに弁護士に相談を
ここまで、社長の自己破産についてご紹介してきましたが、総じて言えることは、「早期の相談が何よりも大切」だということです。
早期に相談をすることで、負債額を減額できたり、その後の生活への影響を最小限に抑えることも可能になるからです。
ここは必ず理解しておきましょう。
-
(1)会社の倒産に関する注意事項
会社の破産を決定した際、
- 一部の債権者のみへの返済
- 会社在庫の処分
などは、破産手続きにおいて不利に働く可能性があります。
そういった返済や処分が適切であるかどうかの判断は非常に難しいため、独自に判断することなく、早めに弁護士へ相談することが賢明です。 -
(2)社長個人のダメージを抑えるには早期相談が重要
お伝えしてきたように、経営難が進行する前の早めの相談は、社長個人のダメージを抑えるためにも必要不可欠だといえます。
自己破産をした後にも人生は続いていきますから、その後の影響を最小限に抑えるためにも、必ず「早期に相談する」という意識を持ってください。
6、まとめ
今回は、社長の自己破産についてご紹介してきました。
自己破産にはあまり良くないイメージも多いですから、なかなか一歩を踏み切れない方も多いでしょう。
しかし、社長が自己破産をしたとしても、その後の人生で再スタートができるルートはたくさん存在しています。
むしろ、自己破産をすることで得られるメリットの方が大きいともいえます。
そういったことを実感していただくためにも、早めに弁護士へ相談をし、ご自身にとって最適な方法を選択していただければ幸いです。

- 萩原達也 代表弁護士
- 弁護士会: 第一東京弁護士会
- 登録番号: 29985
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
債務整理、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金請求など、借金問題についてのお悩み解決を弁護士がサポートいたします。債務整理のご相談は何度でも無料です。ぜひお気軽に お問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています


同じカテゴリのコラム(自己破産)
-
更新: 2025年05月28日
- 自己破産
- 自己破産後の生活

自己破産後の生活はどう変わる? 普通の暮らしを取り戻すために注意するべきこと
多額の借金を背負っても、自己破産をして免責が許可されれば借金はゼロとなり、人生の再スタートを切ることができます。
実際、令和3年、自己破産を裁判所に申請し受け付けられた件数は、6万8240件でした。(令和3年司法統計第105表 「破産新受事件数 受理区分別 全地方裁判所」より)
とはいえ、自己破産をしてしまうと、その後の生活においてさまざまな制限に悩まされることになると考えている方も多いのではないでしょうか。
たしかに、自己破産をすると、その後の生活への影響がゼロというわけではありません。しかし、実は多くの方が心配しているほど制限された生活を余儀なくされるわけでもありません。自己破産後の生活が気になる方は、本コラムを参考にしてみてください。コラム全文はこちら -
更新: 2025年05月26日
- 自己破産
- 自己破産
- 債務整理
- 違い

債務整理と自己破産の違いがよく分かる! 特徴とメリット・デメリット
抱えている借金をどうにかしようと調べたときに「債務整理」や「自己破産」といった言葉を見聞きすることでしょう。
債務整理とは、多額の借金を抱えて返済できなくなったとしても、借金を減額または免除する(ゼロにする)ことができる方法です。借金問題をスムーズに解決するためには、債務整理と自己破産の違いだけでなく、任意整理や個人再生などの手段を正確に理解し、状況に合った手続きを選択することが重要といえます。
本コラムでは、債務整理と自己破産の違いをはじめに、自己破産と任意整理または個人再生との違い、また、どのような場合に自己破産を選ぶべきなのかについて、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。コラム全文はこちら -
更新: 2025年05月08日
- 自己破産
- 自己破産
- 申し立て後

自己破産申し立て後の流れと期間、してはいけないことを紹介
自己破産は、裁判所に申し立てるだけで終わるものではありません。事案によっては申し立て後の手続きに半年~1年程度の期間を要することもあります。
自己破産を成功させるためには、申し立て後にもさまざまなことに注意しなければなりません。コラム全文はこちら
カテゴリを選ぶ
- トップページ
- 債務整理 弁護士コラム
- 自己破産
- 社長の自己破産について 自分自身・家族・会社への影響は?