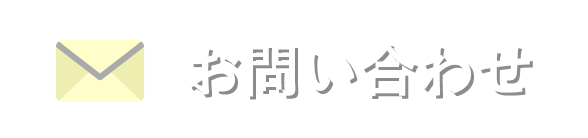- トップページ
- 債務整理 弁護士コラム
- その他
- 老後破産とは? 老後に自己破産するメリットとデメリットを解説
債務整理 弁護士コラム
老後破産とは? 老後に自己破産するメリットとデメリットを解説
- その他
- 老後破産

近年、老後破産に陥る人が増えています。もともと年金を十分にもらえない人も多いことに加えて、物価の上昇や税金、社会保険料などの負担の増大といった社会状況の変化に伴い、老後の生活で経済的に困窮する人が増加しているのです。
なかには多額の借金を抱えており、悩んでいる方もいるでしょう。そのような場合は、自己破産が有効です。自己破産は、借金の負担を減らす債務整理の一種で、年齢を問わず、免責の条件を満たせば借金から解放され、経済生活の立て直しを図ることができます。
本コラムでは、老後破産の意味を解説した上で、老後に自己破産するメリットとデメリット、自己破産後の生活に備えるための対処法について、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。
1、老後破産とは
一般的に報道などで用いられる「老後破産」という言葉は、借金の有無には関係なく、老後の生活で経済的に破綻してしまうことを指しています。
年金だけでは老後の生活費をまかなうことができず、十分な貯蓄もなければ、生活に困窮してしまうでしょう。自己破産をしていなくても、老後に貧困状態に陥ることが「老後破産」と呼ばれています。
もちろん、老後に借金を抱えて自己破産をすることも「老後破産」のひとつです。
誰しも老後破産は回避したいはずですが、返済できないほどの借金を抱えてしまった場合には、自己破産をするのも悪いことではありません。自己破産は経済生活を立て直すために法律で定められた正当な手段なので、必要に応じて利用を検討しましょう。
2、老後の自己破産で得られる3つのメリット
自己破産の最大のメリットは、借金の返済義務が全額免除されることです。老後の自己破産においては、以下のように現役世代の自己破産とは異なるメリットも得られます。
-
(1)破産・免責が認められやすい
自己破産は、「支払不能」の状態でなければ認められません。支払不能とは、客観的に見て借金の返済を継続していくだけの支払い能力がない状態のことです。
高齢者の場合は、年金を受給していても十分な金額ではないことが多く、今後仕事をして収入を増やすことも難しいのが実情です。そのため、現役世代の場合よりも少ない借金額(たとえば100万円未満など)でも「支払不能」と認められやすいといえます。
また、あくまでも傾向としてですが、免責も高齢者の方が認められやすいといえます。浪費やギャンブルなどの「免責不許可事由」(破産法第252条1項各号)がある場合には、原則として免責は認められません。しかし、老後に入って収入が減少してから作った借金であれば、生活費のためのやむを得ない借金であることが多いでしょう。
また、若いときの浪費やギャンブルが原因で始まった借金であっても、長期間にわたって返済を継続していれば、追加の借入があったとしても、主に借金返済や生活費のための借金に変容していると判断される可能性も出てきます。
さらに、将来的な増収の見込みが乏しければ、自己破産以外に解決方法がないと判断されやすいため、裁量免責(破産法第252条2項)が認められる可能性も高いといえます。 -
(2)公的年金を受給しながら借金をなくすことができる
自己破産をしても、国民年金や厚生年金といった公的年金や、確定拠出型の企業年金には影響がなく、全額受給することができます。したがって、基本的に今までどおりの収入を維持しながら、自己破産で借金の免責許可を受けることが可能です。
この点、自己破産の手続き中は一部の職種への就業が制限されるため、現役世代なら、場合によっては退職を余儀なくされて収入が途絶えるおそれもあります。 -
(3)借金の相続を回避できる
老後に自己破産をして借金をなくしておけば、自分が亡くなった後に配偶者や子どもなどの相続人が債務を相続してしまうことを回避できます。
相続人は相続放棄によっても借金の相続を回避できますが、その場合は手間や費用の負担を避けることができません。また、プラスの遺産も一切受け取れないというデメリットもあります。
相続人に迷惑をかけたくなければ、自己破産を検討した方がよいでしょう。
3、老後の自己破産で注意すべき3つのデメリット
老後の自己破産には、以下のデメリットもあるので注意が必要です。
-
(1)一定以上の財産を失う
自己破産をすると、次の範囲を超える財産は原則としてすべて処分されてしまいます。
- 99万円以下(東京地方裁判所の運用では33万円以下)の現金
- その他の財産で評価額20万円以下のもの
公的年金が差し押さえられることはありませんが、個人年金や生命保険については、解約返戻金見込み額が20万円を超える場合は全額が処分の対象となります。個人年金や生命保険の解約返戻金を老後の生活費の当てにしていた人は、注意が必要です。
なお、自己破産の申し立て前に財産の名義を家族などに変更することは、財産隠しに該当します。
財産隠しが発覚すると免責が許可されない(破産法第252条1項1号)だけでなく、詐欺破産罪(破産法第265条1項1号)に問われるおそれもあるので、絶対に行ってはいけません。 -
(2)連帯保証人に迷惑がかかることがある
高齢者の中には、連帯保証人を立てて借りた住宅ローンや事業ローンなどが完済できずに残っている人もいることでしょう。
連帯保証人がいる場合に自己破産をすると、連帯保証人が残高の返済請求を受けてしまいます。連帯保証人も返済できない場合は、連帯保証人自身も自己破産などの債務整理を検討する必要があるでしょう。
なお、連帯保証人付きの借金を隠して自己破産を申し立てたり、申し立て前にその借金のみを一括返済したりすると免責が許可されなくなるため(破産法第252条1項3号、7号)、行ってはいけません。 -
(3)認知症の場合は成年後見人の選任が必要
認知症の診断を受けた人が自己破産をするためには、先に家庭裁判所で成年後見人を選任する必要があります。なぜなら、認知症を発症した人は民法上「意思能力がない」ものとして扱われるため、自己破産の申し立てという法律行為を単独ですることはできないからです。
成年後見人選任の手続きは一般的にさほど難しいものではありませんが、それなりの手間と費用がかかります。近年は、近親者ではなく弁護士や司法書士といった法律専門職が成年後見人に選任されることが多い傾向にあることにも注意しましょう。法律専門職が成年後見人となった場合には、被後見人(認知症の人)が亡くなるまで毎年2~6万円程度の報酬を支払う必要があります。
4、自己破産後の生活に備えるための対処法
借金問題は自己破産で解決できますが、自己破産後の生活設計もあらかじめ考慮しておく必要があります。高齢者が自己破産後の生活に備える場合には、以下の対処法が有効です。
-
(1)自由財産拡張の申し立てで多くの財産を確保
本来は自己破産で処分される財産でも、裁判所に「自由財産拡張の申し立て」をすれば手元に残せる可能性があります。
「自由財産」とは、破産後も債務者の手元に残せる財産のことです。本来は自由財産に含まれない財産でも、債務者の経済的更生のために必要不可欠なものがある場合には、裁判所の判断で自由財産の範囲が拡張されることがあるのです。
高齢者の自己破産で自由財産の拡張が認められやすい財産としては、次のようなものが挙げられます。- 預貯金:主として公的年金や個人年金を原資とするもので、当面の生活に必要と考えられる金額については自由財産拡張が認められやすい
- 生命保険:医療保険がセットになっているもので、解約すると債務者が同等の条件で医療保険に再加入することが難しい場合は、自由財産拡張が認められやすい
- 自動車:交通が不便な居住環境で、債務者の体力が衰えていて、自動車がなければ買い物や通院などの日常生活に支障をきたすような場合は、自由財産拡張が認められる可能性がある
-
(2)住宅ローンの残高が少ない場合は任意売却
老後も住宅ローンが残っている場合には、自己破産をする前に任意売却をするのもひとつの方法です。
住宅は競売よりも任意売却の方が高額で売れる可能性が高く、アンダーローンなら売却価格によっては、自己破産しなくても借金を整理できることもゼロではありません。
自己破産を回避できないとしても、任意売却なら通常、引っ越し費用は売却代金の中から提供されます。 -
(3)生活費が足りない場合は生活保護を申請
自己破産後の生活費の目処がどうしても立たない場合には、生活保護の申請を検討するとよいでしょう。自己破産をしても、生活保護を受給することに支障はありません。
自己破産の申し立てと生活保護の申請は、どちらを先にしても問題ないですが、理想的な流れとしては、自己破産を弁護士に依頼した後、自己破産の申し立て準備と生活保護の申請を並行して進めることです。
弁護士に依頼すると、数日中に受任通知が債権者に届き、督促や返済がいったん止まります。それから落ち着いて、生活保護を申請するとよいでしょう。自己破産の申し立て準備は、弁護士が主導して進めます。
弁護士費用については、分割払いを利用できる事務所も少なくありません。ある程度の財産がある場合には、弁護士の助言に従って換金し、弁護士費用の支払いに充てることもできます。
5、まとめ
老後の自己破産にはデメリットもありますが、借金の返済から解放されるというメリットは何ものにも代えがたいものです。
自己破産手続きは複雑ですが、弁護士に依頼すれば全面的なサポートが受けられるので、安心して任せることができます。
ベリーベスト法律事務所では、借金問題に関するご相談は何度でも無料で受け付けています。老後の自己破産をお考えの方は、ぜひ一度、債務整理専門チームを組成している当事務所の無料相談をご利用ください。

- 萩原達也 代表弁護士
- 弁護士会: 第一東京弁護士会
- 登録番号: 29985
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
債務整理、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金請求など、借金問題についてのお悩み解決を弁護士がサポートいたします。債務整理のご相談は何度でも無料です。ぜひお気軽に お問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています


同じカテゴリのコラム(その他)
-
公開: 2026年01月29日
- その他
- 保証債務とは

【事例でわかる】保証債務の仕組みとリスク軽減のための具体策
友人や親族から「保証人になってほしい」と頼まれた際、断りづらさから安易に応じてしまう人もいます。しかし、保証契約は単なる形式的な署名ではなく、保証人に重い法的責任を負わせるものです。
特に「連帯保証」では、債権者が主債務者を飛ばして直ちに保証人へ請求できるため、負担は極めて重くなります。
今回は、保証債務の定義や仕組み、通常の保証と連帯保証の違い、保証人が直面するリスクや責任範囲などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。コラム全文はこちら -
公開: 2026年01月15日
- その他
- 差し押さえ
- 持っていかれるもの

差押えで持っていかれるもの、持っていかれないものをカンタンに解説
借金の返済が滞ってしまうと、最終的に「差押え」という強制執行に発展することがあります。差押えで持っていかれる可能性があるものには、預金や給与の一部、不動産や車など、日常生活に欠かせない財産が含まれており、生活への影響は計り知れません。
しかも、借金の返済が滞った場合、信用情報に影響が出るため、クレジットカードの利用停止がなされる場合もあります。また、差押えされた場合、銀行口座が凍結されたり、勤務先に借金が知られたり、信用や人間関係にまで波及する場合があります。そのため、精神的な負担も非常に大きく、日常生活そのものが立ち行かなくなるケースも少なくありません。
もっとも、すべての財産が差押えの対象になるわけではなく、法律で「生活に最低限必要な財産」は守られています。また、事前に債務整理を行うことで差押えを防ぐことも可能です。今回は、差押えで持っていかれるもの・持っていかれないもの、差押えが生活に与える影響などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。コラム全文はこちら -
更新: 2025年12月25日
- その他
- 闇金

闇金被害は弁護士に相談を! 悪質な手口や正しい対処法を解説
一般的な金融機関から借り入れができなくなって闇金に手を出してしまい、深刻な被害に遭ってしまう人は後を絶ちません。
闇金は、「審査なし」「ブラックOK」「誰でも即日融資」などの甘い文句で勧誘してくるものです。しかし、闇金は到底支払えないような高金利を要求し、支払いが遅れるとしつこい取り立てや悪質な嫌がらせによって精神的に追い込んできます。
ご自身だけでなく、家族や知人、職場にまで被害が及ぶ可能性も高いので、絶対に闇金に手を出してはいけません。もしお金を借りてしまったら、すぐに弁護士へ相談しましょう。
本コラムでは、闇金とはどのような業者のことをいうのか、闇金が使う具体的な手口、お金を借りてしまったときの対処法などについて、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。コラム全文はこちら
カテゴリを選ぶ
- トップページ
- 債務整理 弁護士コラム
- その他
- 老後破産とは? 老後に自己破産するメリットとデメリットを解説