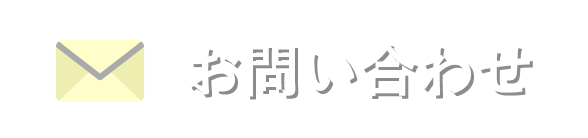- トップページ
- 債務整理 弁護士コラム
- 自己破産
- 自己破産における免責とは? 免責許可が難しいときの3つの対処法
債務整理 弁護士コラム
自己破産における免責とは? 免責許可が難しいときの3つの対処法
- 自己破産
- 自己破産
- 免責

自己破産とは、返済できなくなった借金から解放されるための法的手続きです。
しかし、自己破産を申し立てても、必ず借金の返済義務が免除されるとは限りません。「免責」が許可されて初めて返済義務が免除され、借金から解放されます。
本コラムでは、自己破産における免責とは何か、どのようなケースで免責が許可されないのかについて、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。免責許可を受けるための手続きや、免責許可が難しい時の対処法も解説するので、ぜひ参考にしてください。
1、自己破産における免責とは
自己破産における免責とは、借金の返済義務が免除されることです。免責は個人の破産手続きに特有の制度であり、法人の破産手続きに免責の制度はありません。
そもそも破産手続きは、借金の返済ができなくなった債務者の財産を換金し、各債権者に対して公平な割合で配当するための手続きです。そして、破産手続きが終了すれば法人は消滅するため、法人が持っていた一切の権利や義務も同時に消滅します。それに伴い借金も消滅するのです。
しかし、個人は破産手続きが終了しても個人という存在が消滅するわけではないので、残った借金について免責の制度が設けられています。
具体的には、裁判所は一定の条件の下に免責の許可を決定し(破産法第252条1項)、この決定が確定すると、債務者は残った借金の返済義務を免除されます(同法第253条1項)。
2、自己破産をしても免責が許可されないケース
自己破産をしても免責が許可されないケースとして、大きく分けると次の2つの場合が挙げられます。
-
(1)免責不許可事由がある場合
免責不許可事由とは、破産が認められても免責が認められないケースとして、法律に明記されたもののことです。
具体的には、破産法第252条1項で以下の11個の事由が掲げられています。- ① 不当な財産減少行為
- ② 不当な債務負担行為
- ③ 不当な偏頗弁済
- ④ 浪費やギャンブルのために過大な債務を負担すること
- ⑤ 相手をだまして行う信用取引
- ⑥ 業務帳簿等を隠したり改ざんしたりすること
- ⑦ 虚偽の債権者名簿を提出すること
- ⑧ 裁判所の調査に協力しないこと
- ⑨ 破産管財人等の職務を妨害すること
- ⑩ 過去7年以内に免責許可を受けたこと
- ⑪ その他、破産法上の義務に違反すること
なお、前述した日本弁護士連合会の調査では、免責不許可となったケースは1件もありません。
-
(2)免責を希望する債権が非免責債権の場合
非免責債権とは、債権の性質上、免責の対象とならないものとして法律に明記されたもののことです。
具体的には、破産法第253条1項ただし書きで以下の7個の債権が掲げられています。- ① 租税などの公租公課
- ② 悪意で加えた不法行為に対する損害賠償請求義務
- ③ 故意または重過失による、人の生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償義務
- ④ 養育費や婚姻用等、親族関係に基づく支払義務
- ⑤ 雇用関係に基づく給料の支払い義務等
- ⑥ 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった負債
- ⑦ 罰金等の支払義務
これらの非免責債権は、免責が許可されても支払義務が残ります。したがって、負債の大半が非免責債権である場合には、あまり自己破産をする実益がありません。
3、自己破産で免責が許可されるまでの流れと注意点
免責が許可されるかどうかの判断は、自己破産手続きの最終段階で行われます。最終的に免責許可決定を得るまでの流れは、以下のとおりです。
-
(1)弁護士への依頼
自己破産の申し立ては債務者自身が行うこともできますが、専門的な知識を要するため、弁護士に依頼して行うのが一般的です。依頼を受けた弁護士が発送した受任通知が債権者に届くと、督促や返済がいったん止まります。
それから、依頼者は弁護士の指示に従って必要書類を集め、弁護士と打ち合わせを行います。裁判所に提出する申立書類は、弁護士が作成します。 -
(2)自己破産・免責の申し立て
自己破産を申し立てる際には、「破産手続開始」と「免責許可」という2種類の決定を求める申し立てが必要です。もっとも、債務者が破産手続開始の申立てをすれば、反対の意思を表示しない限り、同時に免責許可の申し立てをしたものとみなされます。
裁判所が用意している書式では、両方を同時に申し立てる形式となっているので、申し立ては一度で済みます。
申し立ての手続きは、弁護士が代理人として行います。ただし、申し立ての際に1~3万円程度の実費を裁判所に納める必要があるため、あらかじめ弁護士の事務所に預けることが必要です。 -
(3)裁判官との面談
申し立てが受理されると、裁判官との面談(債務者審尋)が行われ、借入の経緯や財産状況などについて、詳しく尋ねられます。依頼した弁護士も面談に同席し、裁判官への説明をサポートします。
-
(4)破産手続開始決定
面談の結果、債務者が支払不能状態にあると判断されると、裁判所が破産手続開始決定を行います。債務者にめぼしい財産がなく、免責不許可事由もない場合は、同時に破産手続が廃止され、すぐに免責の手続きに移行します。この流れで進められる破産事件のことを「同時廃止事件」といいます。
-
(5)破産管財人による調査(免責不許可事由がある場合など)
債務者に一定額を超える財産がある場合や、免責不許可事由がある場合には、破産管財人が選任され、管財手続き(破産手続き)が行われます。破産管財人が選任される破産事件のことを「管財事件」といいます。
管財事件となった場合は、破産手続開始決定の際に、20万円程度(少額管財事件の場合)または50万円以上(通常管財事件の場合)の予納金を納めるよう、裁判所から指示されます。
管財手続きでは、破産管財人が債務者の財産を換金して債権者への配当を行うとともに、免責不許可事由の内容や程度について詳しく調査します。 -
(6)免責審尋
東京地裁では、免責手続きで「免責審尋」が開かれます。裁判官と再度面談し、免責に関する事情を確認する手続きです。
他の裁判所では、免責審尋は省略するところが多くなっています。申し立て直後の債務者審尋の際に、免責に関する事情についても併せて確認しているからです。
管財事件の場合は、たいてい最終の債権者集会の際に破産管財人が免責の許可・不許可についての意見を述べます。 -
(7)免責許可決定
免責不許可事由がなければ、裁判所が免責許可決定を行います。
自己破産の申し立てから免責許可決定までに要する期間は、同時廃止事件で3~4か月程度、少額管財事件で4~6か月程度、通常管財事件で6~12か月程度が平均的です。
免責許可決定が確定するまでには、さらに約1か月かかります。
4、免責不許可事由がある場合の3つの対処法
免責不許可事由がある場合には、原則として自己破産を申し立てても借金の返済義務が免除されません。その場合には、以下の対処法が考えられます。
-
(1)裁量免責を求める
免責不許可事由があっても、事情によっては裁判所の裁量により免責が許可されることがあります(破産法第252条2項)。このことを「裁量免責」といいます。
たとえば、浪費やギャンブルのために借金をした場合でも、借金全体の中で占める割合が著しいものではなく、債務者が真摯に反省していれば、裁量免責が認められる可能性があります。
裁量免責を求めるためには、申し立ての段階で陳述書に免責不許可事由の内容を詳しく記載するとともに、反省文も作成して添付することが有効です。 -
(2)免責不許可となった場合は異議申立てをする
免責不許可の決定が出てしまった場合には、1週間以内に「即時抗告」という形で異議申し立てをすることが可能です。
異議申し立てをすると、高等裁判所で再審理されます。債務者としては、免責不許可事由がないか、裁量免責が相当であることを主張し、改めて免責許可の決定を求めることになります。 -
(3)個人再生または任意整理を検討する
裁量免責は必ずしも認められるとは限りませんし、異議申立てで裁判所の決定が覆る可能性も低いのが実情です。
自己破産による免責が難しい場合には、個人再生または任意整理を検討する方が得策といえます。個人再生と任意整理では、借金の使い道や借入の経緯は問われないからです。
個人再生は、裁判所の決定により借金を5分の1~10分の1程度に減額し、3~5年で分割返済する手続きです。多額の借金があるものの、自己破産はできない事情がある場合に向いています。
任意整理は、債権者との直接交渉によって将来利息をカットし、残った借金を3~5年で分割返済する手続きです。多額の借金がある場合にはあまり向いていませんが、家族や親戚などが返済に協力してくれる場合には、検討してみるとよいでしょう。
なお、個人再生には自己破産の場合とおおむね同様の「非免責債権」がある(民事再生法第229条3項、第244条)ことには注意が必要です。
5、まとめ
自己破産を申し立てたケースのほとんどで、免責が許可されているのが実情です。
しかしその理由は、裁量免責が期待できないほどの免責不許可事由がある場合には、もともと他の解決方法を選択しているからだと考えられます。裁量免責が容易に認められることが理由ではありません。
そのため、免責に不安がある場合には、弁護士から専門的なアドバイスを受け、個人再生や任意整理も視野に入れて、最適な解決方法を検討することが重要です。
ベリーベスト法律事務所にご相談いただければ、債務整理専門チームの経験豊富な弁護士が状況に応じて、借金問題の解決までサポートいたします。自己破産を考えているものの免責に不安がある方は、お気軽に当事務所の無料相談をご利用ください。

- 菅谷 良平 パートナー弁護士
- 弁護士会: 東京弁護士会
- 登録番号: 47122
債務整理部マネージャー弁護士として、債務整理・借金問題及びその周辺分野に精通しています。これまで、お客さまの生活再建に向けて、数多くの案件に対応してまいりました。債務整理のご相談は、何度でも無料です。任意整理、自己破産、個人再生など、借金問題についてお悩みの方は、ぜひお気軽に ご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています


同じカテゴリのコラム(自己破産)
-
更新: 2025年12月25日
- 自己破産
- 自己破産
- 官報

自己破産すると官報に名前が出る? 家族にバレる可能性や掲載時期
多額の借金を抱えても、一定の条件を満たす場合は、自己破産によってすべての借金の支払い義務を免れることができます。ただし、自己破産をすると「官報」に氏名や住所が掲載され、全国に公表されてしまいます。
官報に掲載されることが不安で、自己破産するか迷っている方もいるかもしれません。しかし、会社や家族、知人などに見られる可能性は低く、過剰に心配する必要はないでしょう。
本コラムでは、自己破産して官報に掲載されるとどうなるか、掲載時期や掲載される内容、官報に載らずに債務整理する方法などについて、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。コラム全文はこちら -
公開: 2025年12月16日
- 自己破産
- 残クレ
- 破産

残クレで破産したら車は没収? 手放さずに済む? 借金を整理する方法
「残クレの支払いがもう限界……」そのような状況に追い込まれていませんか。
残価設定型クレジット(残クレ)は、月々の負担が軽く見える一方で、契約満了時に高額な残価精算や乗り換え判断を迫られます。生活に欠かせない車なのに、支払いができず自己破産まで考える人も少なくありません。
自己破産になれば、原則として車を手放さなければなりません。しかし、借金の負担を減らす「債務整理」には、任意整理や個人再生など、ほかにも種類があります。状況に応じた最適な手段を選択することで、車を手元に残したまま借金問題を解決できる可能性があるのです。
今回は、残クレ契約中に自己破産すると車がどうなるのか、手放さずに済む方法はあるのか、自己破産以外の借金整理の選択肢などを、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。コラム全文はこちら -
更新: 2025年12月03日
- 自己破産
- 自己破産
- 退職金

自己破産は退職金も処分対象? バレずに手続きを進めるコツを解説
借金問題の解決手段として自己破産を選択すれば、裁判所から免責許可を得られた場合に限り、原則としてすべての借金返済義務が帳消しになります。
ただし、自己破産の強力な借金減額効果を享受するには、自己破産特有の「財産処分」に注意しなければなりません。特に会社員の方が自己破産をする場合は、退職金という大きな財産の扱いが問題になります。
本コラムでは、自己破産をしたときの退職金の取り扱いについて、差し押さえにならないかどうかなど、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。自己破産手続きは、財産処分以外にも注意すべき点が少なくありません。想定外のデメリットを被る事態を避けるためにも、事前に弁護士までご相談ください。コラム全文はこちら
カテゴリを選ぶ
- トップページ
- 債務整理 弁護士コラム
- 自己破産
- 自己破産における免責とは? 免責許可が難しいときの3つの対処法