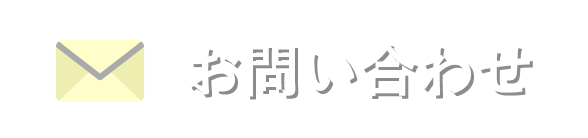- トップページ
- 債務整理 弁護士コラム
- 借金問題
- 親の借金が降りかかったときの対処法をケース別にわかりやすく解説
債務整理 弁護士コラム
親の借金が降りかかったときの対処法をケース別にわかりやすく解説
- 借金問題
- 親の借金

親子であっても、他人の借金を返済する義務は原則としてありません。肩代わりするかどうかは、基本的に子ども自身の判断で自由に決められます。
しかし親の借金でも子どもに返済義務が生じることがあり、借金を放置すると子どもが差し押さえを受けることにもなりかねません。
本コラムでは、親の借金が降りかかってきた場合に、子どもはどのように対処すればよいのかについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
この記事で分かること
- 親の借金で子どもに返済義務が生じる場合とその対処法
- 返済が困難な場合の消滅時効援用や債務整理の利用
1、親の借金の連帯保証人になっている場合の対処法
子どもが親の借金の連帯保証人になっている場合、親が滞納すると債権者は子どもに返済を請求してきます。そのときに子どもがとるべき対処法は、以下のとおりです。
-
(1)原則として返済する必要がある
連帯保証人は、主債務者(実際にお金を借りた人)と同一の債務を負っています。そのため、原則として債権者から請求されたとおりに返済する必要があります。親の滞納が長引いて期限の利益を喪失している場合には、残高を一括で返済しなければなりません。
「先に主債務者の財産を差し押さえるべきだ」、「先に他の連帯保証に請求してほしい(他にも連帯保証人がいる場合)」などの主張はできないことにも注意が必要です(民法第436条、第454条)。 -
(2)交渉で分割払いが認められることもある
一括返済の請求を受けてもすぐに支払えない場合には、分割払いの交渉をすることが考えられます。債権者としても、通常は、すぐに法的措置をとるよりも任意の返済を望むので、分割払いで合意しているケースが数多くあります。
どこまでの交渉に応じるかは債権者の意向次第ですが、返済可能な条件で合意できる場合は、分割で返済していくこともひとつの解決方法です。 -
(3)勝手に連帯保証人にされた場合は返済を拒否できる
子どもが知らないうちに親が勝手に子どもを連帯保証人にした場合は、そもそも連帯保証契約が成立していません。したがって、子どもは返済を拒否できます。
ただし、連帯保証契約を申し込む際には、通常、連帯保証人となる人の本人確認書類や実印、印鑑証明書などが必要です。親がこれらのものを持ち出して使用した場合、金融機関としては親に正当な代理権があるものと信用してしまうこともあります。そのため、親が子どもの本人確認書類や実印、印鑑証明書などを容易に持ち出せるような状況であった場合には、「表見代理」と呼ばれる制度により連帯保証契約が有効に成立する可能性もあります(民法第109条、第110条、第112条)。
もっとも、金融機関が連帯保証契約を結ぶ場合には、連帯保証人となる人に連絡するなどして、保証意思を確認する義務があると考えられています。したがって、何の連絡もなく勝手に連帯保証人にされた場合には、返済を拒否できる可能性が高いといえます。
拒否しても請求が止まらない場合には、債務不存在確認訴訟を提起することが有効です。
なお、少しでも返済に応じると、親の無権代理行為を追認(事後承諾)したものとみなされ、子どもに連帯保証人としての返済義務が生じることにも注意が必要です(民法第113条)。
2、親が子ども名義で借金した場合の対処法
親が子ども名義で借金した場合には、子どもが名義の使用を承諾していたかどうかによって対処法が異なります。
-
(1)名義を貸した場合は返済する必要がある
名義の使用を承諾していた場合、債権者に対しては親ではなく子どもが返済義務を負います。なぜなら、自分の名義で借金することに同意している以上、債権者と子どもとの間で金銭消費貸借契約が有効に成立しているからです。
そのため、債権者から返済を請求された場合には拒否できません。親子の間で「親が返済する」「絶対、子どもに迷惑はかけない」などと約束していても、債権者には対抗できないのです。実務上、このことを「名義貸し」といいます。 -
(2)親が勝手に借りた場合は返済を拒否できる
名義の使用を承諾せず親が勝手に借りた場合、子どもには借金する意思がないため契約は成立しません。したがって、返済義務は負わないのが原則です。
ただし、親が子どもの代理人と名乗って借金をした場合は、勝手に連帯保証人にされた場合と同様の問題が生じます。つまり、本人確認書類や実印、印鑑証明書などを親が容易に持ち出せるような状況であった場合には表見代理が成立し、子どもに返済義務が生じる可能性があるということです。
債権者からの請求を止めるためには債務不存在確認訴訟の提起が考えられることと、追認すると子どもに返済義務が生じてしまうことも、勝手に連帯保証人にされた場合と同様です。
3、親が借金を抱えたまま死亡したときの対処法
親が借金を抱えたまま死亡すると、原則として子どもに(配偶者がいれば配偶者にも)借金の返済義務が引き継がれます(民法第896条)。
しかし、相続放棄または限定承認をすれば、借金の返済義務から免れることが可能です。
-
(1)相続放棄をする
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の権利義務の承継を全面的に拒否することです(民法第939条)。相続放棄をすれば、被相続人の借金を引き継がなくてすみますが、プラスの遺産があったとしても一切受け取れないことに注意しなければなりません。プラスの遺産の総額よりも借金額の方が明らかに大きい場合には、相続放棄が有効です。
相続放棄をするためには、原則として相続開始を知ったときから3か月以内に、家庭裁判所で申述という手続きをする必要があります(民法第915条1項本文、第938条)。通常は親が亡くなったときから3か月間が申述期間となります。
その後に借金が発覚した場合でも、借金があることを知ったときから3か月が経過するまでは相続放棄が認められる可能性があります。ただし、この場合には家庭裁判所から詳しい状況を尋ねられたりするため、手続きの難易度が高くなることに注意が必要です。 -
(2)限定承認をする
限定承認とは、被相続人が残したプラスの財産の限度においてのみ、借金などマイナスの財産も引き継ぐことです(民法第922条)。相続人は、遺産以外の財産を使ってまで親の借金を返済する必要がなくなります。親の借金の残高が正確にわからない、他にも借金がありそう、といった場合には限定承認が有効です。
限定承認の申述手続きは、相続開始を知ったときから3か月以内に、相続人全員で行う必要があります(民法第923条)。そのため、自分の他にも相続人がいる場合には、速やかに話し合って方針を決めることが重要です。
4、親から降りかかってきた借金を払えないときの対処法
これまでに紹介した方法で親の借金の返済義務を回避できない場合は、以下の対処法で解決を図ることになります。
-
(1)消滅時効を援用する
親が借金を残して亡くなった場合などでは、債権者との取引が長期間にわたって途絶えていて、消滅時効にかかっていることも少なくありません。借金の時効期間は基本的に最後の取引日が起算点となり、以下の期間が経過すると消滅時効が完成します。
令和2年3月31日以前に借りた場合 令和2年4月1日以降に借りた場合 貸金業者からの借金 5年 5年 個人からの借金 10年 5年
借入日や最後の取引日がわからない場合は、債権者に連絡して取引履歴などの資料の開示を請求しましょう。その際、返済義務を認めたり、少しでも返済したりすると、消滅時効を主張できなくなることに注意が必要です(民法第152条1項)。
消滅時効を主張して返済を拒否するためには、時効の援用を行う必要があります(民法第145条)。その方法は、「消滅時効援用通知書」を作成し、内容証明郵便で債権者へ送付するのが一般的です。 -
(2)債務整理をする
親の借金の消滅時効が完成しておらず、子どもも支払えないほどの金額である場合でも、債務整理をすれば解決できます。
債務整理とは、法律にのっとって借金を減額または免除してもらうことが可能な手続きのことです。主に、任意整理・個人再生・自己破産という3種類の手続きがあります。どの手続きが適しているかは、借金総額だけでなく、返済義務を負った子どもの収入や財産状況、職業、今後の生活設計などによって異なってきます。
手続きの選択を誤るとスムーズに解決できないおそれがあるため、債務整理の実績が豊富な弁護士に相談し、アドバイスを受けた方がよいでしょう。方針が決まり、弁護士に債務整理を依頼すれば受任通知が送付されるので、債権者からの督促はいったん止まります。債務整理の手続きはすべて弁護士が代行して的確に進めるので、安心です。
5、まとめ
親の借金は、原則として親自身にのみ返済義務があり、子どもには返済義務はありません。しかし、子どもが連帯保証人になっている場合や、子どもの名義で借金をした場合、子どもが相続した場合などでは、子どもに返済義務が生じることがあります。
子どもに返済義務があるかどうかの判断や、返済義務を負う場合の解決方法を検討する際には、専門的な知識や経験が要求されます。そのため、弁護士にご相談の上で対処することをおすすめします。
ベリーベスト法律事務所では、借金問題に関するご相談は何度でも無料でご利用可能です。借金問題についての知見が豊富な弁護士が詳しい事情を伺い、最善の対処法を提案します。お困りの際は、お気軽に無料相談をご利用ください。

- 萩原達也 代表弁護士
- 弁護士会: 第一東京弁護士会
- 登録番号: 29985
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
債務整理、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金請求など、借金問題についてのお悩み解決を弁護士がサポートいたします。債務整理のご相談は何度でも無料です。ぜひお気軽に お問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています


同じカテゴリのコラム(借金問題)
-
更新: 2025年12月03日
- 借金問題
- 借金
- 一本化

借金の一本化はデメリットもある! 手続き方法や事前に確認したい点
複数の銀行や消費者金融などから借金をしているときは、借金の一本化をすることで返済負担を軽減できる可能性があります。
ただし、借金を一本化しても、借金がなくなるわけではありません。すぐに返しきれないほどの借金があるときは、弁護士のサポートを受けながら債務整理を行いましょう。
本記事では、借金一本化のメリットやデメリット、債務整理との違いなどをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。コラム全文はこちら -
公開: 2025年11月26日
- 借金問題
- 旦那に内緒で
- 借金

夫に内緒で借金をした! バレずに返済可能? 債務整理などの対処法
自由に使えるお金が少ない主婦は、欲しいものを買うために借金をしたり、生活費が足りず、穴埋めのためにやむを得ず借金をしてしまうことがあります。
夫に内緒で借金をした場合、何とか夫にバレずに借金を返済していきたいと考える方も多いでしょう。借金問題を解決するには、さまざまな方法があります。なかには、夫にバレずに返済できる手段も存在しますので、早めに適切な対応をとることが重要です。
本コラムでは、夫に内緒で作った借金を返済する方法や債務整理などの対処法について、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。コラム全文はこちら -
公開: 2025年11月19日
- 借金問題
- 借金
- 減らない

借金が減らない! よくある6つの原因と法的な解決策を弁護士が解説
「毎月きちんと返済しているのに、なぜか借金が減らない……」このようなお悩みを抱えている方は、少なくありません。
借金がなかなか減らないのは、利息の仕組みや返済方法、借入先の数などに原因があることが多いのが実情です。特に、支払方法を「リボ払い」に設定している場合や「自転車操業(=借金返済のために新たな借金をする状態)」に陥っていると、いくら返しても元金が減らず、返済のゴールが見えなくなってしまいます。
本コラムでは、借金が減らない6つの原因と、完済を目指すためにできる対策などについて、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。コラム全文はこちら
カテゴリを選ぶ
- トップページ
- 債務整理 弁護士コラム
- 借金問題
- 親の借金が降りかかったときの対処法をケース別にわかりやすく解説