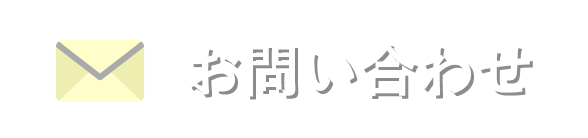- トップページ
- 債務整理 弁護士コラム
- 任意整理
- 2回目の任意整理(再和解)は可能? できない場合の対処法とは
債務整理 弁護士コラム
2回目の任意整理(再和解)は可能? できない場合の対処法とは
- 任意整理
- 任意整理
- 再和解

任意整理は将来利息のカットや返済期間の延長などによって、毎月の返済の負担を軽減することができる債務整理の方法です。他の債務整理よりも手続きや費用の負担が軽く、メリットが大きい解決手段といえます。
しかし、通常は3年~5年にわたって返済を続ける必要があり、その間に何らかの事情で返済が難しくなることもあるでしょう。
そんなとき、債権者と和解した内容を変更して再和解をすることはできるのでしょうか。今回は、すでに任意整理で和解した借金の再和解が可能かどうか、できない場合はどうすればよいのかについて解説します。
1、任意整理した後に再和解はできる?
一度任意整理で返済の負担を軽減してもらったにもかかわらず、その後に再び交渉して再和解してもらうことはできるのでしょうか。
-
(1)法律上の制限はない
任意整理に法律上の回数制限はないので、再和解も可能です。
そもそも任意整理は債権者と直接交渉し、合意することで今後の返済額や返済方法を変更する手続きです。債権者の合意が得られるのであれば再和解も、再々和解もできます。 -
(2)再和解できるかどうかは債権者次第
任意整理では、債権者に対して合意を強制することはできません。そのため、再和解できるかどうかは債権者の意向次第ということになります。
債権者の中には、任意整理では貸し倒れの処理ができないことや、一度和解したにもかかわらず支払えなくなる債務者は信用できないなどの理由で、再和解に応じないところもあります。
多くの貸金業者は、債権額や支払えなくなった理由、1回目の和解内容など、さまざまな事情を考慮してケース・バイ・ケースで再和解に応じるかどうかを検討します。
結論として、再和解はできる場合もあればできない場合もあるということです。 -
(3)和解条件は厳しくなることが多い
再和解が可能なケースでも、1回目の和解と同じように借金を減額してもらうのは難しいことが多いのが実情です。
ほとんどの場合はすでに将来利息はカットされているため、もう減額できる対象がありません。1回目の和解後に延滞をした場合には、その遅延損害金も加算しなければ再和解に応じてもらえないのが一般的です。その場合、1回目の和解内容よりも毎月の返済額が増えてしまいます。
2、任意整理後の再和解ができないケース
任意整理後の再和解ができないケースには、債権者側に原因がある場合と、債務者側に原因がある場合とがあります。以下で具体的にみていきましょう。
-
(1)債権者が応じない
債権者が再和解に応じないケースとしては、会社の方針として再和解に応じないという場合もあれば、個別の事情に照らして返済の見込みがないと判断される場合もあります。
基本的に再和解に応じてくれる債権者でも、以下のような事情がある場合には再和解に応じない可能性が高くなります。- 1回目の和解後、間もない時期(6か月未満など)に再和解を申し出た
- 延滞が長期(3か月以上など)に及んでいる
- やむを得ない事情がないのに延滞を繰り返している
一方で、以下のようにやむを得ない事情があると認められる場合は、再和解に応じてもらえる可能性が高いといえます。
- リストラに遭ったり、病気や事故で収入が減った
- 和解後の返済期間の半分以上にわたって延滞することなく返済していた
-
(2)収入が大幅に減ってしまった
1回目の和解後に収入が大幅に減ってしまい、回復する見込みが乏しい場合は、基本的に再和解はできません。
たとえリストラや病気、事故などやむを得ない事情による場合であっても、この先、返済資金を調達できる見込みがないのであれば債権者から返済の見込みなしと判断されるからです。 -
(3)債務総額が大幅に増えてしまった
1回目の任意整理で対象外とした他社の借金で延滞して遅延損害金が加算されたり、クレジットカードを利用したりすると、債務総額が大幅に増えることもあります。
収入が減らなくても債務総額が大幅に増えてしまうと、やはり債権者は返済の見込みなしと判断して、再和解に応じてもらえない可能性が高くなります。
3、任意整理後の延滞を放置するとどうなる?
任意整理後の返済を延滞してしまった場合、そのまま放置すると以下のリスクを負うことになります。
-
(1)一括返済を要求される
延滞が一定期間続くと、残額の一括返済を要求されます。
多くの場合は「返済を2回分怠ると期限の利益を失い、残額を一括で支払う」という合意をしているはずです。ケースによっては「1回でも返済を怠るとただちに残額を一括で支払う」という合意をしている場合もあります。
期限の利益とは、決められた支払期日までは返済しなくてよいという債務者の利益のことです。期限の利益を失うと分割払いが認められなくなるため、一括で返済しなければならないのです。
和解書の「期限の利益喪失条項」を見直して、何回まで延滞を待ってもらえるかを確認しましょう。 -
(2)遅延損害金がかかる
延滞すると遅延損害金がかかります。消費者金融との任意整理では、年利14.6%~20%程度の割合で遅延損害金が加算されるのが一般的です。
期限の利益を喪失した後、完済するまで遅延損害金がかかり続けます。200万円の元金を3か月延滞した場合、年利14.6%とすると7万3000円もの遅延損害金が加算されます。 -
(3)差押えを受けることも
延滞を続けていると、最終的には給料や預金口座などの財産を差し押さえられる可能性があります。
ただし、差押えはある日突然、受けるわけではありません。ほとんどは、事前に債権者から裁判を起こされます。どうせ返済できないと考えて裁判を放置していると、債権者の主張通りの判決が言い渡されて確定し、差押えの手続きに進んでしまいます。
裁判を起こされても、裁判上の和解で分割払いを認めてもらうこともできます。和解条件は1回目よりも厳しくなりがちですが、裁判所から書類が届いたときには放置せず、適切に対応する必要があります。
4、任意整理の再和解ができないときの対処法
任意整理の再和解ができないときでも、他の方法で借金を解決できます。諦めずに、以下の対処法を検討しましょう。
-
(1)他社の借り入れも追加で任意整理をする
他社からも借金があり、まだ任意整理をしていない借入先がある場合は、その借金も任意整理することが考えられます。このように1回目の任意整理で手続きから除外していた債権者について追加で任意整理をすることを「追加介入」といいます。
他社への返済の負担が軽くなれば、再和解ができなくても全体的に返済可能となる可能性があります。 -
(2)個人再生をする
追加介入ができない場合や、追加介入をしても返済が難しい場合は、個人再生をすることが考えられます。
個人再生とは、裁判所に申し立てることによって借金が大幅に減額される手続きのことです。最大で借金総額を100万円にまで減額できる可能性があります。
たとえば、500万円の借金を抱えている場合、任意整理では元金は基本的にカットできないため、毎月8万4000円(60回払いの場合)~13万9000円(36回払いの場合)ほどを返済していかなければなりません。
一方、個人再生で100万円に減額されれば、毎月の返済額は1万7000円(60回払いの場合)~2万8000円(36回払いの場合)ほどですみます。 -
(3)自己破産をする
個人再生でも3年~5年は返済を継続する必要があるので、収入が乏しい場合には利用できません。そんなときは、自己破産を検討しましょう。自己破産では、一定の条件を満たせば、裁判所の決定によってすべての借金の返済義務が免除されます。
5、まとめ
任意整理後の再和解は多くの場合で可能ですが、1回目の和解よりは条件が厳しくなりがちです。事情によっては再和解できないこともあります。
そんなときでも、追加介入や個人再生、自己破産などによって借金問題の解決は可能です。早期に対処する方が解決方法の選択肢が多くなります。返済が苦しくなったときは、早めに弁護士に相談するなどして最適な解決方法を選ぶことをおすすめします。
ベリーベスト法律事務所では、借金問題については何度でも無料でご相談いただけます。任意整理後の再和解をお考えの場合の他、借金でお悩みのときはお気軽にご相談ください。

- 萩原達也 代表弁護士
- 弁護士会: 第一東京弁護士会
- 登録番号: 29985
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
債務整理、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金請求など、借金問題についてのお悩み解決を弁護士がサポートいたします。債務整理のご相談は何度でも無料です。ぜひお気軽に お問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています


同じカテゴリのコラム(任意整理)
-
更新: 2025年12月25日
- 任意整理
- 任意整理
- クレジットカード

任意整理するとクレジットカードはどうなる? 注意点と対処法
任意整理をすると、クレジットカードを今までどおりに利用できなくなります。キャッシュレス決済を活用していると、クレジットカードが使えなくなれば、不便に感じることも多いことでしょう。
しかし、任意整理をしてから一定期間が経過すれば、再びクレジットカードが使えるようになります。具体的にいつから使えるのか、カードの新規発行はできるのかといったことが気になるかもしれません。
そこで本コラムは、任意整理をするといつからいつまでクレジットカードが使えなくなるのか、任整理対象外のカードや家族カードはどうなるか、任意整理後のクレジットカード新規作成の注意点などを、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。コラム全文はこちら -
更新: 2025年12月03日
- 任意整理
- 任意整理
- 繰り上げ返済

任意整理後に繰り上げ返済はできる? デメリットもあることに注意
任意整理では、将来利息(残っている借金に対して発生し、完済まで払う予定の利息)をカットして、残った元金を3年~5年で分割返済していくことが一般的です。しかし、繰り上げ返済(元金の一部や全部を前倒しで返済すること)をして、早く完済したいとお考えの方もいるでしょう。
任意整理後に繰り上げ返済をすることは可能です。しかし、メリットが少ない反面、いくつかのデメリットがあるため、繰り上げ返済には慎重になる必要があります。
本コラムでは、繰り上げ返済をする際の注意点と、任意整理後に繰り上げ返済をするメリット、デメリットについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が紹介します。コラム全文はこちら -
更新: 2025年10月24日
- 任意整理
- 任意整理
- 必要書類

任意整理の必要書類は? 契約書・領収書を紛失したら? 弁護士が解説
任意整理をする際、必要な書類は何か、用意するといい書類はあるかなど、準備に不安がある方もいるでしょう。また、契約書や領収書などが手元になく、任意整理ができないのではないかと思われている方もいるかもしれません。
しかし、いくつもの金融会社から借金をしていて、すべての書類がそろっていない状態だったとしても、弁護士に依頼すれば任意整理が進められる可能性があります。
本コラムでは、任意整理の必要書類や、あわせて用意するといい書類について、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。コラム全文はこちら
カテゴリを選ぶ
- トップページ
- 債務整理 弁護士コラム
- 任意整理
- 2回目の任意整理(再和解)は可能? できない場合の対処法とは