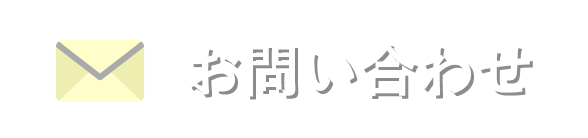- トップページ
- 債務整理 弁護士コラム
- 借金問題
- 法定利率とは|借金への影響は? 約定利率との違いや計算方法を解説
債務整理 弁護士コラム
法定利率とは|借金への影響は? 約定利率との違いや計算方法を解説
- 借金問題
- 法定利率とは

民法で決められている「法定利率」は、借金の返済が遅れた場合の遅延損害金の計算に用いられることがあります。現在の法定利率は年3%です。
ただし、銀行や消費者金融からの借り入れでは、あらかじめ契約で決めた「約定利率」に基づいて遅延損害金が計算されます。約定利率は法定利率よりも高い場合が多く、返済が遅れると高額の遅延損害金が発生するおそれがあります。借金の返済が困難になった場合は、弁護士に相談して債務整理の手続きを検討することが大切です。
本記事では法定利率の概要や、約定利率との違い、計算方法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、法定利率とは? どんなときに適用される?
民法では「法定利率」が決められています。借金の遅延損害金(=返済が遅れたときにペナルティーとして支払うお金)を計算する際などに、法定利率が適用されることがあります。
-
(1)法定利率とは
「法定利率」とは、民法第404条に基づき、利息の計算などに適用される基準利率のことです。契約当事者の間で利率を決めていない場合や、損害賠償などで利率の合意がない場合に、法定利率が適用されます。
たとえば、AさんがBさんの物を壊してしまい、100万円の損害賠償を支払う義務を負ったとします。
本来であれば、Aさんは物を壊したその日に、Bさんに対して100万円を支払わなければなりません。支払いが遅れるほど、Bさんにとっては経済的な不利益が大きくなります。
AさんとBさんの損得を埋めるため、1日ごとに「遅延損害金」が発生することになっています。AさんはBさんに対し、100万円に加えて、一定の利率で計算した遅延損害金を支払わなければなりません。
AさんとBさんの間で利率を合意していない限り、遅延損害金には法定利率が適用されます。
現在の法定利率は年3%であるため、元本100万円の場合、年間3万円、1日あたり約82円の遅延損害金が発生することになります。 -
(2)法定利率が適用されるのはどんなとき?
利息が生じる債権(=金銭を請求する権利)について、当事者間で利率を決めていないときは、法定利率が適用されます(民法第404条第1項)。
法定利率が適用されるケースとしては、以下の例が挙げられます。・借金の返済が遅れた場合
返済期日の翌日から返済日までの間、遅延損害金が発生します。遅延損害金の利率を合意している場合を除き、法定利率に基づいて計算されます。
・交通事故や暴行など、不法行為に基づく損害賠償責任が生じた場合
故意または過失によって他人に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければなりません。不法行為がなされたその日から支払日までの間、遅延損害金が発生します。遅延損害金の利率を合意している場合を除き、法定利率に基づいて計算されます。
・損害賠償などの金銭を前倒しで受け取る場合
失われた将来の収入(=逸失利益)や、将来的にかかる介護費用の損害賠償は、当事者が和解する際に前倒しで精算するのが一般的です。
この場合、将来の時点で受け取るべき金額を、支払いを受ける時点での価値まで割り引きます(=中間利息控除)。中間利息控除としての割引には、法定利率が用いられます。 -
(3)法定利率は3年ごとに見直される|現在は年3%
現在の法定利率は「年3%」です。これは令和2年4月1日に施行された民法改正により導入されたもので、令和11年3月31日までは、法定利率が年3%で維持されることが決まっています。
法定利率は、当初の固定制(年5%)から変動制に変更され、3年ごとに見直される仕組みとなっています。
令和11年4月1日以降の法定利率は、銀行による貸し付けの平均利率を参照して増減される可能性があります。
2、銀行や消費者金融からの借金にも、法定利率は適用される?
借金の利息や遅延損害金には、一定の条件下で法定利率が適用されることがあります。ただし、銀行や消費者金融からの借金については、事前に取り決めた「約定利率」が原則として適用されます。
-
(1)利息と遅延損害金の違い
「利息」とは、貸付日から返済期限までの間、借主が借入金の利用に対して支払う対価です。
一方、「遅延損害金(遅延利息)」とは、返済期限を過ぎた後に発生する追加的な損害金で、いわば『延滞料』のような性質を持ちます。
返済期限までは利息が発生し、返済期限の翌日以降は遅延損害金が発生します。 -
(2)借金の利息に法定利率が適用されるケース
借金の利息に法定利率が適用されるのは、以下の①および②の条件をいずれも満たす場合に限られます。
- ① 貸主と借主の間で、利息を発生させる旨の合意をしたこと
- ② ①の利息について、以下のいずれかに該当すること
(a)具体的な利率の合意がなされていない
(b)法定利率を適用する旨の合意がなされた
なお、そもそも利息を発生させることについて合意していない場合には、貸主は借主に対して利息を請求できません。
また、貸主と借主の間で具体的な利率を合意している場合には、原則としてその利率が適用されます。合意によって決められた利率を「約定利率」といいます。
ただし、借金の利息の約定利率については、利息制限法によって以下の上限が設けられています。
【利息制限法による利率の上限】元本の額 利息の約定利率の上限 10万円未満 年20% 10万円以上100万円未満 年18% 100万円以上 年15% ※これを超える利息の契約は、超過部分が無効になります。
-
(3)借金の遅延損害金に法定利率が適用されるケース
借金の遅延損害金に法定利率が適用されるのは、以下の①または②のいずれかに該当するケースです。
- ① 貸主と借主の間で、遅延損害金の具体的な利率が合意されていない
- ② 貸主と借主の間で合意した遅延損害金の利率(=約定利率)が、法定利率を下回っている
なお、貸主と借主の間で合意した遅延損害金の約定利率が法定利率以上であれば、原則として約定利率が適用されます。
ただし、遅延損害金(賠償額の予定)の上限は、通常の利息の上限(利息制限法第1条)の1.46倍までとされています。
【利息制限法による遅延損害金の上限】元本の額 遅延損害金の上限 10万円未満 年29.2%(=20%×1.46) 10万円以上100万円未満 年26.28%(=18%×1.46) 100万円以上 年21.9%(=15%×1.46) 営業的金銭消費貸借の場合
※銀行や消費者金融のローンなど上記にかかわらず、年20% ※上記の上限を超えた遅延損害金は、超過部分が無効になります。
-
(4)銀行や消費者金融からの借金には、法定利率ではなく約定利率が適用される
銀行や消費者金融が提供するローンにおいては、利息と遅延損害金について、それぞれ利息制限法の範囲内で約定利率が決められているケースが大半です。
したがって、銀行や消費者金融からの借金については、法定利率ではなく約定利率が適用されます。
なお、約定利率が利息制限法の上限を超えている場合、超過部分が無効になります。
約定利率は、銀行や消費者金融と結んだ契約書や貸付条件書に明記されています。「利息」「遅延損害金」の条文中や、その条文が引用している貸付条件の明細を確認してみましょう。
また、銀行や消費者金融のウェブサイトのマイページにログインすれば、約定利率を確認できることがあります。
3、借金の遅延損害金の仕組み|法定利率・約定利率による計算方法も解説
借金の返済期限を過ぎると、返済が完了するまでの期間に応じて、日割りで遅延損害金が発生します。
たとえば、令和7年6月30日までに100万円を返済しなければならないところ、期限に遅れてしまい、実際に返済を行ったのが、3か月後の同年9月30日だったとします。
この場合、返済期限の翌日である7月1日から、返済をした9月30日までの92日間について遅延損害金が発生します。
遅延損害金の額は、法定利率または約定利率を用いて日割り計算を行います。計算式は以下のとおりです。
※貸主と借主の間で、法定利率以上の約定利率が合意されている場合には、原則としてその約定利率が適用されます。それ以外の場合は、法定利率が適用されます。
上記の100万円の返済遅延のケースにおいて、年20%の約定利率が適用される場合と法定利率が適用される場合では、遅延損害金の額はそれぞれ以下のように計算されます。
※以下の計算例では、小数点以下を四捨五入しています。
遅延損害金の額
=100万円×20%(約定利率)÷365日×92日
=5万411円
② 法定利率が適用される場合
遅延損害金の額
=100万円×3%(法定利率)÷365日×92日
=7562円
4、借金の返済が難しいときは「債務整理」という選択肢も|弁護士に相談を
借金の返済が難しくなったら、弁護士に相談して「債務整理」を行いましょう。
債務整理は、借金の負担を軽減または免除してもらえる可能性がある手続きです。主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類があります。
-
(1)任意整理
「任意整理」は、裁判所を通さず、弁護士が銀行や消費者金融などの債権者と交渉して、借金の軽減を目指す手続きです。債権者の同意が得られれば、利息や遅延損害金のカット、返済スケジュールの変更などが認められます。
比較的短期間で、生活への影響やコストを抑えながら取り組むことができます。 -
(2)個人再生
「個人再生」は、裁判所に申し立てをして借金の減額を認めてもらう手続きです。減額の内容などを決めた再生計画について、債権者の決議と裁判所の認可を得られれば、その内容に従って借金が減額されます。
個人再生は、安定した収入のある人が多額の借金を負っている場合に適した手続きです。住宅ローンのある持ち家を手放さずに済む「住宅資金特別条項」という制度も利用できます。 -
(3)自己破産
「自己破産」は、返済能力がないと判断された場合に、裁判所を通じて借金の返済義務を免除してもらう手続きです。高価な財産などは処分されますが、最終的に借金はゼロになります。
借金が多すぎる場合や、無職または定職に就いていない場合などには、自己破産が有力な選択肢となります。財産は原則として処分されるものの、生活に必要な最低限の財産は処分されずに残ります。
債務整理の各手続きには、それぞれメリットとデメリットの両面があります。借金問題を根本的に解決するためには、適切な手続きを選択することが大切です。債務整理には複数の選択肢があるため、弁護士に相談して適切な方法を検討することが重要です。
5、まとめ
法定利率は民法で決められた基準利率で、利率の合意がない場合などに適用されます。一方、約定利率は取引の当事者間で合意した利率で、借金の利息や遅延損害金の計算に使われるのが一般的です。
返済期限に遅れると、遅延損害金が日々発生し、借金の総額が増える原因になります。督促が続くことにより精神的負担も大きくなり、最終的には財産の差押えに至る可能性もあります。
借金の返済に悩んでいる場合は、弁護士に相談して債務整理の可能性を検討してみることが大切です。
ベリーベスト法律事務所は、借金問題や債務整理に関するご相談を受け付けております。返済にお悩みの方は、一人で抱え込まずにお気軽にご相談ください。あなたにとって無理のない解決策を、一緒に探っていきましょう。

- 萩原達也 代表弁護士
- 弁護士会: 第一東京弁護士会
- 登録番号: 29985
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
債務整理、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金請求など、借金問題についてのお悩み解決を弁護士がサポートいたします。債務整理のご相談は何度でも無料です。ぜひお気軽に お問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています


同じカテゴリのコラム(借金問題)
-
更新: 2026年02月09日
- 借金問題
- 闇金
- 借金

ヤミ金の借金はどこに相談すべき? 正しい対処法を弁護士が解説
借金を返済するお金がなく、生活するにも苦しい状況になると、「どこからもお金を借りられないから、ヤミ金に頼るしかない」と考えてしまう方も少なくありません。
しかし、ヤミ金は法律に違反して営業している違法業者であり、法外な利息の請求や家族・職場を巻き込むような過酷な取り立てなど、深刻なトラブルを引き起こすリスクがあります。中には、一度借りてしまったことで個人情報が流出し、別のヤミ金に狙われ続けるケースもあるため、ヤミ金での借金は絶対にしてはいけません。
本コラムでは、ヤミ金で借金するとどうなるのか、実際に借りてしまった場合の正しい対処法や相談できる公的機関・窓口について、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。コラム全文はこちら -
更新: 2025年12月03日
- 借金問題
- 車
- ローン
- 滞納

車のローンを滞納するとどうなる? 支払えないときの解決方法とは
マイカー購入は、わたしたちが行う取引のなかでは、高額取引といえます。そのため、多くの人は、キャッシュでの買い物(一括払い)ではなく、ローンを組んで車を購入することが多いでしょう。
しかし、長期間でのローンを組めば、予測外の事情変更などが原因で、返済が苦しくなりローンを滞納する可能性があります。
そこで、今回は、車のローンを滞納してしまったときの流れや解決方法について解説していきます。車の購入を控え、今後のローンの支払いが気になるという人や、すでにローンの返済が苦しくなってしまった人はぜひ参考にしてください。コラム全文はこちら -
更新: 2025年12月03日
- 借金問題
- 借金
- 一本化

借金の一本化はデメリットもある! 手続き方法や事前に確認したい点
複数の銀行や消費者金融などから借金をしているときは、借金の一本化をすることで返済負担を軽減できる可能性があります。
ただし、借金を一本化しても、借金がなくなるわけではありません。すぐに返しきれないほどの借金があるときは、弁護士のサポートを受けながら債務整理を行いましょう。
本記事では、借金一本化のメリットやデメリット、債務整理との違いなどをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。コラム全文はこちら
カテゴリを選ぶ
- トップページ
- 債務整理 弁護士コラム
- 借金問題
- 法定利率とは|借金への影響は? 約定利率との違いや計算方法を解説